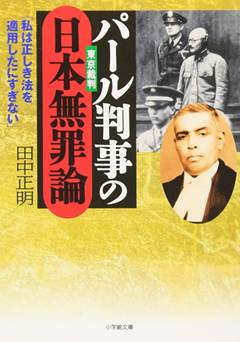2025�N9��
���� �G�߂̂����A
�n�����g��������ċv�����̂ł����C���N�̏����ُ͈�Ɏv���܂����D�wAI�x�ɐq�˂Ă݂�ƁC���N��8�����É��̓����ō��C���́C�̉��ł���36�x��������20���]����C�K�オ��ɔM���Ȃ�C�����ɂ�40�x���܂����D
9���ɂȂ��Ă����ς�炸�̍����������Ă���܂����C�F�l���������߂����ł��傤���c�c�D
�܂��Ȃ�84���}����M�҂ɂ́C���̏��������܂����D�ł��邾���O�o�͔����C�G�A�R���̌����������ɕ��������ĉ߂����܂����D
���ɂƂ���8���Ƃ����̂́C�w���N���̓�M�B�̉ċx�݁x���w�����m�푈�̏I��������x�Ƃ�����̈Ӗ��ŁC���ʂȌ��ł��D
����͋G�߂̂����A�Ƃ��āC�w8���ɑ��鎄�̎v���x��\���q�ׂ����Ǝv���܂��D
������ɂȂ�܂��̂ŁC�ȉ��̂悤�ȏ͗��Ăł��b�����܂��D
[1] 70�]�N�O��8���̎v���o
���̏��N������߂�������M�B�C�ɓߒJ�̓����̋��ؑ��ł́C�W����500m�Ƃ�����������C�������͂������̂́C��C�͊������Ă���C�؉A�ł͗������߂����܂����D���̋C�C�����E���E�ь�Ƃ���3��ނ̉ʕ����l���Ƃ�����Ղ������炵���̂ł����D
7���̉��{�̊l�肽�Ă̔����́C�o���o���Ƃ����鎖���o���C��̓|�����Ǝ��܂��D���̏�Ԃ̓����M�҂͑�D���ł����D���̓���8���ɂȂ�Ɠs��̓X���̔����̂悤�ɉʓ����_�炩�ɂȂ�C�ʏ`���������点�Ȃ���H�ׂ��ԂɂȂ��Ă��܂��܂��D�F�l�������x�̓o���o���Ƃ����铍�̂��������𖡂���Ē��������v���܂��D
 AI���`��������
AI���`��������
�c�A���ƈ��̋G�߂��w�_�ɋx�Ɂx�̂���c�ɂ̉ċx�݂́C8��1������~������16���܂łł����D�ċx�݂͐�km��ɂ���k�J�̑��ʼnj���̂��y���݂ł����D���̐�ɂ͓`��������C�w���[�ȍ~�ɉj���Ɨ������x�ƌ����Ă��܂����D���R������������8��10�����炢�ɉj���ɍs���܂������C�����̒��Ԃ͂��炸�C��̐����₽�������܂����D���̗₽�������̂��N�����₷���Ƃ����x�����ƒm��܂����D
�P���8��15���ɂ͍Z��Ŗ~�x�肪�s���C���߂��C�镗���S�n�悩�����L��������܂��D
�����Ă��~���߂���Ɩ�Ԃ͂����Ɨ������Ȃ�C�|���z�c�𒅂ĐQ����悤�ɂȂ�܂��D��M�B�̉Ă͒Z���C�����n���̂�����X�ł����D
��w�i�w���Ă��獡���܂ŁC�قږ��É��Ő������Ă��܂����C���É��̉Ă͒����������������ł��D����́C���N���̐M�B�̉Ă��S�Ɏc���Ă���̂ł��D
[2] 8���Ƃ����Α����m�푈���I��������ł�
2-1. �I�풼�O������̕����܂ł̏o����
���N�͏I��80�N�ڂɓ�����܂�����C���������V�������_����̎��g�݂����邩�Ɗ��҂��Ă���܂������C�S���ʔN�ʂ�ŁC�w�푈�͔ߎS���I�x�w��x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ��I�x�Ƃ��������̘_���ɏI���܂����D
�b�͔�т܂����C�ŋ߃C���^�[�l�b�g���֗��ɂȂ�܂����D�����wCopilot�x���wGemini�x�����wAI�x�����s���Ă��܂��D
�M�҂��g���n�߂āC���̔\�͂ɋ����Ă���܂��D�������������ƁC�l�b�g�ɂ���c��Ȏ�������b���܂Ƃ߂ĕ��Ă���܂��D
�C�ɂȂ��Ă�������Ŏ��₷��ƁC���̉̓Y�o�b���w�I���ˊт����x�������w����ς�I�x�w�����I�x�ƌ��������z���N�������C�M�҂͍��n�}���Ă��܂��D
�����̎Љ�Ɛ��������邽�߂ɁC���X���X�wAI�̊��x�͕ω����Ă���l�q�ł����C���̂Ƃ���C���{�̈ӌ����Ƃ��C���̒��̗��s�肾�Ƃ��C���{�Ɠ��̜u�x�Ȃǂ��������Ȃ��Y�o�b�Ƃ������܂�������悤�ł��D���ЊF���܂��C�����̋K�����|����ʍ��̂����ɂ����������E�߂��܂��D
�ȉ��C�����ƈ�����p�x����C�����m�푈�O��̗��j�߂Ă݂܂��傤�D
2-1-1. �w�Ȃ����E���̌���������8��6���������̂��x
���̖₢�ɂ́C����ׂ�������܂����D1945�N2���N���~�A�����ŊJ���ꂽ�č����[�Y�x���g�哝�́E�p���`���[�`���E�\�A�X�^�[�������L�����w�����^��k�x�ŁC�w�h�C�c�~����3�J����Ƀ\�A�͓��\�s�N����j���đΓ�����ɎQ������D���̌��Ԃ�ɁC�����암�Ɛ瓇���\�A�ɗ^����c�c�x�Ƃ��������킳��Ă����̂ł����D
����A�C���V���^�C���Ȃǃh�C�c�ǂ�ꂽ���_���n�̕����w�҂́C�i�`�X������w���q���e�x�����Ȃ��Ɛ��E�̓i�`�X�ɐ�̂����Ƃ��������ϔO����C�哝�̂ɒ��i���C�}���n�b�^���v��̖��̂��ƂŖ����Ɍ������J�����Ă��܂����D
1945�N7��16�����������w�g���j�e�B�[�����x�����̕��g���[�}���哝�̂ɓ͂��܂��D
�h�C�c��5��7���������~�����Ă��܂�������C�����^�̖���Ń\�A��8��7���ȍ~�C���\�s�N����j�����đΓ�����ɎQ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��D�����ɕ��������������̂���ȂǁC�h�C�c�̐�㏈���ł̓\�A�ɍD������ɂ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁC�č��̎��͂ŏ��������Ƃ����`�ɂ���K�v������C�M���M����8��6���Ɍ��������ɓ��ݐ����Ƃ���Ă��܂��D
���������̎��������Ȃ�������C8��15���̓��{�̖������~�����x��C�\�A�R���k�C���ɏ㗤���C�k�C�������̒��N�����̂悤�ɕ������ꂽ���ꂪ����܂����D
�ڂ����͈ȉ���YouTube���Q�Ƃ��ĉ������D
1996�N�w�č���R�����فx�����w����@�����܂���
�����ł́C���q���e�Ɋւ���W�����s���Ă��āC����E��풆�ɊJ�����ꂽ�����̖͌^��C�}���n�b�^���v��Ɋւ��鎑���C�����̎ʐ^��f�������Ȃǂ��W������Ă���C�����J���̌o�܂₻�̗��j�I�w�i�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂��D�܂��C���ۂɌ����𓊉�����B-29�����@�u�G�m���E�Q�C�v�̎��@�W��������܂����D
�w���������ɂ���Đ푈�𑁂��I��点�邱�Ƃ��ł��C�ĕ��̖����~�����c�c�x�Ƃ���������������Ă��܂����D
 �L���֓������ꂽ�E���j�E���^�̌����w���g���{�[�C�x�̃��v���J
�L���֓������ꂽ�E���j�E���^�̌����w���g���{�[�C�x�̃��v���J
|
 ����ɓ������ꂽ�v���g�j�E���^�����w�t�@�b�g�}���x�̃��v���J
����ɓ������ꂽ�v���g�j�E���^�����w�t�@�b�g�}���x�̃��v���J
|
2-1-2. ���V�A�Ɠ��{�̍������
 ���{�ƃ��V�A�̍��� �\�K�� ���
���{�ƃ��V�A�̍��� �\�K�� ���
���X�ŗL���ȃI�z�[�c�N�C�́C�V�x���A���痬�ꍞ�މh�{�L�x�ȒW���ɂ��\�w���̒W�������ƁC�[�w���̔Z��������2�w�ɕ�����Ă��āC���Ǝ������L�x�Ƃ���Ă���C�܂��C�������ӂł́C�Ζ��E�V�R�K�X�������L�x�ł���Ƃ���Ă��܂��D
�k�C�������ē��k�������V�A�̂Ƃ���C�I�z�[�c�N�C�̓��V�A�̓��C�Ƃł��C�j�𓋍ڂ������q�͐����͂�z�u����C��ɍU������Ȃ������̕ۊnjɂɂȂ�킯�ŁC�R���I�D�ʂ��m�ۏo���܂��D
��ɏq�ׂ������^�̖���ŃX�^�[�������_�����{�S�́C�k�C�������ɂ������Ǝv���܂��D
����8��15�����a�V�c�̃|�c�_���錾����̋ʉ������������āC�����m�푈���w��������߁I�x�̏�ԂɂȂ������C�\�A�R�����͖��B�y�уI�z�[�c�N�C���ʂŁC�~���̒���(9��2��)�܂ł͐푈���ł���Ƃ��Đi�R�𑱂��܂����D
-
�w�������~����C�\�A�̖k�C���N�U�Ƃ����j�~�������{���̘b�x
����قǂ܂œw�͂��Ď�ɓ��ꂽ�瓇�I���̌R���I���l������C�\�A�ɂ��w�k���l���̕Ԋҁx�Ȃǂ͂�����͑S���Ȃ������Ǝv���܂��D
���V�A���w�E���V�A���w�E�o���G�E���y�͂��炵���̂ł����C���l�����������x�z���Ă��镡�����ƂŁC���낵�����ʂ������Ă��鎖��Y��Ă͂Ȃ�܂���D
-
�w�V�x���A�}���x
-
�V�x���A����̉䂪�q�̋A���҂�̉́w�ݕǂ̕�x
2-1-3. �푈�́w�A���n����x�̑��ʂ͗ɂ���ď�������ꂽ
���I�푈�́C�����̔��l�Ɏx�z����Ă����L�F�l��̐A���n�ɂƂ��āC���������ł��Ɨ����ł��������Ƃ�����]��^���܂����D
��ꎟ���E����C���{�͂Ȃ�ƍ��ۘA���̏�C�������ɂȂ�܂����D
���F�l��ł�����{�͏�C�������Ƃ����w�l�퍷�ʔ��̑匴���x�����ۘA���Ɏ����������Ƃ��܂������C�����ł��܂���ł����D
�A�W�A�ł́C���{�ƃ^�C�������Ă��ׂĂ̍������Ă̐A���n�ƂȂ��Ă��܂����D��̓I�ɂ́C�C���h(�p)�C�p�L�X�^��(�p)�C�~�����}�[(�p)�C�}���[�V�A(�p)�C�x�g�i��(��)�C���I�X(��)�C�J���{�W�A(��)�C�u���l�C(�p)�C�}���[�V�A(�p)�C�C���h�l�V�A(��)�C�t�B���s��(��)�C���X
100�N�O�C��p�Ɗ؍��Ƃ͓��{�̐A���n�������Ƃ����l�����܂����C����͊ԈႢ�ŁC�F�����w���{�b���x�������̂ł����D�ːЏ�͓��{���œo�^����C�����`��������C�����������x�ł����D���Ă̐A���n����Ƃ͑S���قȂ��Ă��܂����D�Љ�C���t���C��b���炪�[�����Ă����̂ŁC�I���C���{�͋}�������܂������C��p�Ɗ؍��͓����悤�ɋ}�����𐋂��C�����I�ɂ͓��{�𗽉킷�镔����o�Ă��܂����D
���ɋ}���������̂��C�Ɨ���ʂ����w�^�C�����x�ł��D��ɏq�ׂ����Ă̐A���n�������e���̌o�ϔ��W�̐i�x������C��p�E�؍��Ƃ̍���������Ǝv���܂��D���ꂪ�C��p�E�؍���������w�A���n�x�łȂ��������Ƃ̏؋��ł��D
���{���猩�������m�푈�̂�����̖ړI�́C���Đ�i���̐A���n����̖������������ɁC���h��F�̐��_�̉��ŃA�W�A���Ƃ���邱�Ƃł����D�푈�O���͔j�|�̐����Ői�݂܂������C�㔼�ɂȂ�ƁC�⋋�Ԃ��f����C���Ƃ���H���B�i���D�j����悤�ɂȂ�C���S������Ă��܂��܂����D
���q�����ЊQ�����ɏo������Ƃ��́C�މ@�̐H���͎��Ȓ��B���Ă��܂��D�������q�������H�����ꂽ�ƌ����Ė��Ԑl�̐H�Ƃ�����肷��ǂ��Ȃ�ł��傤���c�c�D����ȏ�Ԃ����{�R�̐�X�ŋN�����悤�Ȃ̂ł��D����ɂ܂������Ƃ́C���{�R�͕����Ĉ����グ�Ă����܂��ƁC�߂��Ă����@�卑�́C�l�������{�ɂ��Ȃ��悤�O��I���w���{�͋��\�ȐN���҂ŁC�@�卑�����̐N������A���n�Z����������x�̂��Ƃ����v�z������s�Ȃ��܂����D
�w���ɂ����鋴�x�ŗL���ȃ^�C�ƃ~�����}�[���q���S���́C�f��ł͓S���̕��������j����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����C�A���n�ł͂Ȃ������^�C���́C�푈��C�����ꍡ���g���Ă��܂��D�~�����}�[���́C�C�M���X���{�̈ӌ��ɂ��j�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��āC���̔p���̘e���w���{�����e���ł��ǂ��Č��n�l�ɓS���~�݂���Ă��鑜�x�������Ă��܂��D
���̂悤�ɓ��{���������g������C�Ɨ��^�����ĊJ���Ȃ��悤�ɏ@�卑���K���ɂȂ��ē��{�R�̐A���n����̏؋����B�ł����̂ł����D
-
�w�Ɨ��^�����w�����Ă����A�W�A�̎w���҂̓��{���ߘ_�x
2-1-4. ���a�V�c�͍~���Ɛ��̕����ɐs�͂���
�����N��Ƃ��āC���̈ӂ����ނ��Ƃɏd���𐬂��Ă����̂ŌR���̖\�����~�߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����D
�j���ɂ��C�������̎��������ēc���`������������ӂ�����C�Ԃ��Ȃ��}�������i1929�N9���j�D�w�V�c�Ɏ����ؕ������x�ƌ����\���������ƌ����܂��D���̎����ɂ�菺�a�V�c�́C�R���̖\�����~�߂�͂̌��E��m��̂ł����D
�������������~���i�|�c�_���錾�j��������邩�ۂ��̏�ʂł́C�R�̔��Θ_�������̂��C�S�ցE���Y�Ƃ����������������o��̏���C��������肵���̂͏��a�V�c�������Ƃ���Ă��܂��D
-
�s��Ƃ��ꂩ��̓��{�̓������������a�V�c�̋ʉ�����
-
�ʉ��������㕶��
-
�w�s���̓��{���~�������a�V�c�c�c�x
�Q�l�܂ł�
2-2. ���������Ȃ������m�푈���N�����̂�
�č��̑����m�헪���O�҂̗���Ō������ƁC�ȉ��̗l�Ȍ������o���܂��D
�����Ԃ�����܂�����C���Z������l�b�g�ŁC���ɂ��wAI�x���g���Ē��グ�C���Z�̓Ǝ��̗��j�ς��m�����邱�Ƃ����E�߂��܂��D
1995�N�����푈�Ɖ��֏��
1960�N�A���[�푈���I�����邽�߂̖k������ꃍ�V�A�͂��̒���������܂������̌��т𖼖ڂɃ��V�A�͐V���版�C�B���l�����C���V�A�͔O��̕s���`�E���W�I�X�g�N���R�`�Ƃ��Đ������܂����D
�l���Ă����ɑ_���̂͊؍��ł��D���̊؍��͐����̑����ƂȂ��Ă���C���V�A�̋����ɂ������Ċ؍�����������Ƃ��l�����܂��D
����œ��{�͊؍���Ɨ����Ƃɂ��ēƎ��ɓ��{�ƍ��������������C���V�A�̍X�Ȃ�쉺�̖h�g��ɂ������ƍl���܂����D
���֏��ł́C�@���N�����̓Ɨ��@�A��p�����@�B�ɓ������̗L�@�C�����������߂܂������C���V�A�̓h�C�c�E�t�����X�Ƒg��ŇB�𒆎~�������i3�����j�D
���̂��Ɨɓ������암�i�����j�̓��V�A���d���C��ƌR�`�����݂����D
1998�N�Đ��푈�C�t�B���s�����A�����J�̐A���n�ɑւ��
�A�����J�̖c����`���~�܂炸�J���u�C�̃L���[�o�E�h�~�j�J���̗̗L���߂����ăX�y�C���Ɛ푈���N�����C�X�y�C���ɏ����������ߑ�q�C���ォ��̃X�y�C���̔h�����A�����J�������p���`�ɂȂ����D�����m�Ō����O�A���E�t�B���s�������܂ł��č��̎x�z���ɂȂ����D
1904�`1905�N���I�푈
���̐푈�́C�p�Ăɏ悹���Ă���Ă��܂����푈�Ƃ����ʂ�����܂��D���V�A�����N������{�ւ̐N�U��_���Ă���ƒ������C�R�͂t���C�����Ƃ����Ƃ��̓o���`�b�N�͑��ɃX�G�Y�^�͂��g�킹�Ȃ��Ƃ������p���������сC�����炯���������̂��p���ł����D
�푈���������C���{�̍��͂̌��E�����ɂߘa���H��ɏ��o�����̂��č��ł����D���ʂƂ��āC�R�͂���e��܂ł荞��ŗ��v���҂��C����͈�C�̌��𗬂������V�A������ɒǂ�������C�p���ƁC�č��̊O����r�͂��������ł����D
���I�푈�͑S���E�ɑ傫�ȉe����^���܂����D
-
���{���g�́C���E�ŋ��Ƃ���ꂽ�o���`�b�N�͑���S�ł��������M���C�C�R�����͎�`�ɒǂ�����C��N�푈�����̌͊������Ŏ���ł͎g���悤�̂Ȃ��������w�����x�C�w��a�x��グ�C�G���Ɉꔭ�̖C�e�����猂�����܂����v���܂����D
- �L�F�l�퍑�Ƃ����l���ƂƐ���ď��������ŁC�A���n����̓Ɨ��^���������ɂȂ�C���{�ɐ������̎u�m���W�܂�悤�ɂȂ�܂����D
�����E�����E�v���m�c�c���X
���{�ɂ��A�W�A�̘A�т�������A�W�A��`�̎v�z���L�܂�C�Ɨ��^���Ƃ������x������l����������܂����D���{�B�E�{���V�E���R���c�c���ł��D
- 2018�N�o���g�C���ݏ����𗷂����Ƃ��C���{�l�ƕ�������w���V�A��������Ă���Ă��肪�Ƃ��x�ƌ����C�ǂ�ʃ��V�A�������Ă��邩��m��܂����D
1910�N ���ؕ���
���������̑����Ƃ݂Ȃ��Ă����؍���Ɨ������C��ˊJ���ƃ��V�A�̖h�g��ɂ��������{�̈ӌ��̕s��v�œ����푈�͋N���C�؍���Ɨ����������C�̊Ԃłӂ�ӂ�Ƃ��ă��`�������Ȃ��̂ŁC���{�ɕ��������D
����
1912�N���ؖ��������i�h��v���E�����ŖS�j
���Ԃ͌R�������̎���ցc�c
1914�N�`1919�N ��1�����E���
�O�������i�h�C�c�鍑�E�I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�E�I�X�}���鍑�j�ƎO�������i���V�A�E�C�M���X�E�t�����X�j�̐푈
���{�͓��p�����̊W�ŁC�O���������ɕt���C�����̃h�C�c�̂ɏo��
�����C�č��͒����̗�����Ƃ�C�o���ɕ���e��������ċ����̗����D�h�C�c�̐����͍U�����āC1917�N�O���������ɉ��S���܂����D
1917�N�̃��V�A�v���ɂ���āC���V�A�͐푈���痣�E���܂����D
2-2-1. ��1�����E����̓��{�̌��v�g��
�����[���b�p����ɋ��X�Ƃ��Ă���ԁC���{�͓��p�����ɏ]���p�����ɉ��S���D1919�N�ɂ͈��G���h�C�c���v�̎R���Ȃ�C�h�C�c�̓�m�������̂��܂����D���̌��ʁC�����m�͓��Ă̔e�������̕���ƂȂ�܂����D
�w�č��̑����m�����͊g��x
���L�̂悤�ɐ��͂��}�g�傳���Ă����܂����D
| 1865�N |
��k�푈�I�� ���̎��_����č��͋���ȍ��ƂƂ��ČN��
�˓��{�̖����ېV�ɑ������� |
| 1867�N |
�A���X�J�ƃA�����[�V���������V�A���甃�� |
| 1867�N |
�~�b�h�E�G�[�������C���l���������̂ŗ̗L |
| 1898�N |
�n���C������č��̏��B�Ƃ��ĕ��� |
| 1898�N |
�Đ��푈�ɏ������C�t�B���s���E�O�A���̓J���u�C�����Ƌ��ɃX�y�C�����犄���C�C�m���ƃX�y�C���̗��������D���� |
| 1899�N |
�T���A�����������O�����Ŋl�� |
�w���{�̑����m���͌��̊g��x
���������{�����͂��g�債�Ă����܂����D
| 1868�N |
�����ېV �ߑ㉻�ւ̑��� <��1965�N��k�푈�I��> |
| 1895�N |
��p���� |
| 1910�N |
�؍����� |
| 1919�N |
��1�����E���̐폟���Ƃ��ē�m�����ϑ����� |
�i�X�y�C���E�|���g�K���E�p�E���E���j�ɒx��ċ}�������C�X�y�C����|���Ĕe�҂Ƃ��ċ}���������č��ɂƂ��āC���{���ǂ̂悤�ɉf�������I�͑z���ł���D
�ˑ�ꎟ���E����͕č��͉p���ɖd��C���{�������ĂāC���V�A�̓쉺����̏��ɂ�����p������j�������C�V�����w���V���g����c�x�œ��{�鐭���ł��o���Ă���
2-2-2. ��1�����E����̃��[���b�p�̕ω�
�yA�z���Y��`�����̒a��
���V�A�鍑��1917�N���V�A�v�����o�āC1922�N�\�r�G�g�Љ��`�A�M�ɕϐg���C���E�ŏ��߂Ă��w���Y��`�������Ɓx���a�������̂ł����D
�\�A�͂��̗B��̋��Y��`�̎��������ׁC�e���ɎЉ��`�̎�������C�v�����N�����l�ނ��琬���C�w�J���ҊK���̉���x�̂��߂Ɋe���֊g�U�������D
�yB�z�鍑�͕��C���a���Ƃ��čďo������
�h�C�c�鍑�˃h�C�c���a���{�|�[�����h�֕Ԋ�
�I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�˃I�[�X�g���A���a���{�`�F�R�\���o�L�A�{�n���K���[�{���[�S�X���r�A
�I�X�}���鍑�˃g���R���a���{�V���A�{���o�m���{�p���X�`�i
����̃��[���b�p�̓��F���T�C���̐��Ƃ���
(���[���b�p�̒鍑�͉�̂���C����{�鍑�݂̂��c�����D)
�yC�z�A���n����^���̊�����
1905�N���{���o���`�b�N�͑�����ł����C���l�̋���鍑���V�A�ɏ����������Ƃ��C�̎x�z�ɋꂵ��ł����e�A���n�̖��������Ƃ������h�������D�����ē��{�Ŋw�������n�ߒ����̎u�m������1911�N���w�h��v���x���N�����C������|���C�w���ؖ����x���������܂��D���̉e���ł܂��܂��w�A���n����̓Ɨ��x�^��������ɂȂ�C�e���̎u�m�����̈ꕔ�����{�ɏW�܂��Ă��܂����D
�yD�z���ۘA���̒a��
AI���wGemini�x�ɖ₤�ƁC�ȉ��̉��܂����D
(1) ���ۘA���a���̌o�܁C���̑g�D�́C���̐��ʂ́c�c
���ۘA���́C��ꎟ���E���̎S�Ђ��x�ƌJ��Ԃ��Ȃ��Ƃ��������肢����a�������C�j�㏉�̖{�i�I�ȍ��ە��a�ێ��@�ւł��D���̐ݗ��ɂ́C�A�����J�̃E�b�h���E�E�E�B���\���哝�̂������u�\�l�����̕��a�����v���傫�ȉe����^���܂����D
�a���̌o��
���ۘA���́C��ꎟ���E���̍u�a���ł��郔�F���T�C�����Ɋ�Â��āC1920�N�ɃX�C�X�̃W���l�[���ɖ{����u���Đݗ�����܂����D�������C���ł���A�����J�́C�c��̌Ǘ���`�I�Ȕ��ɂ��������܂���ł����D�܂��C�s�퍑�ł���h�C�c��v����̃\�A�������͎Q�����F�߂��܂���ł����D
�g�D
���ۘA���͎�Ɉȉ���3�̋@�ւō\������Ă��܂����D
-
����: ���ׂẲ��������Q�����C�ꍑ��[�̌����ʼn^�c����܂����D�d�v�Ȍ���͑S���v�������ł����D
-
������: ��C�������Ɣ��C�������ō\������C���ە����̉����Ȃǂ�S���܂����D��C�������́C�����͓��{�C�C�M���X�C�t�����X�C�C�^���A��4�����ł����D
-
������: �A���̓���Ɩ���S����݂̎����@�ւł��D���������ɂ́C���{�̐V�n�ˈ���A�C���C���ۓI�ȐM���܂����D
�܂��C�֘A�@�ւƂ��ď�ݍ��ێi�@�ٔ�����**���ۘJ���@�ցiILO�j**���ݒu����܂����D
���ʂƌ��E
���ۘA���́C�������̒n�整������������ȂLj��̐��ʂ��グ�܂������C���̗L�����ɂ͌��E������܂����D
-
����:
�n��I�ȕ����̒��فi�X�E�F�[�f���ƃt�B�������h�Ԃ̃I�[�����h�������Ȃǁj
-
���E:
�卑�̕s�Q��: �A�����J���s�Q�����������Ƃ́C�A���̌��Ђ����ቺ�����܂����D
�S���v�̌���: �d�v�Ȍ���ɑS���v�����߂邽�߁C�v���ȑΉ�������ł����D
�R�����ق̌��@: �������������邽�߂̗L���ȌR���͂��Ȃ��C�o�ϐ��ق������͂��ォ�������߁C�卑�̐N���s�ׂ�h�����Ƃ��ł��܂���ł����D
�����̌��E�́C1930�N��̖��B���ςɂ�������{�̍s����C�C�^���A�̃G�`�I�s�A�N�U�ȂǁC�̐N���s�ׂ�j�~�ł��Ȃ��������ƂŘI�悵�܂����D�����āC����E���̖u���ɂ���Ă��̋@�\�͊��S�ɒ�~���C����**���ۘA���iUN�j**�ւƈ����p����C1946�N�ɐ����ɉ��U���܂����D
(2) ���ۘA���ɂ�������{�̗����ʒu�Ɗ���
���{�͏�C�������Ƃ��� �l�퍷�ʓP�ސ錾���Ă���
���ۘA���ŏ�C�������Ƃ��Đl�퍷�ʓP�ސ錾����悤�ɓ�����
���{�̐l�퍷�ʓP�p��ẮC���ۘA���̐ݗ����c�_���Ă���1919�N�̃p���u�a��c�ŁC�S����\�̖q��L�������S�ƂȂ�s���܂����D����́C���ۘA���K��Ɂu�l�킠�邢�͍��Д@���ɂ��@���゠�邢�͎����㉽�獷�ʂ�݂��Ȃ��v�Ƃ��������荞�����Ƃ�����̂ł����D
��Ă̔w�i
��ꎟ���E���ŏ����������{�́C�p���u�a��c�Ŏ�v�폟���̈���Ƃ��ĎQ�����܂����D�����C���{�͉��ėƌ�����ׂ鑶�݂Ƃ��č��ۓI�Ȓn�ʂ��m��������܂������C����ŃA�����J��J�i�_�Ȃǂł͓��{�l�ږ��ɑ���r�˖�肪�[�������Ă��܂����D���̒�ẮC�����������ʂ��Ȃ����C���ێЉ�ł̓��{�̒n�ʂ��m�ł�����̂ɂ��悤�Ƃ�����̂ł����D
��Ă̌o�߂ƌ���
-
�e���̔���: ��Ă͑����̍�����x���܂������C���ɃA�����J�ƃC�M���X�����������܂����D�A�����J�͍����ɐ[���Ȑl���������Ă���C�C�M���X�͐A���n�ł̎x�z�ɉe�����o�邱�Ƃ����O�������߂ł��D
-
�ŏI�I�Ȍ���: ��Ă͎^�������ō̑�����܂������C�c���߂��A�����J�̃E�B���\���哝�̂��u�S���v�łȂ����ߕs�����v�ƈ���I�ɐ錾���C�ŏI�I�ɍ��ۘA���K��ւ̋L�ڂ͌������܂����D
���̒�Ă͎������܂���ł������C���ێЉ�ɂ����Đl�핽���m�Ɏ咣�����ŏ��̎��݂Ƃ��āC���j�I�ɏd�v�ȈӋ`�������܂����D
2-2-3. 1929�N���E�勰�Q���n�܂�
��1�����E���́C���ɂȂ�Ȃ������č����C���ɂȂ��Ă��܂�����e������Ȃ��Ȃ������B�Ɍ����ėA�o���邱�ƂŔ���ȗ��v�܂����D���̗L��]�鎑�����C����̐�[�ł��鎩���ԁC�q��@�c�c���ɓ�������C���ꂪ�V���ȕx����сC�č��͖��\�L�̂����������������C���E�o�ς̒��S�����B����A�����J�ֈڂ������ł�����܂����D
�č��Ɠ��l�����ɂȂ�Ȃ��������{���푈�����ł킫�C�D�i�C�Ɍb�܂�܂����D
�吳�f���N���V�[��_���K�[���͂��̍��̎��ł����D
1929�N10���C�j���[���[�N�،�������̊�����\���́C�u���ԂɑS���E�ɍL�����w���E�勰�Q�x�ƂȂ�܂����D
���Y�ݔ����g�傳��C�w���́x�͗L��]���Ă���̂ɔ����Ă����l�����Ȃ��I
�����Ă���Ȃ�����C����������Ȃ��I
����������Ȃ�������͕����Ȃ��I
���������炦�Ȃ�����̂������Ȃ��I
���̕��̘A�����n�܂��Ă��܂����̂ł����D
�Z���I�ɍl���܂��Ƃ��̑�s����ł��オ��ɂ́C�R���g�����R���Y�Ƃ������I
�����ɐN�����V�����s����J��c�c�Ƃ����̂��N�����l���鎖�ł��D
�h�C�c�̓i�`�X���䓪���C34�N�q�b�g���[�������ɁC�ČR�����i
�C�^���A�̓t�@�V�X�^�}�����C�G�`�I�s�A��
���{�͌R���̑䓪�C���B������
���̌����́C�`�������ł��Љ��YouTube�̓���̂Ƃ���ł��D
�勰�Q�ƑΛ��������[�Y�x���g�哝��
�A�����J�ɂ����Ă�1933�N�ɓ��I�������[�Y�x���g�哝�̂��W�J�����j���[�f�B�[������ɂ���āC�勰�Q�̉������}��ꂽ�ǂ�����Ă��܂����C���̐^�U�̒����wGemini�x�Ɋm���߂܂��ƁC�ȉ��̉܂����D
�j���[�f�B�[������̕]��
�j���[�f�B�[������́C�A�����J�o�ς����S�ɉ������킯�ł͂Ȃ��C����E���ɂ������ɂ���čŏI�I�ɋ��Q����E�o�����Ƃ�����������ʓI�ł��D�������C���{�̖������g�傳���C���{��`�̂������傫���ϊv�����Ƃ����_�ŁC���j�I�ɔ��ɏd�v�ȈӖ��������Ă��܂��c�c�D
���̉ɗ͂āC���܂łɂ��̕������l�������w�����m�푈�̉B�ꂽ�ʁx�����Љ�����Ǝv���܂��D�ǎҏ��Z�ɂ�����܂��ẮC�����g�ōēx���m���߂��������D
���[�Y�x���g�哝�̂�1941�N�̑����m�ɂ�����s���l������ŊJ���邽�߂ɂ́C�č��{�����牓�����ꂽ�������m�ŁC���{��@�������Ȃ��ƌ��ӂ����D
-
���{�̈͂�ABCD��͖Ԃ����C�Ζ��E�A���~�E�S�����̎������͊������邻������C���z�����Ă��邾�낤�D
-
���{���U�߂Ă���Ƃ���ΐ^��p�ł��낤�D�Â��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��R�͂�^��p�ɏW�߂Ă����C�p�̐��[���̂ŁC�K�v�Ȋ͑D����������ďC������悢�D�M�d�ȋ��ƍq��@�͗m��őҋ@�����Ă����Ηǂ��D
-
��P�����ƂȂ�Εč����_�͈�ۂƂȂ��đœ|���{�ɂȂ�C���z�̗\�Z���t���C�R�������ƁC�s������̒E�o���ł���c�c�D
-
���{�R�͂܂�܂Ƃ���㩂ɂ͂܂�܂����D�������ȉ��̂悤�Ȃ��܂��t���Łc�c
-
���O�ɐ��z�����Ă���̊�P�U���̗\�肪�C�Í���ǂɎ��Ԃ��|����C��g�ق���č����{�ւ̒ʒB���C�U���̌�ɂȂ��Ă��܂����D
���̌����w���{�͔ڋ��ҁx�Ƃ������b�e����č����{�ɕt������C�č����͈�ۂƂȂ��ē{��ɐk���錋�ʂɂȂ����D
-
��2�C��3�g�̍U���ŁC�R���^���N�C����ɂȂǑS�Ă��j���o��ł������`���ɋ�ꂪ���Ȃ����ƂŁC���{���͑��͕č��̋�P�������1�g�U�������ň����Ԃ����D
-
�U��������̐^��p�ł́C��ԌÂ��w��̓A���]�i�x����{�R�̐^��p��P�ɂ�����L�O��Ƃ��ĕۑ������D
YouTube�̓A���]�i�L�O�فiUSS Arizona Memorial�j:
�^��p�U���Œ��v������̓A���]�i�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�C�ł��L���ȋL�O�قł��D�]���ƂȂ��������̏�g���������D�̂̒��ɖ����Ă���C�ԗ�̏ꏊ�ƂȂ��Ă��܂��D�{�[�g�ł����s�����Ƃ��ł����C���O�\�K�v�ł��D���v������͂̍b�������낷���Ƃ��ł��܂��D
-
���v�����ŐV�s�̐�̓~�Y�[���́C�����Ɉ����g���C�C�����đO�����A�����C�����m����ő劈�C1945�N9��2���̓��{�̘A���R�ɑ��閳�����~���̒���́C���̐�̓~�Y�[���͏�ŏd���O����b�ɂ�点���̂ł����D
�~�Y�[���L�O��
-
�����ٔ�
�ٔ��̒����͉��LYouTube���Q��
�ٔ��̊J�n��4��29���@�c�c�c�c�c�c�c�c�i���a�V�c�̒a�����j
A����Ƃ̏��Y����12��23���c�c�c�c�i��c�É��̒a�����j
���R�̈�v�H�H�H
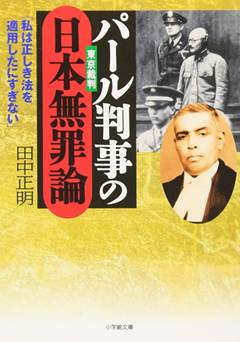 �p�[�������̓��{���ߘ_
�p�[�������̓��{���ߘ_
�p�[�������̓C���h����y���Q�����w�����ٔ�15�l�̔����x�̈�l�D
�����ЂƂ薳�߂��咣�����l�ł���D
��� �c�������́C�M�҂̏f���ł��D
�M�҂�8���ւ̎v���Ƃ����^�C�g���ŏ����n�߂܂��������X�Ƃ��ݏグ�Ă�����̂�����܂��Ďv�킸�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����D
�ǎҏ��Z�������m�푈�ɂ��ď����ł������̂��Ƃ��m�F���Ă��������C���N��8���͂����Ɛ[���v���������ďI��L�O�����}���Ă������������Ǝv���܂��D
2025�N9��13��
(��)J�R�X�g������ ��\ �c�����m