�A�ڃR�����w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ڎ�
JBpress�A�ڃR�����w�{���g���^�����x
�r�W�l�X���T�C�gJBpress�ɂ����āA2008�N����2013�N�܂ł̊Ԃɍ��v104��̃R���� �w�{���g���^�����x ��A�ڂ��Ă��܂����B
���ݘA�ڒ��̃R���� �w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ƕ����ēǂ�Œ����ƁA���[��J�R�X�g�̍l�������������邩�Ǝv���܂��B����A���L�̃����N�ɃA�N�Z�X���Ă݂ĉ������B
�ߋ��̏��M�\��
2026�N1��
2026�N�����̔N�������A
�č��R�ɂ��x�l�Y�G���̌��E�}�h�D���̑哝�̂�U���c�H�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ�������������n�܂���2016�N��10���]�o���܂����B�x����Ȃ���V�N�̂����A��\���グ�܂��B
�F�l�A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�����̌����w�悸观��n�߂�x�Ƃ����̂�����܂��B�F���܂ɋƖ����v�����E�߂��闧��̕��Ђ��A���Ђ̂g�o�̃X�^�C����ϊv�������āA���̊炠���Đl�l�ɉ��v�����E�߂��邱�Ƃ��ł��悤���c�A�Ǝv�������܂����B
[1] �{�N�x����n�߂镾��HP�̐V�������g��
�`YouTube���̊��p�`
���́A��20�N�O�ɂȂ�܂����A���Y�����Ԃ̐��Y����̌��C����w�g���^���Y�����x�ƁwJ�R�X�g�_�x�ɂ��āA�w���Y���Y�����x�ƑΔ䂵��
�w���̂Â���H����S�̑��Ƃ��đ�����`�i�R�X�g�_�`�x
�Ƃ����^�C�g���ōu���v���܂����B���̎��ɓ��Y���Ř^��r�f�I��ҏW���A���Y�O���[�v���ŋ��ނƂ��Ďg���ėǂ����Ƃ̑Őf������A���Ђ����R�Ɏg���Ƃ����ł��̓��悪���삳��܂����B
����A���e���Ċm�F���܂������A�u�����e�͉��玞��x��̖ʂ͖����A���݊��Ă���F���܂ɂ��`�����������Ƃ��l�܂��Ă��܂����̂ŁA�����YouTube�Ɍf�ڂ��A�F���܂Ɍ��Ē������Ƃɂ��܂����B
����60���̂��b�����AYouTube���w��b15���x�̘g�ɓ���邽�߂ɁA�u�@�B�I�Ɏl�������Ă��܂��v�̂ŁA�b���r���Ńv�c�b�Ɛ�Ă��܂��܂����A�ǂ��������ق��������B���̉�͐ꂽ�Ƃ��납��n�܂�܂��̂ŁA����A�O�̉�̓r�����畷���Ȃǂ̍H�v�����肢���܂��B
�����^�C�g����
�w2006�N�@���Y�����ԁE���Y���匤�C��ł̍u���u���̂���H����S�̑��Ƃ��đ�����`�w�i�R�X�g�_�x�`�v�x�ƂȂ��Ă���܂��B
-
(����1) 2026/01/04 �����[�X��
-
(����2) 2026/01/11 �����[�X��
-
(����3) 2026/01/18 �����[�X��
-
(����4) 2026/01/25 �����[�X��
���Q�l�܂łɁA�g���^����h�����ꂽ���̂����w���������̓��Y�ōu������Ɏ������o�܂ɂ��Ĉȉ��������v���܂��B
���̂Â���̋ƊE�ł́A1990�N�ɓ���ƁA�h���b�J�[���m��21���I�ɂ͉Ȋw�Z�p���i������̂ŁA����ŐE�H���w���o����悤�Șr���������Z�p�ҁiTechnologist�j���K�v�ƂȂ�Ɛ����܂����B������{�ł�1950�N����1960�N��ɑn�Ƃ������{�̒������Ƃ̏���̑n�Ǝ҂́A�����������萷�肵�Ă��܂������A2��ڂ͎ЋƔ��W�̊ϓ_���璠��d���ŁA����͐E�H�C���̕����������Ȃ�A�Z�p�Ɍ�ꂪ�ڗ��悤�ɂȂ�܂����B��������́A����̂悤�ɁA����̐E�H�����[�h���A����ɂ��ڂ����l�ނ̈琬�����߂���悤�ɂȂ�܂����B
���Ƃł��A��w�ŋ����͈͂̒��Ő��E��Top�Z�p���w�����̋Z�p���ł́A����͊Ǘ��o���Ȃ��̂ŁA���E�̍Ő�[�łȂ��Ă��ǂ�����A����ŐE�H���w���o����悤�ȕ��E���m���Ƙr���������l�ނ��K�v�ɂȂ��Ă��܂����B
����Ɍĉ����āA�o�c�A�E���ȏȁi��w�j�E���J�ȁi������ƁE�E�ƌP���j����̂ƂȂ�A�������t���w���̂Â����{�@�x�����肳��A�w���̂����w�x���ݒu���ꂽ�̂ł����B
���̂����w�͍�ʌ��s�c�s�ɂ���܂�������A�Ŋ��̗L���Ȏ����ԉ�ЂƂ��ē��Y���w���Y���Y�����iNPW�j�x�̐��i�{���������������������w�u�`�x�����肢�����̂ł����B�������Y�̐��Y����̃g�b�v�͏��{���В��ł����̂ŁA�����������w�}�c�Q������x�Ƃ������̂ŌĂ�A��ڒu�����l�ނł����B������A���g���^���Y�����̐��i�����ƁA���E�̓��Y���Y�����̐��i������������킹���̂ł����B���݂��ɔn�������A�M�҂����Y�̐��Y����̌��C��ōu�����邱�ƂɂȂ����̂ł����B���݂ɁA��������͌���A���Y�̕��В��ɂ܂ŏo�����܂����B
�����̓��Y�́A1999�N�Ɏn�܂����������w�S�[�����v�x�Ō����ȕ����𐋂��Ă��܂������A�����ׂ����v�̃l�^�������Ȃ������ŁA�g���^�̘b�����āA������h���ɂ��čX�Ȃ���v��i�߂悤�Ƃ��Ă����̂��Ǝv���܂��B
���̍u���̌�A�t�����X�����ŁA���m�[�ԂƓ��Y�Ԃ̔z�����w�i�R�X�g�_�x��K�������ʂ��������ƌ��������܂����B
�ǎ҂̊F���܁A�w���̎��g�����o�o�x�͕��Ђɂ���܂��̂ŁA���ЂɃ��[���Ő������������܂��ƁA�o�c�e�ł����肢�����܂��B
[2] 2026�N�̌o�ϗ\�z�ƊF���܂ւ̒�
���N���A���̒n����ɏZ�ސl�ނ́B�y�`�z�E�N���C�i�푈�A�y�a�z�C�X���G������A�y�b�z�ُ�C�ہA�y�c�z�l�������A�y�d�z�@���Η��Ƃ����傫�Ȗ�������A���ނւ̓���H���Ă���c�B�ƌx����炵�Ă܂���܂����B
���ꂩ��2�N�o�������N�A2026�N�͂ǂ̂悤�ȔN�ɂȂ�̂ł��傤���H
�y�`�z�E�N���C�i�푈
�E�N���C�i�푈�́A�E�N���C�i�̂��ԂƂ������ŁA���V�A�̘V�������Ă����C���t���{�݁A���ɉ҂����ł������V�R�K�X�A�Ζ��֘A�{�݂��������A����ł��������V�A�A�M�̉��䍜������A�����I�ȓ�������22�̋��a������Ȃ�Ƃ��̂���Ă��܂����A�A�W�A�n�����A�C�X���������ɂƂ��Ă͓Ɨ��̋@���_���Ă���Ƃ���Ă��܂��B�����B�̉��C�n���́A���������Ƀ��V�A�ɂ��܂����ꂽ�悤�ȗ̓y�A�����́A�Ɨ������Ďx�z���ɒu����]������Ƃ�������������A�ŏI�I�ɂ̓��V�A�A�M���s��A���K�͂ȃ��V�A�A�M�Ɉޏk����̂ł͂Ƃ݂��Ă��܂��B
�y�a�z�C�X���G������
�푈����߂�Ɠ��������l�^�j�A�t�́A�푈�𑱂����ʂƂ��āA���E���̕��a���b���肤�l�X����C�X���G���݂̂Ȃ炸�A���E���ɏZ��ł��郆�_���l�ɑ��āA�p�����e�B�i�̖��O�ɂނ����d�ł������閯���Ƃ��Ĕ��̖ڂ��������n�߂Ă��܂��B���̌��ʂƂ��āB���E�e�n�ŕ��a�ɕ�炷���_���l�����ł���l�^�j�A�t�͌����A���r����ł��傤���A�C�X���G�������͂ǂ��Č�����̂��H�s�����Ԃ͑������Ƃł��傤�B
�y�b�z�ُ�C��
�ُ�C�ہA�]���͔M�g�A����n���P�[���ł������A���E�e�n�ŏZ����P������R�Ύ�������悤�ɂȂ�܂����B�X�ɑ�C�̗��ꂪ�ς�������ƂŁA���̓~�劦�g�̔�Q���`�����Ă��܂��B�����ُ�C�ۂ��ׂ�CO2�̂������Ƃ���Ă��āA���̑�Ƃ���EV����i�߂܂������A����Ȃ��ƂɌ��݂̃��`�E���d�r�ɂ��EV���͍ЊQ�ɑ��Ĕ��ɐƂ��Ƃ������Ƃ����E���Ŋm�F����܂����B
���ʂƂ��Ĉ��Ղɂd�u����}���������ԃ��[�J�[�͌������o�c���ɎN����A��������Ă������̂Ǝv���܂��B
�y�c�z�Ɓy�d�z�̓R�����g���ȗ��������܂����A2026�N�ɂ͐V���Ȃ��肪���݉����Ă��܂����B
�y�T�z���؍��̍����j�]
1997�N�̔j�]���ɂ́AIMF�̌������w���ʼn��܂������A�����IMF�̊������������Ă̔j�]�Ȃ̂ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ĉ�����̂��S�z�ł��B
���{�͊؍��ɑ��ẮA2024�N�x�ł͖�80���~�̗A�o���������̂ł����A���ꂪ�啝�Ɍ������邱�Ƃł��傤�B
�y�U�z�����̃o�u������
�������{���i�N�ɘj���ăC���t�������ɑ���̓������s���Ă��܂������A��������̎������L�т��A����ȕ���ςݏグ�Ă���Ƃ̎��ł��B
���{�̑Β��f�Պz�́A2024�N�x�A�o156���h���A�A��167���h����2021�N�x�̃s�[�N���猸�����Ă��܂��B���̑O�ɐS�z�Ȃ̂́A�|�Y������ƁA�ꍇ�ɂ���Ă͈�̋ƊE���Ɉ�|�Z�[�����s���A���̑�Ôg�����{�s��ɉ����邱�Ƃ����O����܂��B
���������ł́A2019�N�̃R���i�����h�~�ŋ�����p���ēs�s���������߁A�����̒�����Ƃ��ׂ�A���ʂƂ��Ď��Ǝ҂����ӂ�A�����ĕs���Y�o�u�������Љ�卬���Ɋׂ��Ă���ƌ����Ă��܂��B�����ɐi�o�������{��Ƃ́A�`���C�i�v���X�����Ə̂��āA���Y�ݔ��̈ꕔ���x�g�i����C���h�l�V�A�Ɉڂ��Ă��܂��B�������N���ɁA�����o�ςɑ�ٕς��N���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A���������ɔ���c���ė��܂��������Ȑ��i���A�S�C���̔@���D���E���P���A���ꂪ�������ɂȂ����w���E�勰�Q�x���N����ƒf������w�҂����܂��B
���{��`���ł́A�e��Ƃ��s��ł̔̔������Ȃ��琶�Y���܂����A�����̂悤�ȋ��Y��`���̍��c��Ƃ́A���Ƃ̖ڕW�Ƃ��Đ��Y�ʂ����߂��A�ǂꂾ���B�������ŁA�Ǘ��҂̐��т��]�������ƕ����܂��B
�V�����Ԃ͒��菄�炵�Ă��܂����A�q�̐����܂�ȋ�Ԃ������Ƃ��c�B�Z��݂͖w�Ǔ����ړI�ōw������l�������A�����������w�}���V�������A�Z��ł���l�͏��Ȃ������Ă��܂����B�R���i�O�́A�N�ԂU�`�W�T�قǒ�����K��Ă��܂������A���ۂɖ铔�肪�Ƃ����Ă��鑋�͏��Ȃ����ƁA���Ă����ōH�������f���Ă���c�n�𐔑����m�F���Ă��܂��B
����Ƃ��āA���������Ƃ������đ��Y�����w�����K�i�x���w���z���p�l���x�A�w���͔��d�x�A�w���`�E���d�r�x�A�w�d�C�����ԁx���́A���������ɍɂ͎R�Ɛς܂�Ă��܂��B
��������@�ɕm����O�ɁA�����I�Ȗf�Տ�ǂ�����Ă����Ȃ��ƁA��ςȂ��ƂɂȂ鋰�ꂪ����܂��B
�y�V�z���A��C������̌��Ў���
���E���a�͍��A�ɂ���Ĉێ�����A���̍��A�́y�āz�y�p�z�y���z�y�I�z�y���z�̏�C�������ɂ���ē������\���ɂȂ��Ă��鎖�ŕ��a���ێ��ł���c�\���ł������A
�p�����wBrexit�x������o�����B�����͎Љ�ۏ������č��h�ƋɉE���Η����A�����I�s����ɂȂ��Ă��܂��B�I���ƒ����́A�O�q�̂悤�Ɋ�@�ɕm���Ă���܂��B
����Ȓ��ŁA�č��̓x�l�Y�G�����}�P���đ哝�̂�U�����܂����B
���ꂼ������ɏ��̂����C�������ł́A�E�ъ�鐢�E�w�勰�Q��������邱�Ƃ��A���������҂��邱�Ƃ͏o�������ɂ���܂���B
����Ȓ��Ŏv���N�������̂��A1950�N��ׂꂩ�������g���^�����Ԃ𗧂Ē������Γc�ގO�В��̌����ł��B
�w�����ɏ�͎����Ŏ��I�x�ƞ������A�Г��̉��v��i�߁A���̊�b�̏�ɁA���݂̃g���^������܂��B
�w�����ɏ�͎����Ŏ��I�x�̐^�ӂ́A�����ʂ�A�_���݂�A�s���ɒ��Ή��Ƃ��Ȃ�Ƃ����w�Â����l���ʼn�Ђ��o�c����ȁI�x�Ƃ������Ƃł��B�����̋�̗���������ƁA�w7�����Ƃł����v���o����悤�ɂ���I�x�Ƃ������̂ł����B
���̕ӂ̋�̓I�Șb�́A����A����������������\��ł��܂��c�B
�����ԋƊE�Ɛ����̌o�c�������̂��d�@�ƊE�ł����B����Ō����A�D�G�Ȑl�ނ��ʂɍ̗p���A�[������ŐV�̋Z�p���������̂ɁA�s��Ő��i������Ȃ��Ȃ���w��]�ސE�ҁx������ق��Ă����c�̌J��Ԃ��ł����B
���̓d�@���[�J�[�́A�v���싅�̑I���W�Ɠ����悤�ɁA�w��ł̔��\��A�Ј�����̕�����蒲���ŁA�D�G�Ј��̃��X�g�A�b�v�����A������2�`5�{�̔N��ň���������}��܂����B�w��]�ސE�ҁx�Ƃ����̂́A���̐l�B�ɑ�`������^�������ɂȂ�܂��B
���ɑ�胁�[�J�[�̋Z�p�҂��T���X���̐ꖱ�ɓ]�E���A�����~�̔N��Ŕ����̎��Ƃ𗧂��グ���l��m���Ă��܂��B
2026�N�̍����A���{�̎����ԋƊE�́A���E��Top�𑖂��Ă��܂����A�d�@�ƊE�͊��S�ɗ������A���͍���Ƃ��Đ��{�̂Ă�����ŁA�Ă�Top�ɂȂ��悤�Ɋ撣���Ă���Œ��ł��B
�Ƃ���������ꂪ���ł����A��Ƃ̋����͂��w���i�x�ł͂���܂���B
�̐S�Ȃ̂��w�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��u���Ȃ��i���ƈ��|�I�ȒZ�[���x�ł��B
������ێ����邽�߂��w�l�ނ̈琬�x�ɂ���܂��B
2026�N���w�G�߂̂����A�x�̃R�����ł́A���̃e�[�}�ɉ����Ă��b�����čs���܂��B�ǂ��������҂��������B
���A�wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�͉i�炭���x�݂��Ă��܂������A�������Ƀ����[�X�������܂��B�����҉������B
2026�N1���g��
(��)J�R�X�g������ ��\ �c�����m
2025�N9��
���� �G�߂̂����A
�n�����g��������ċv�����̂ł����C���N�̏����ُ͈�Ɏv���܂����D�wAI�x�ɐq�˂Ă݂�ƁC���N��8�����É��̓����ō��C���́C�̉��ł���36�x��������20���]����C�K�オ��ɔM���Ȃ�C�����ɂ�40�x���܂����D
9���ɂȂ��Ă����ς�炸�̍����������Ă���܂����C�F�l���������߂����ł��傤���c�c�D
�܂��Ȃ�84���}����M�҂ɂ́C���̏��������܂����D�ł��邾���O�o�͔����C�G�A�R���̌����������ɕ��������ĉ߂����܂����D
���ɂƂ���8���Ƃ����̂́C�w���N���̓�M�B�̉ċx�݁x���w�����m�푈�̏I��������x�Ƃ�����̈Ӗ��ŁC���ʂȌ��ł��D
����͋G�߂̂����A�Ƃ��āC�w8���ɑ��鎄�̎v���x��\���q�ׂ����Ǝv���܂��D
������ɂȂ�܂��̂ŁC�ȉ��̂悤�ȏ͗��Ăł��b�����܂��D
- [1] 70�]�N�O��8���̎v���o
- [2] 8���Ƃ����Α����m�푈���I��������ł�
[1] 70�]�N�O��8���̎v���o
���̏��N������߂�������M�B�C�ɓߒJ�̓����̋��ؑ��ł́C�W����500m�Ƃ�����������C�������͂������̂́C��C�͊������Ă���C�؉A�ł͗������߂����܂����D���̋C�C�����E���E�ь�Ƃ���3��ނ̉ʕ����l���Ƃ�����Ղ������炵���̂ł����D
7���̉��{�̊l�肽�Ă̔����́C�o���o���Ƃ����鎖���o���C��̓|�����Ǝ��܂��D���̏�Ԃ̓����M�҂͑�D���ł����D���̓���8���ɂȂ�Ɠs��̓X���̔����̂悤�ɉʓ����_�炩�ɂȂ�C�ʏ`���������点�Ȃ���H�ׂ��ԂɂȂ��Ă��܂��܂��D�F�l�������x�̓o���o���Ƃ����铍�̂��������𖡂���Ē��������v���܂��D

�c�A���ƈ��̋G�߂��w�_�ɋx�Ɂx�̂���c�ɂ̉ċx�݂́C8��1������~������16���܂łł����D�ċx�݂͐�km��ɂ���k�J�̑��ʼnj���̂��y���݂ł����D���̐�ɂ͓`��������C�w���[�ȍ~�ɉj���Ɨ������x�ƌ����Ă��܂����D���R������������8��10�����炢�ɉj���ɍs���܂������C�����̒��Ԃ͂��炸�C��̐����₽�������܂����D���̗₽�������̂��N�����₷���Ƃ����x�����ƒm��܂����D
�P���8��15���ɂ͍Z��Ŗ~�x�肪�s���C���߂��C�镗���S�n�悩�����L��������܂��D
�����Ă��~���߂���Ɩ�Ԃ͂����Ɨ������Ȃ�C�|���z�c�𒅂ĐQ����悤�ɂȂ�܂��D��M�B�̉Ă͒Z���C�����n���̂�����X�ł����D
��w�i�w���Ă��獡���܂ŁC�قږ��É��Ő������Ă��܂����C���É��̉Ă͒����������������ł��D����́C���N���̐M�B�̉Ă��S�Ɏc���Ă���̂ł��D
[2] 8���Ƃ����Α����m�푈���I��������ł�
2-1. �I�풼�O������̕����܂ł̏o����
���N�͏I��80�N�ڂɓ�����܂�����C���������V�������_����̎��g�݂����邩�Ɗ��҂��Ă���܂������C�S���ʔN�ʂ�ŁC�w�푈�͔ߎS���I�x�w��x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ��I�x�Ƃ��������̘_���ɏI���܂����D
�b�͔�т܂����C�ŋ߃C���^�[�l�b�g���֗��ɂȂ�܂����D�����wCopilot�x���wGemini�x�����wAI�x�����s���Ă��܂��D
�M�҂��g���n�߂āC���̔\�͂ɋ����Ă���܂��D�������������ƁC�l�b�g�ɂ���c��Ȏ�������b���܂Ƃ߂ĕ��Ă���܂��D
�C�ɂȂ��Ă�������Ŏ��₷��ƁC���̉̓Y�o�b���w�I���ˊт����x�������w����ς�I�x�w�����I�x�ƌ��������z���N�������C�M�҂͍��n�}���Ă��܂��D
�����̎Љ�Ɛ��������邽�߂ɁC���X���X�wAI�̊��x�͕ω����Ă���l�q�ł����C���̂Ƃ���C���{�̈ӌ����Ƃ��C���̒��̗��s�肾�Ƃ��C���{�Ɠ��̜u�x�Ȃǂ��������Ȃ��Y�o�b�Ƃ������܂�������悤�ł��D���ЊF���܂��C�����̋K�����|����ʍ��̂����ɂ����������E�߂��܂��D
�ȉ��C�����ƈ�����p�x����C�����m�푈�O��̗��j�߂Ă݂܂��傤�D
2-1-1. �w�Ȃ����E���̌���������8��6���������̂��x
���̖₢�ɂ́C����ׂ�������܂����D1945�N2���N���~�A�����ŊJ���ꂽ�č����[�Y�x���g�哝�́E�p���`���[�`���E�\�A�X�^�[�������L�����w�����^��k�x�ŁC�w�h�C�c�~����3�J����Ƀ\�A�͓��\�s�N����j���đΓ�����ɎQ������D���̌��Ԃ�ɁC�����암�Ɛ瓇���\�A�ɗ^����c�c�x�Ƃ��������킳��Ă����̂ł����D
����A�C���V���^�C���Ȃǃh�C�c�ǂ�ꂽ���_���n�̕����w�҂́C�i�`�X������w���q���e�x�����Ȃ��Ɛ��E�̓i�`�X�ɐ�̂����Ƃ��������ϔO����C�哝�̂ɒ��i���C�}���n�b�^���v��̖��̂��ƂŖ����Ɍ������J�����Ă��܂����D
1945�N7��16�����������w�g���j�e�B�[�����x�����̕��g���[�}���哝�̂ɓ͂��܂��D
�h�C�c��5��7���������~�����Ă��܂�������C�����^�̖���Ń\�A��8��7���ȍ~�C���\�s�N����j�����đΓ�����ɎQ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��D�����ɕ��������������̂���ȂǁC�h�C�c�̐�㏈���ł̓\�A�ɍD������ɂ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁC�č��̎��͂ŏ��������Ƃ����`�ɂ���K�v������C�M���M����8��6���Ɍ��������ɓ��ݐ����Ƃ���Ă��܂��D
���������̎��������Ȃ�������C8��15���̓��{�̖������~�����x��C�\�A�R���k�C���ɏ㗤���C�k�C�������̒��N�����̂悤�ɕ������ꂽ���ꂪ����܂����D
�ڂ����͈ȉ���YouTube���Q�Ƃ��ĉ������D
-
�w�}���n�b�^���v��̂������ɂ��āx
-
�w���������Ƃ��̔�Q���ɂ��āx
-
�w�g���[�}���哝�̂̉�z�x
1996�N�w�č���R�����فx�����w����@�����܂���
�����ł́C���q���e�Ɋւ���W�����s���Ă��āC����E��풆�ɊJ�����ꂽ�����̖͌^��C�}���n�b�^���v��Ɋւ��鎑���C�����̎ʐ^��f�������Ȃǂ��W������Ă���C�����J���̌o�܂₻�̗��j�I�w�i�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂��D�܂��C���ۂɌ����𓊉�����B-29�����@�u�G�m���E�Q�C�v�̎��@�W��������܂����D
�w���������ɂ���Đ푈�𑁂��I��点�邱�Ƃ��ł��C�ĕ��̖����~�����c�c�x�Ƃ���������������Ă��܂����D

|

|
2-1-2. ���V�A�Ɠ��{�̍������

���X�ŗL���ȃI�z�[�c�N�C�́C�V�x���A���痬�ꍞ�މh�{�L�x�ȒW���ɂ��\�w���̒W�������ƁC�[�w���̔Z��������2�w�ɕ�����Ă��āC���Ǝ������L�x�Ƃ���Ă���C�܂��C�������ӂł́C�Ζ��E�V�R�K�X�������L�x�ł���Ƃ���Ă��܂��D
�k�C�������ē��k�������V�A�̂Ƃ���C�I�z�[�c�N�C�̓��V�A�̓��C�Ƃł��C�j�𓋍ڂ������q�͐����͂�z�u����C��ɍU������Ȃ������̕ۊnjɂɂȂ�킯�ŁC�R���I�D�ʂ��m�ۏo���܂��D
��ɏq�ׂ������^�̖���ŃX�^�[�������_�����{�S�́C�k�C�������ɂ������Ǝv���܂��D
����8��15�����a�V�c�̃|�c�_���錾����̋ʉ������������āC�����m�푈���w��������߁I�x�̏�ԂɂȂ������C�\�A�R�����͖��B�y�уI�z�[�c�N�C���ʂŁC�~���̒���(9��2��)�܂ł͐푈���ł���Ƃ��Đi�R�𑱂��܂����D
-
�w�������~����C�\�A�̖k�C���N�U�Ƃ����j�~�������{���̘b�x
����قǂ܂œw�͂��Ď�ɓ��ꂽ�瓇�I���̌R���I���l������C�\�A�ɂ��w�k���l���̕Ԋҁx�Ȃǂ͂�����͑S���Ȃ������Ǝv���܂��D
���V�A���w�E���V�A���w�E�o���G�E���y�͂��炵���̂ł����C���l�����������x�z���Ă��镡�����ƂŁC���낵�����ʂ������Ă��鎖��Y��Ă͂Ȃ�܂���D
-
�w�V�x���A�}���x
-
�V�x���A����̉䂪�q�̋A���҂�̉́w�ݕǂ̕�x
2-1-3. �푈�́w�A���n����x�̑��ʂ͗ɂ���ď�������ꂽ
���I�푈�́C�����̔��l�Ɏx�z����Ă����L�F�l��̐A���n�ɂƂ��āC���������ł��Ɨ����ł��������Ƃ�����]��^���܂����D
��ꎟ���E����C���{�͂Ȃ�ƍ��ۘA���̏�C�������ɂȂ�܂����D
���F�l��ł�����{�͏�C�������Ƃ����w�l�퍷�ʔ��̑匴���x�����ۘA���Ɏ����������Ƃ��܂������C�����ł��܂���ł����D
�A�W�A�ł́C���{�ƃ^�C�������Ă��ׂĂ̍������Ă̐A���n�ƂȂ��Ă��܂����D��̓I�ɂ́C�C���h(�p)�C�p�L�X�^��(�p)�C�~�����}�[(�p)�C�}���[�V�A(�p)�C�x�g�i��(��)�C���I�X(��)�C�J���{�W�A(��)�C�u���l�C(�p)�C�}���[�V�A(�p)�C�C���h�l�V�A(��)�C�t�B���s��(��)�C���X
100�N�O�C��p�Ɗ؍��Ƃ͓��{�̐A���n�������Ƃ����l�����܂����C����͊ԈႢ�ŁC�F�����w���{�b���x�������̂ł����D�ːЏ�͓��{���œo�^����C�����`��������C�����������x�ł����D���Ă̐A���n����Ƃ͑S���قȂ��Ă��܂����D�Љ�C���t���C��b���炪�[�����Ă����̂ŁC�I���C���{�͋}�������܂������C��p�Ɗ؍��͓����悤�ɋ}�����𐋂��C�����I�ɂ͓��{�𗽉킷�镔����o�Ă��܂����D
���ɋ}���������̂��C�Ɨ���ʂ����w�^�C�����x�ł��D��ɏq�ׂ����Ă̐A���n�������e���̌o�ϔ��W�̐i�x������C��p�E�؍��Ƃ̍���������Ǝv���܂��D���ꂪ�C��p�E�؍���������w�A���n�x�łȂ��������Ƃ̏؋��ł��D
���{���猩�������m�푈�̂�����̖ړI�́C���Đ�i���̐A���n����̖������������ɁC���h��F�̐��_�̉��ŃA�W�A���Ƃ���邱�Ƃł����D�푈�O���͔j�|�̐����Ői�݂܂������C�㔼�ɂȂ�ƁC�⋋�Ԃ��f����C���Ƃ���H���B�i���D�j����悤�ɂȂ�C���S������Ă��܂��܂����D
���q�����ЊQ�����ɏo������Ƃ��́C�މ@�̐H���͎��Ȓ��B���Ă��܂��D�������q�������H�����ꂽ�ƌ����Ė��Ԑl�̐H�Ƃ�����肷��ǂ��Ȃ�ł��傤���c�c�D����ȏ�Ԃ����{�R�̐�X�ŋN�����悤�Ȃ̂ł��D����ɂ܂������Ƃ́C���{�R�͕����Ĉ����グ�Ă����܂��ƁC�߂��Ă����@�卑�́C�l�������{�ɂ��Ȃ��悤�O��I���w���{�͋��\�ȐN���҂ŁC�@�卑�����̐N������A���n�Z����������x�̂��Ƃ����v�z������s�Ȃ��܂����D
�w���ɂ����鋴�x�ŗL���ȃ^�C�ƃ~�����}�[���q���S���́C�f��ł͓S���̕��������j����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����C�A���n�ł͂Ȃ������^�C���́C�푈��C�����ꍡ���g���Ă��܂��D�~�����}�[���́C�C�M���X���{�̈ӌ��ɂ��j�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��āC���̔p���̘e���w���{�����e���ł��ǂ��Č��n�l�ɓS���~�݂���Ă��鑜�x�������Ă��܂��D
���̂悤�ɓ��{���������g������C�Ɨ��^�����ĊJ���Ȃ��悤�ɏ@�卑���K���ɂȂ��ē��{�R�̐A���n����̏؋����B�ł����̂ł����D
-
�w�Ɨ��^�����w�����Ă����A�W�A�̎w���҂̓��{���ߘ_�x
2-1-4. ���a�V�c�͍~���Ɛ��̕����ɐs�͂���
�����N��Ƃ��āC���̈ӂ����ނ��Ƃɏd���𐬂��Ă����̂ŌR���̖\�����~�߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����D
�j���ɂ��C�������̎��������ēc���`������������ӂ�����C�Ԃ��Ȃ��}�������i1929�N9���j�D�w�V�c�Ɏ����ؕ������x�ƌ����\���������ƌ����܂��D���̎����ɂ�菺�a�V�c�́C�R���̖\�����~�߂�͂̌��E��m��̂ł����D
�������������~���i�|�c�_���錾�j��������邩�ۂ��̏�ʂł́C�R�̔��Θ_�������̂��C�S�ցE���Y�Ƃ����������������o��̏���C��������肵���̂͏��a�V�c�������Ƃ���Ă��܂��D
-
�s��Ƃ��ꂩ��̓��{�̓������������a�V�c�̋ʉ�����
-
�ʉ��������㕶��
-
�w�s���̓��{���~�������a�V�c�c�c�x
�Q�l�܂ł�
-
�s��Ƃ��ꂩ��̓��{�̓������������a�V�c�̋ʉ�����
�y4K�J���[�z���b�\���[�j�̍Ŋ� - The Execution of Benito Mussolini in Color
-
�q�g���[�̍Ŋ���24����
-
�q�g���[�̍Ŋ�
2-2. ���������Ȃ������m�푈���N�����̂�
�č��̑����m�헪���O�҂̗���Ō������ƁC�ȉ��̗l�Ȍ������o���܂��D
�����Ԃ�����܂�����C���Z������l�b�g�ŁC���ɂ��wAI�x���g���Ē��グ�C���Z�̓Ǝ��̗��j�ς��m�����邱�Ƃ����E�߂��܂��D
1995�N�����푈�Ɖ��֏��
1960�N�A���[�푈���I�����邽�߂̖k������ꃍ�V�A�͂��̒���������܂������̌��т𖼖ڂɃ��V�A�͐V���版�C�B���l�����C���V�A�͔O��̕s���`�E���W�I�X�g�N���R�`�Ƃ��Đ������܂����D
�l���Ă����ɑ_���̂͊؍��ł��D���̊؍��͐����̑����ƂȂ��Ă���C���V�A�̋����ɂ������Ċ؍�����������Ƃ��l�����܂��D
����œ��{�͊؍���Ɨ����Ƃɂ��ēƎ��ɓ��{�ƍ��������������C���V�A�̍X�Ȃ�쉺�̖h�g��ɂ������ƍl���܂����D
���֏��ł́C�@���N�����̓Ɨ��@�A��p�����@�B�ɓ������̗L�@�C�����������߂܂������C���V�A�̓h�C�c�E�t�����X�Ƒg��ŇB�𒆎~�������i3�����j�D
���̂��Ɨɓ������암�i�����j�̓��V�A���d���C��ƌR�`�����݂����D
1998�N�Đ��푈�C�t�B���s�����A�����J�̐A���n�ɑւ��
�A�����J�̖c����`���~�܂炸�J���u�C�̃L���[�o�E�h�~�j�J���̗̗L���߂����ăX�y�C���Ɛ푈���N�����C�X�y�C���ɏ����������ߑ�q�C���ォ��̃X�y�C���̔h�����A�����J�������p���`�ɂȂ����D�����m�Ō����O�A���E�t�B���s�������܂ł��č��̎x�z���ɂȂ����D
1904�`1905�N���I�푈
���̐푈�́C�p�Ăɏ悹���Ă���Ă��܂����푈�Ƃ����ʂ�����܂��D���V�A�����N������{�ւ̐N�U��_���Ă���ƒ������C�R�͂t���C�����Ƃ����Ƃ��̓o���`�b�N�͑��ɃX�G�Y�^�͂��g�킹�Ȃ��Ƃ������p���������сC�����炯���������̂��p���ł����D
�푈���������C���{�̍��͂̌��E�����ɂߘa���H��ɏ��o�����̂��č��ł����D���ʂƂ��āC�R�͂���e��܂ł荞��ŗ��v���҂��C����͈�C�̌��𗬂������V�A������ɒǂ�������C�p���ƁC�č��̊O����r�͂��������ł����D
���I�푈�͑S���E�ɑ傫�ȉe����^���܂����D
- ���{���g�́C���E�ŋ��Ƃ���ꂽ�o���`�b�N�͑���S�ł��������M���C�C�R�����͎�`�ɒǂ�����C��N�푈�����̌͊������Ŏ���ł͎g���悤�̂Ȃ��������w�����x�C�w��a�x��グ�C�G���Ɉꔭ�̖C�e�����猂�����܂����v���܂����D
- �L�F�l�퍑�Ƃ����l���ƂƐ���ď��������ŁC�A���n����̓Ɨ��^���������ɂȂ�C���{�ɐ������̎u�m���W�܂�悤�ɂȂ�܂����D
�����E�����E�v���m�c�c���X
���{�ɂ��A�W�A�̘A�т�������A�W�A��`�̎v�z���L�܂�C�Ɨ��^���Ƃ������x������l����������܂����D���{�B�E�{���V�E���R���c�c���ł��D - 2018�N�o���g�C���ݏ����𗷂����Ƃ��C���{�l�ƕ�������w���V�A��������Ă���Ă��肪�Ƃ��x�ƌ����C�ǂ�ʃ��V�A�������Ă��邩��m��܂����D
1910�N ���ؕ���
���������̑����Ƃ݂Ȃ��Ă����؍���Ɨ������C��ˊJ���ƃ��V�A�̖h�g��ɂ��������{�̈ӌ��̕s��v�œ����푈�͋N���C�؍���Ɨ����������C�̊Ԃłӂ�ӂ�Ƃ��ă��`�������Ȃ��̂ŁC���{�ɕ��������D
����
1912�N���ؖ��������i�h��v���E�����ŖS�j
���Ԃ͌R�������̎���ցc�c
1914�N�`1919�N ��1�����E���
�O�������i�h�C�c�鍑�E�I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�E�I�X�}���鍑�j�ƎO�������i���V�A�E�C�M���X�E�t�����X�j�̐푈
���{�͓��p�����̊W�ŁC�O���������ɕt���C�����̃h�C�c�̂ɏo��
�����C�č��͒����̗�����Ƃ�C�o���ɕ���e��������ċ����̗����D�h�C�c�̐����͍U�����āC1917�N�O���������ɉ��S���܂����D
1917�N�̃��V�A�v���ɂ���āC���V�A�͐푈���痣�E���܂����D
2-2-1. ��1�����E����̓��{�̌��v�g��
�����[���b�p����ɋ��X�Ƃ��Ă���ԁC���{�͓��p�����ɏ]���p�����ɉ��S���D1919�N�ɂ͈��G���h�C�c���v�̎R���Ȃ�C�h�C�c�̓�m�������̂��܂����D���̌��ʁC�����m�͓��Ă̔e�������̕���ƂȂ�܂����D
�w�č��̑����m�����͊g��x
���L�̂悤�ɐ��͂��}�g�傳���Ă����܂����D
| 1865�N | ��k�푈�I�� ���̎��_����č��͋���ȍ��ƂƂ��ČN�� �˓��{�̖����ېV�ɑ������� |
|---|---|
| 1867�N | �A���X�J�ƃA�����[�V���������V�A���甃�� |
| 1867�N | �~�b�h�E�G�[�������C���l���������̂ŗ̗L |
| 1898�N | �n���C������č��̏��B�Ƃ��ĕ��� |
| 1898�N | �Đ��푈�ɏ������C�t�B���s���E�O�A���̓J���u�C�����Ƌ��ɃX�y�C�����犄���C�C�m���ƃX�y�C���̗��������D���� |
| 1899�N | �T���A�����������O�����Ŋl�� |
�w���{�̑����m���͌��̊g��x
���������{�����͂��g�債�Ă����܂����D
| 1868�N | �����ېV �ߑ㉻�ւ̑��� <��1965�N��k�푈�I��> |
|---|---|
| 1895�N | ��p���� |
| 1910�N | �؍����� |
| 1919�N | ��1�����E���̐폟���Ƃ��ē�m�����ϑ����� |
�i�X�y�C���E�|���g�K���E�p�E���E���j�ɒx��ċ}�������C�X�y�C����|���Ĕe�҂Ƃ��ċ}���������č��ɂƂ��āC���{���ǂ̂悤�ɉf�������I�͑z���ł���D
�ˑ�ꎟ���E����͕č��͉p���ɖd��C���{�������ĂāC���V�A�̓쉺����̏��ɂ�����p������j�������C�V�����w���V���g����c�x�œ��{�鐭���ł��o���Ă���
2-2-2. ��1�����E����̃��[���b�p�̕ω�
�yA�z���Y��`�����̒a��
���V�A�鍑��1917�N���V�A�v�����o�āC1922�N�\�r�G�g�Љ��`�A�M�ɕϐg���C���E�ŏ��߂Ă��w���Y��`�������Ɓx���a�������̂ł����D
�\�A�͂��̗B��̋��Y��`�̎��������ׁC�e���ɎЉ��`�̎�������C�v�����N�����l�ނ��琬���C�w�J���ҊK���̉���x�̂��߂Ɋe���֊g�U�������D
�yB�z�鍑�͕��C���a���Ƃ��čďo������
�h�C�c�鍑�˃h�C�c���a���{�|�[�����h�֕Ԋ�
�I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�˃I�[�X�g���A���a���{�`�F�R�\���o�L�A�{�n���K���[�{���[�S�X���r�A
�I�X�}���鍑�˃g���R���a���{�V���A�{���o�m���{�p���X�`�i
����̃��[���b�p�̓��F���T�C���̐��Ƃ���
(���[���b�p�̒鍑�͉�̂���C����{�鍑�݂̂��c�����D)
�yC�z�A���n����^���̊�����
1905�N���{���o���`�b�N�͑�����ł����C���l�̋���鍑���V�A�ɏ����������Ƃ��C�̎x�z�ɋꂵ��ł����e�A���n�̖��������Ƃ������h�������D�����ē��{�Ŋw�������n�ߒ����̎u�m������1911�N���w�h��v���x���N�����C������|���C�w���ؖ����x���������܂��D���̉e���ł܂��܂��w�A���n����̓Ɨ��x�^��������ɂȂ�C�e���̎u�m�����̈ꕔ�����{�ɏW�܂��Ă��܂����D
�yD�z���ۘA���̒a��
AI���wGemini�x�ɖ₤�ƁC�ȉ��̉��܂����D
(1) ���ۘA���a���̌o�܁C���̑g�D�́C���̐��ʂ́c�c
���ۘA���́C��ꎟ���E���̎S�Ђ��x�ƌJ��Ԃ��Ȃ��Ƃ��������肢����a�������C�j�㏉�̖{�i�I�ȍ��ە��a�ێ��@�ւł��D���̐ݗ��ɂ́C�A�����J�̃E�b�h���E�E�E�B���\���哝�̂������u�\�l�����̕��a�����v���傫�ȉe����^���܂����D
�a���̌o��
���ۘA���́C��ꎟ���E���̍u�a���ł��郔�F���T�C�����Ɋ�Â��āC1920�N�ɃX�C�X�̃W���l�[���ɖ{����u���Đݗ�����܂����D�������C���ł���A�����J�́C�c��̌Ǘ���`�I�Ȕ��ɂ��������܂���ł����D�܂��C�s�퍑�ł���h�C�c��v����̃\�A�������͎Q�����F�߂��܂���ł����D
�g�D
���ۘA���͎�Ɉȉ���3�̋@�ւō\������Ă��܂����D
-
����: ���ׂẲ��������Q�����C�ꍑ��[�̌����ʼn^�c����܂����D�d�v�Ȍ���͑S���v�������ł����D
-
������: ��C�������Ɣ��C�������ō\������C���ە����̉����Ȃǂ�S���܂����D��C�������́C�����͓��{�C�C�M���X�C�t�����X�C�C�^���A��4�����ł����D
-
������: �A���̓���Ɩ���S����݂̎����@�ւł��D���������ɂ́C���{�̐V�n�ˈ���A�C���C���ۓI�ȐM���܂����D
�܂��C�֘A�@�ւƂ��ď�ݍ��ێi�@�ٔ�����**���ۘJ���@�ցiILO�j**���ݒu����܂����D
���ʂƌ��E
���ۘA���́C�������̒n�整������������ȂLj��̐��ʂ��グ�܂������C���̗L�����ɂ͌��E������܂����D
-
����:
�n��I�ȕ����̒��فi�X�E�F�[�f���ƃt�B�������h�Ԃ̃I�[�����h�������Ȃǁj
-
���ۋ��͂̐��i�i�o�ρC�Љ�C�����C�l������j
-
-
���E:
�卑�̕s�Q��: �A�����J���s�Q�����������Ƃ́C�A���̌��Ђ����ቺ�����܂����D
�S���v�̌���: �d�v�Ȍ���ɑS���v�����߂邽�߁C�v���ȑΉ�������ł����D
�R�����ق̌��@: �������������邽�߂̗L���ȌR���͂��Ȃ��C�o�ϐ��ق������͂��ォ�������߁C�卑�̐N���s�ׂ�h�����Ƃ��ł��܂���ł����D
�����̌��E�́C1930�N��̖��B���ςɂ�������{�̍s����C�C�^���A�̃G�`�I�s�A�N�U�ȂǁC�̐N���s�ׂ�j�~�ł��Ȃ��������ƂŘI�悵�܂����D�����āC����E���̖u���ɂ���Ă��̋@�\�͊��S�ɒ�~���C����**���ۘA���iUN�j**�ւƈ����p����C1946�N�ɐ����ɉ��U���܂����D
(2) ���ۘA���ɂ�������{�̗����ʒu�Ɗ���
���{�͏�C�������Ƃ��� �l�퍷�ʓP�ސ錾���Ă���
���ۘA���ŏ�C�������Ƃ��Đl�퍷�ʓP�ސ錾����悤�ɓ�����
���{�̐l�퍷�ʓP�p��ẮC���ۘA���̐ݗ����c�_���Ă���1919�N�̃p���u�a��c�ŁC�S����\�̖q��L�������S�ƂȂ�s���܂����D����́C���ۘA���K��Ɂu�l�킠�邢�͍��Д@���ɂ��@���゠�邢�͎����㉽�獷�ʂ�݂��Ȃ��v�Ƃ��������荞�����Ƃ�����̂ł����D
��Ă̔w�i
��ꎟ���E���ŏ����������{�́C�p���u�a��c�Ŏ�v�폟���̈���Ƃ��ĎQ�����܂����D�����C���{�͉��ėƌ�����ׂ鑶�݂Ƃ��č��ۓI�Ȓn�ʂ��m��������܂������C����ŃA�����J��J�i�_�Ȃǂł͓��{�l�ږ��ɑ���r�˖�肪�[�������Ă��܂����D���̒�ẮC�����������ʂ��Ȃ����C���ێЉ�ł̓��{�̒n�ʂ��m�ł�����̂ɂ��悤�Ƃ�����̂ł����D
��Ă̌o�߂ƌ���
-
�e���̔���: ��Ă͑����̍�����x���܂������C���ɃA�����J�ƃC�M���X�����������܂����D�A�����J�͍����ɐ[���Ȑl���������Ă���C�C�M���X�͐A���n�ł̎x�z�ɉe�����o�邱�Ƃ����O�������߂ł��D
-
�ŏI�I�Ȍ���: ��Ă͎^�������ō̑�����܂������C�c���߂��A�����J�̃E�B���\���哝�̂��u�S���v�łȂ����ߕs�����v�ƈ���I�ɐ錾���C�ŏI�I�ɍ��ۘA���K��ւ̋L�ڂ͌������܂����D
���̒�Ă͎������܂���ł������C���ێЉ�ɂ����Đl�핽���m�Ɏ咣�����ŏ��̎��݂Ƃ��āC���j�I�ɏd�v�ȈӋ`�������܂����D
2-2-3. 1929�N���E�勰�Q���n�܂�
��1�����E���́C���ɂȂ�Ȃ������č����C���ɂȂ��Ă��܂�����e������Ȃ��Ȃ������B�Ɍ����ėA�o���邱�ƂŔ���ȗ��v�܂����D���̗L��]�鎑�����C����̐�[�ł��鎩���ԁC�q��@�c�c���ɓ�������C���ꂪ�V���ȕx����сC�č��͖��\�L�̂����������������C���E�o�ς̒��S�����B����A�����J�ֈڂ������ł�����܂����D
�č��Ɠ��l�����ɂȂ�Ȃ��������{���푈�����ł킫�C�D�i�C�Ɍb�܂�܂����D
�吳�f���N���V�[��_���K�[���͂��̍��̎��ł����D
1929�N10���C�j���[���[�N�،�������̊�����\���́C�u���ԂɑS���E�ɍL�����w���E�勰�Q�x�ƂȂ�܂����D
���Y�ݔ����g�傳��C�w���́x�͗L��]���Ă���̂ɔ����Ă����l�����Ȃ��I
�����Ă���Ȃ�����C����������Ȃ��I
����������Ȃ�������͕����Ȃ��I
���������炦�Ȃ�����̂������Ȃ��I
���̕��̘A�����n�܂��Ă��܂����̂ł����D
�Z���I�ɍl���܂��Ƃ��̑�s����ł��オ��ɂ́C�R���g�����R���Y�Ƃ������I
�����ɐN�����V�����s����J��c�c�Ƃ����̂��N�����l���鎖�ł��D
�h�C�c�̓i�`�X���䓪���C34�N�q�b�g���[�������ɁC�ČR�����i
�C�^���A�̓t�@�V�X�^�}�����C�G�`�I�s�A��
���{�͌R���̑䓪�C���B������
���̌����́C�`�������ł��Љ��YouTube�̓���̂Ƃ���ł��D
�勰�Q�ƑΛ��������[�Y�x���g�哝��
�A�����J�ɂ����Ă�1933�N�ɓ��I�������[�Y�x���g�哝�̂��W�J�����j���[�f�B�[������ɂ���āC�勰�Q�̉������}��ꂽ�ǂ�����Ă��܂����C���̐^�U�̒����wGemini�x�Ɋm���߂܂��ƁC�ȉ��̉܂����D
�j���[�f�B�[������̕]��
�j���[�f�B�[������́C�A�����J�o�ς����S�ɉ������킯�ł͂Ȃ��C����E���ɂ������ɂ���čŏI�I�ɋ��Q����E�o�����Ƃ�����������ʓI�ł��D�������C���{�̖������g�傳���C���{��`�̂������傫���ϊv�����Ƃ����_�ŁC���j�I�ɔ��ɏd�v�ȈӖ��������Ă��܂��c�c�D
���̉ɗ͂āC���܂łɂ��̕������l�������w�����m�푈�̉B�ꂽ�ʁx�����Љ�����Ǝv���܂��D�ǎҏ��Z�ɂ�����܂��ẮC�����g�ōēx���m���߂��������D
���[�Y�x���g�哝�̂�1941�N�̑����m�ɂ�����s���l������ŊJ���邽�߂ɂ́C�č��{�����牓�����ꂽ�������m�ŁC���{��@�������Ȃ��ƌ��ӂ����D
-
���{�̈͂�ABCD��͖Ԃ����C�Ζ��E�A���~�E�S�����̎������͊������邻������C���z�����Ă��邾�낤�D
-
���{���U�߂Ă���Ƃ���ΐ^��p�ł��낤�D�Â��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��R�͂�^��p�ɏW�߂Ă����C�p�̐��[���̂ŁC�K�v�Ȋ͑D����������ďC������悢�D�M�d�ȋ��ƍq��@�͗m��őҋ@�����Ă����Ηǂ��D
-
��P�����ƂȂ�Εč����_�͈�ۂƂȂ��đœ|���{�ɂȂ�C���z�̗\�Z���t���C�R�������ƁC�s������̒E�o���ł���c�c�D
-
���{�R�͂܂�܂Ƃ���㩂ɂ͂܂�܂����D�������ȉ��̂悤�Ȃ��܂��t���Łc�c
-
���O�ɐ��z�����Ă���̊�P�U���̗\�肪�C�Í���ǂɎ��Ԃ��|����C��g�ق���č����{�ւ̒ʒB���C�U���̌�ɂȂ��Ă��܂����D
���̌����w���{�͔ڋ��ҁx�Ƃ������b�e����č����{�ɕt������C�č����͈�ۂƂȂ��ē{��ɐk���錋�ʂɂȂ����D
-
��2�C��3�g�̍U���ŁC�R���^���N�C����ɂȂǑS�Ă��j���o��ł������`���ɋ�ꂪ���Ȃ����ƂŁC���{���͑��͕č��̋�P�������1�g�U�������ň����Ԃ����D
-
-
�U��������̐^��p�ł́C��ԌÂ��w��̓A���]�i�x����{�R�̐^��p��P�ɂ�����L�O��Ƃ��ĕۑ������D
YouTube�̓A���]�i�L�O�فiUSS Arizona Memorial�j: �^��p�U���Œ��v������̓A���]�i�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�C�ł��L���ȋL�O�قł��D�]���ƂȂ��������̏�g���������D�̂̒��ɖ����Ă���C�ԗ�̏ꏊ�ƂȂ��Ă��܂��D�{�[�g�ł����s�����Ƃ��ł����C���O�\�K�v�ł��D���v������͂̍b�������낷���Ƃ��ł��܂��D
-
���v�����ŐV�s�̐�̓~�Y�[���́C�����Ɉ����g���C�C�����đO�����A�����C�����m����ő劈�C1945�N9��2���̓��{�̘A���R�ɑ��閳�����~���̒���́C���̐�̓~�Y�[���͏�ŏd���O����b�ɂ�点���̂ł����D
�~�Y�[���L�O��
-
�����ٔ�
�ٔ��̒����͉��LYouTube���Q��
�ٔ��̊J�n��4��29���@�c�c�c�c�c�c�c�c�i���a�V�c�̒a�����j
A����Ƃ̏��Y����12��23���c�c�c�c�i��c�É��̒a�����j
���R�̈�v�H�H�H
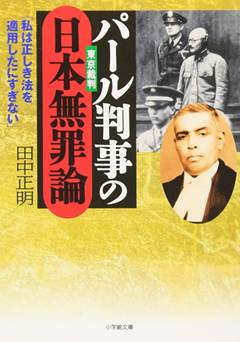
�p�[�������̓��{���ߘ_ �p�[�������̓C���h����y���Q�����w�����ٔ�15�l�̔����x�̈�l�D
�����ЂƂ薳�߂��咣�����l�ł���D
��� �c�������́C�M�҂̏f���ł��D
�M�҂�8���ւ̎v���Ƃ����^�C�g���ŏ����n�߂܂��������X�Ƃ��ݏグ�Ă�����̂�����܂��Ďv�킸�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����D
�ǎҏ��Z�������m�푈�ɂ��ď����ł������̂��Ƃ��m�F���Ă��������C���N��8���͂����Ɛ[���v���������ďI��L�O�����}���Ă������������Ǝv���܂��D
2025�N9��13��
(��)J�R�X�g������ ��\ �c�����m
2025�N6��
���� �G�߂̂����A
6���ɓ���C�~�J���n�܂��ۂ�җ�ȏ������P���܂����D
�F�l���������߂����ł��傤���D
�e���r�ł͒�����M���Ǒ�ɂ��Ă̒��ӂ�������C���ɒ��ӂ��ׂ��́C�c���q�������ŁC�g�����Ⴂ���߁C�H�ʂ�����t�˔M��S�g�邱�ƂɂȂ�̂ŔM���ǂɂȂ�Ղ��Ƃ̂��ƁC�܂�����҂́C�m�o���݂��Ȃ�Ղ��C�����Ƃ�������C�������������ɓ݊��ŁC�M���ǂɂ�����Ղ��Ƃ��������������Ă��܂��D
����҂ŁC�������̕M�҂́C�L���L���ɗ�₵���Β��ƃX�|�[�c�h�����N�őΉ����Ă��܂��D
�F���܂��C�䎩���ɍ��킹�������⋋���ŁC���̍����������Ă��������D
���āC�C�O�ɖڂ����܂��ƁC2025�N6���́C���E�j�̋��ȏ��ɍڂ�悤�ȑ傫�ȏo����������܂����D���̎�ȏo�����ƁC���{�ɋy�ڂ��e�����C���ЂȂ�ɐ���Ă݂����Ǝv���܂��D
(1) �؍��́w�����x�́w���ݖ��x���哝�̂ɏA�C�����D
�؍���1997�N�ʉ݊�@�Ɋׂ�C�����͂܂����W�r�㍑�ł���Ƃ��Đ�i��������̉����̎肪�����L�ׂ��C��@��E�o���܂����D���̌�C��ՓI�Ȕ��W�𐋂����Ƃ��āC�������ɔF�߂�n�ʂ��m�ۂ��݂�܂����D
�����̌o�ς̐��Ƃ����́C���؍��������ɔ��肳���Ă��鐻�i�́C�H�Ƃ̔��W�ƂƂ��ɒ����̕����؍����������ł���悤�ɂȂ�D���{�Ƌ��͂��đS���E�ɑł��ďo��̐����\�z���ׂ��ƒ�Ă��Ă��܂����D
���哝�̂́C�w�����x�w�e�k���N�x�w�e�����x�ɑǂ����C�o�ϐ��Ƃ̌����Ƃ���ɂȂ��Ă��܂��C���̏��������̎��s�����܂��āC�؍��̌��݂̍��̎؋��C��Ƃ̎؋��C�l�̎؋��̎O�d�������Ă��܂����ƌ����Ă��܂��D����́C1997�N�̒ʉ݊�@�����Ђǂ���ԂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����Ă��܂��D
���Ȃ݂Ɍ��ݓ��{�͑�p�ƃ^�b�O��g�݁C�F�{�ɋ���Ȕ����̍H�����萢�E�ɑł��ďo�鏀�������Ă���܂��D
���悢����{�ƒ����ɋ��܂�Ă����̒��ŁC�O���̛��哝�̂́C���܂ł̓��؊W�Z�������{�Ƃ̊W�C���ɑǂ���C�X�Ȃ�A�g�̓���T���Ă��܂������C�w�����x���咣�����w���ɖ���}�x�̋���Ȕ��Ή^���̑O�ɔs��C�e�N�ٔ��ɂ܂ŋy�т܂����D
����6���̑哝�̑I�œ��I�����̂́C�w�����^���x�̌����Ƃ������ׂ��C���ݖ��哝�̂Ȃ̂ł����D�ނ��؍����ǂ������Ă������C���ڂ��K�v�ł��D
���݂ɁC�؍��́w�����^���x����ڂŗ�������ɂ́CYouTube���w�؍��E���J���g�}�\�x�ƌ�������C���E�������������Ԃ��f���o����܂��D
���̈�����́C���ƂȂ��������ŁC���E�߂��܂��D
(2) �������N�_�́C���E�勰�Q�̈������ɂȂ鋰�ꂠ��
�M�҂̑̌��k���炨�b�����܂��傤�D
2013�N�����C�ɂ���R���T����Ђƌ_�C�h�B�C�Y�B�C�͓�ȓ��ŔN��10��قǍu����R���T���e�B���O������Ă��܂������C�����͖K�₷�邽�тɊX�̌`���ς��قNj}���Ȕ��W�����Ă���܂����D
�ꉞ�܂��z�e���ɏh�����Ă��܂������C���{�Ƃ̈Ⴂ�͂ǂ̃z�e�����������₽��ƍL�����ƁC�h�Ń}�X�N�ƃR���h�[���ƃJ�b�v�˂��K���ݒu����Ă��邱�Ƃɕ����̈Ⴂ���o���܂����D
�e���r�ԑg�͖�60�`�����l������CCNN�CABC�CNHK�͎��R�Ɍ����܂����D�C���^�[�l�b�g��Google�ȊO�͎��R�Ɏg�����o��������܂��D
2020�N����͒����K��̓R���i�Œ��f���C2024�N�ɋv���Ԃ�ɖK�ꂽ��C�́C�l�q���ς���Ă���܂����D
�l�ł������Ԃ��Ă����Y������̓����R����́C���������ƒʉ߂ł��C��ʗʂ������Ă���̂��������܂����D�e���r�ԑg�́C������݂̂ɂȂ��Ă��܂��C�����ǂ��Ȃ��Ă邩�悭�킩��܂��C�X�C�b�`�������Ɓw���{�̂��m�点�x�w����ԑg�x�w�o���G�e�B�[�E�h���}�x�̃T���l�C������ʂɏo�Ă�������I��System�ɂȂ��Ă��܂����D
���������������ƂɁC�e�z�e����Wi-Fi�ɂȂ����Ƃ��ł��܂������C�O���l���C���^�[�l�b�g�ɂȂ����߂ɂ͓��ǂ̋���������l�ɕς���Ă��܂��Ă��܂����D
���ǁC���{�Ō_�Ă������X�}�z�́w�C�O�l�b�g�_��x����������ł����D
�����̐����E�o�ς̓}�X�R�~�ł́C2019�N����̍��`�ւ̓��������C�R���i�Ђɉ������C�̋������b�N�_�E���C�o�ϊ����ɑ�_���[�W�C�s�������̍����C�s���Y�o�u������E�E�E�D�C�O���{�̈����グ�E�E�E�D�������Ă��܂����C�M�҂̌o�����猩��C�����Ƃ������́C2019�N�Ƃ����N�����ɂ��đS����������ɂȂ��Ă��܂����C�ƒf���ł��܂��D
���Y��`�����̎����Ƃ����l���ł܂Ƃ߂Ă݂܂��ƁC�ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��D
- �\�A��1920�N�`1990�N��70�N��
- �����[���b�p������1945�N�`1990�N��45�N��
- ������1949�N�`��75�N��
- ���v�J������1980�`2018�͋��Y��`�ł͖��������Ƃ����37�N��
�ŋߍs��ꂽ�_�k�n�g���^���́C�ё��Ƃ������Ɠ������Ƃ��J��Ԃ��悤�Ɏv���܂��D�����̂��ꂾ���̑傫�ȑg�D����}�ƍّ̐��ŃR���g���[���ł���Ƃ͂ƂĂ��v���܂���D�߂������ɉ��炩�̌`�Ő����̐��ɑ�ω����N����Ɗo�債�Ă����������ǂ��ł��傤�D
(3) ���V�A����̊�@
2022�N2��24������n�܂������V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�́C�c��Ȑ�͂�w�i�Ƀ��V�A�̈��|�I�����Ǝv���܂������C�E�N���C�i�̕s���̔��R�Ŏ����������Ă���܂����D
2025�N6���C�E�N���C�i���Ǝ��ɊJ�������e��̃h���[���ƁC�I�݂ȍ��ɂ�胍�V�A�{�y�̔R���{�݂�R���{�݂ɍU�����d�|���C�傫�Ȑ�ʂ��グ�Ă��܂��D
���V�A�����ɂƂ��Ă݂�C�E�N���C�i�N�U�͊O�n�̏o�������������̂��C���V�A�{�y�̗v���v�����U������C�������s��������20%����悤�ɂȂ�C�����̕s�����������������Ă��܂����D
���V�A�����̍����Ԃ�́C1980�N�㔼�̃\�r�G�g�A�M�Ɏ��Ă���̂ŁC���̂܂܍s�����烍�V�A�A�M����̂����̂ł́c�c�Ƃ�������������Ă��܂��D
(4) G7 Summit �̏o���� �č��Ǘ��H�H�H
6��15������17���܂ŁC�J�i�_�̃A���o�[�^�B�ŊJ���ꂽG7 Summit�́C�č��̃g�����v�哝�̂̓C������肪����Ƃ��ď��������ŋA���Ă��܂��܂����D
YouTube��ł́C�č������̏�����̖����b������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��D
�}�X�R�~�̗������Ă��܂��C�x�ʍt�̐��E�ŁC�č��݂̂����[�h�|���h�@�ő����͂��ׂă��[�g���@�ɂȂ��Ă��܂��D����Ȓ��ō��ۋZ�p�W�������[�h�|���h�@�ŏ�����Ă���Ƃ���Α傫�Ȗ����ł��D
�ʉ݂��C���݂̂悤�ȍ��x�ɔ��B�����ʐM�Љ�ł́C�ב֎s��ƘA�����Č݂��̒ʉ݂Ō��ς���C���ےʉ݂Ƃ��Ẵh���͂Ȃ��Ă�������͉\�Ȃ͂��ł��D
�w���O�̃Z���t���C�ɓ���Ȃ����疾������ł�20%�グ��c�c�x�悤�ȍ��Ƃ܂Ƃ��ȃr�W�l�X�͂ł��܂���D�O���[�o���Ȋ�ƂƎ��F�����Ђ́C����ȍ��Ɗւ�肽���Ȃ�͂��ł��D�ւ�肽���Ȃ���Ζ{�Ђ��ڂ��Ă��܂������킯�ł��D
�Ⴆ�A�}�]���ɂƂ��Ă݂�C���E����i�����d����Đ��E���ɔ���킯�ł��D���̕����̃n�u���A�����J�{�y�ɒu���C�A���i�ɑS���ł��������Ă��܂��܂��D
�A�����J�ȊO�̂Ƃ���Ƀn�u�����C�A�����J�ɔ��镪�����ł������邱�ƂɂȂ�܂�����C���R�A�����J����o�Ă��܂��D
�g�����v�哝�̗̂A���ł̋삯���������Ă���ƁC�����̑̂ɐn�����������ĂāC�����̌������Ƃ��Ă���Ȃ��Ǝ����̑̂ɏ�������ƌ����Ă��邱�Ƃɓ������s���ł��D
�W�҂͌�������̂����Ȃ̂ł��@���Ƃ��Ă��܂����C�x���߂���w���D���ɂǂ����x�ƌ������������ł��D�ł����S�オ���č���͕̂č����ł��D�g�����v�哝�̂������悤��10% 20%�̍��łŎ������������ł���͂����Ȃ��̂ł��D
����Ɍ����C�č����ɂƂ��Ă݂�ΗA���i�S���ł����C�A�o���ɂƂ��Ă݂�C�S���E�ɗA�o���܂�����č������͂ق�̐�10%�ɂ����܂���D
�����l�S�V�G�[�^�[�́C���肪�����т��̂ł������莞�Ԃ������Ęb������ł��傤�D
���{�̐��V��b�́C�j�R�j�R���Ȃ��炶���Ǝ��Ԃ�҂��ɏo�Ă��܂��D�ō��̍Ǝv���܂��D
���͎��Ă��܂��C�g�����v���A�������G6 Summit�łǂ�����ăA�����J���O���Đ��E���čs�������b������ꂽ���̂Ǝ��͐M���܂��D
�܂�C2025�N6�����ȂāC�q�m�L����̏�ɃA�����J�͂��邯��ǁC�N���A�����J�ɂ܂Ƃ��ɘb��������l�͂��Ȃ����オ�n�܂����Ǝv���܂��D
(5) �A�����J�̃C��������
2025�N6��22���C�����̊j�{�݂�č��̃X�e���X�����@���o���J�[�o�X�^�[�e�𓊉����܂����D�w����͍L���Ɍ����𗎂Ƃ��đ����m�푈���I��点���Ɠ����ŁC�K�v�ȑI���������x�ƌ���������ł��D���̌��t�͓��{�ł͕��c�������܂����D
���͂Ƃ����C�C�����Ƃ̊ԂɊj�g�U�h�~��������ł������̂��C�O���̃g�����v�哝�̂��s�\���ł���Ƃ��Ĕp�����C����ɃC�������������ăE�����̔Z�k���n�߂��o�܂�����܂��D�j������C�������̑哝�̃v�[�`�����C�ˑR�E�N���C�i�ɐN�U�������Ɠ��������C�j����������C�������̑哝�̂̃g�����v��������Ƃ������Ƃ́C�v�[�`���ɃE�N���C�i�N�U����߂�Ƃ������i���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ��Ӗ����܂��D
�܂Ƃ�
�������A�Ƃ���2025�N6���ɋN�����傫�ȏo���������グ�܂����D
��������ς���·@���V�A�̃v�[�`���哝�́C�A�����̏K�ߕ���ȁC�B�A�����J�̃g�����v�哝�̗̂�����卑���C�V�l�̖ϑz�ɂ��S���E���Ƃ�ł��Ȃ��댯�ȏ�ԂɊׂ�Ă��鎖�ƁC���̊؍����o�ϔj�]�̊R���Ղ��ɂ���Ȃ���C���������������ŋ��͂����߂Ă��Ă��鎖���Љ�܂����D
7���ȍ~�ǂ̂悤�ȓW�J�ɂȂ�̂�������܂��C���[�}���V���b�N���͂邩�ɒ������s�����S���E���P���\�����ɂ߂đ傫���Ƃ���Ă��܂��D����ɔ����Ă̑��簐i���Ē��������v���܂��D�挎�\���グ���w�l�����炷�ȁI�ɂ����点�I�x�w�Ȑl���ł͂Ȃ����l�����x�����Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��D
�w���Ėf�Ր푈�ƃg���^�̑Ή��x
�ȉ��C�O��Ɉ��������w���Ėf�Ր푈�ƃg���^�̑Ή��x�ɂ��Ă��b�����܂��D
�M�҂�1995�`1996�N��2�N�ԃg���^�̕����Ǘ������̐E�ɂ���܂����D
1995�N�t�C�n�Ă��āCGM�Ƃ̍��ى��NUMMI�����@���܂����D����ƁC����Ă���ƌ����g���^�u�����h��C�Ԃ̊�����Yard�͖��^���ł����D�Ƃ��낪�C����Ă��Ȃ��Ƃ���GM�u�����h��P�Ԃ̊�����Yard�͋�ł����D
����Ă�����̍H��ɂ����Ȃ��C����ĂȂ����̍H��ɂ������Ƃ����̂��펯�ł����CNUMMI �ł́C���ꂪ�����������̂ł��D���n���݈��ɁC���Ԃׂĕ���悤�Ɍ��������C�A�����܂����D
���N��ɒ������ʂ��͂����R�Ƃ��܂����D���e�͈ȉ��̒ʂ�ł��D
�yA�z�č� BIG 3�̐��Y��Order-to-Delivery-Lead-Time
�č���BIG3�́C�T�����Y�E�T�����ς���{�ŁCN�T�̔���s�������āC(N+2)�T�̐��Y�v��𗧂Ă�(N+1)�T�ɕ��i�̎�z�����C(N+2)�T�ɍH��Ő��Y���C(N+3)�T���ɂ͑S�Ăɔz�����Ƃ���Lead-Time�ł����D(���݈��̕ł́C���Ԃ͂����Ǝ��Ԃ��|�����Ă���c�c�Ƃ̂��Ƃł���)
�č��f�[���[�͍ɔ̔������ł�����q���猩��Order-to-Delivery-Lead-Time�́C�ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��D
- �����; �f�[���[��(�f�[���[��)�C�q; ���[
- �l�C��; �e�B�̃Z���^�[��(Maker��)�C�q; ������
Maker�͏T����[ - ������; ���Y(�ɖ���)�C�q; 3�`4�T��
���Ȃ݂Ƀ��[�J�[�̕��i+�ԗ���Lead-Time(���_�l)3�T��
�yB�z���{���[�J�[�������ԗA�o��������Order-to-Delivery-Lead-Time
���{���[�J�[�g���^�E���Y�E�z���_��3�Ђ́C���X��Torrance�ɖ{�Ђ��\���Ă���C������݂��̉�Ђ̊Ŕ��������Ԃł����D3�ЂƂ��C�������Y�E�������ς��̗p���Ă�����{���Y�Ԃ�M�����{�ɓ��{�̐��Y�Ǘ�����(M+1)���̑S���E�����̐��Y�v������߁C���i�̎�z�����܂��D(M+1)���̏\���{�̐��Y���C���őS���E�����̎ԗ��̐��Y���s���C���X�ƗA�o��ʕu���ɉ^��A�o�葱�����ς܂��܂��D
�����̎����ԉ^���D�͏�p�Ԋ��Z��4000��ύڂł��܂������C�Ŋւ��A�o�p�ې�Yard��4,000�䑵�������_�łł����A�o�p���ނ̎����Ă��炦�Ȃ������̂�Lead-Time�̑傫�ȃ��X�ƂȂ��Ă��܂����D
�D�ւ͓��{�o�`����č��`�ł̉חg���܂ŁC���C�݂�2�T�ԁC���C�݂܂�3�T�Ԋ|����܂����D
����Ō����C(M+2)���ɕč��g���`�ɓ����ƂȂ�܂��D
�܂�C���{�Ԃ́C�g���`�ɖc���Motor�v�[���ɂ�����Ă̍ɔ̔��ɂȂ�܂��D
�č��̋q���猩��ΓX���ɔ̔��ł�����COrder-to-Delivery-Lead-Time��
- �����; �f�[���[��(�f�[���[��)�C�q; ���[
- �l�C��; �e�B�̃Z���^�[��(Maker��)�C�q; ������
Maker�͗g���`�ɂ���T����[ - ������; ���Y(�ɖ���)
���{�ɔ�������̂�(M+2)����C�q; 10�`14�T��
���Ȃ݂Ƀ��[�J�[�̕��i + �ԗ���Lead-Time(���_�l)10�T��
�yC�z�����̕č��ł̓��{���[�J�[�@�č����n���Y��
���{�̐��Y�Ǘ����ŁC���{�őS���E���������Ԑ��Y������̂Ɠ����悤��M����(M+1)���p���w���i�A�o�v��x�𗧂āCSupplier�ɓ��X�̌X�̕��i�̔[�i�w�������܂��D
(M+1)���ɂȂ�ƁC�eSupplier����[�i���ꂽ���i���v��Ɋ�Â��ăR���e�i�Ƀo���j���O���ĕč��֗A�o���܂��D���{���Ńo���j���O���Ă���C���n�g���H��Ńf�o���j���O(�J��)����܂ŊC��R���e�i�Ŗ�ꃖ���|����܂�����CM���ɐ��Y�v��𗧂Ă��ԗ��p�̕��i���S���č��̑g���H��ɓ͂��ɂ�(M+2)���ɂȂ��Ă��܂��D
���ǁCM���ɓ��{�̐��Y�Ǘ������v�悵�����Y�v��ŁC���n�č��őS�Ċ����Ԃɂ���ɂ́C���ƁC(M+3)�����ɂȂ��Ă��܂��Ă����̂ł����D
�����č��̋q���猩��C�X���ɔ̔������ł�����
- �����; �f�[���[��(�f�[���[��)�C�q; ���[
- �l�C��; �e�B�̃Z���^�[��(Maker��)�C�q; ������
Maker�e�Z���^�[�ɕ�[ - ������; ���Y(�ɖ���)
���{�ɔ������C�͂������i�Ő�������̂�(M+3)����
�q; 14�`20�T��
���Ȃ݂Ƀ��[�J�[�̕��i + �ԗ���Lead-Time(���_�l)��14�T��
�yD�z�����̃g���^�ƍ����̔��X�Ԃ�Order-to-Delivery-Lead-Time�ɂ���
�g���^�Ɗe�̔��X�̊ԂŔN�Ԃ̎Ԗ��ʔ̔��䐔���_��D(�t�@�[�����x)
�̔��X�́C���q�l�ƎԂ̎d�l�̍ו�(�F�E�^�C���E�I�v�V�������X��20����)���l�߁C�g���^�ɍŏI��������ƁC3���セ�̒ʂ�̎d�l�̎Ԃ����C���E�I�t���܂��D�̔��X�̓t���[���i���o�[�ƎԌɏؖ��������ē��ǂɓ͂��ă��C�Z���X�v���[�g�����炢�܂��D�قړ������ԗ����X���ɓ͂��܂��D�̔��X�͎ԗ����グ�C�ו��̃I�v�V���������t���C�F����ă��C�Z���X�v���[�g�����t���C�[�Ԃ��܂��D�����č��̔��X�Ɠ����l�ɐ��������
- �����; �f�[���[�X���C�q; ���L���ړ]�葱��3����
- �l�C��; �f�[���[���̃Z���^�[�ɁC�q; ��4����
- ������; ���Y�C�g���^���Y3�� + �X���܂ł̗A�� 7��
���Ȃ݂Ƀ��[�J�[�̕��i + �ԗ���Lead-Time(���_�l)1�T��
��: �g���^�̍��������Ԃ͑S�ăf�[���[��
�X�ɁC�ԗ��g�ݗ��čH��Ŏg�����i�́C�ɕ�[�������g��4���ԊԊu�ŃT�v���C���[����[������Ă��܂��D���̌��ʑg�ݗ��čH����̒I�����Y��]���͈���ȉ��ƂȂ��Ă��܂��D
���N��ɕč�������ꂽ���̏�Ԓ������ʂɂ��āC�S�������ł����D
�������ʂ��Ă̕����Ǘ����Ƃ��Ă̔��f
(1) �q�̗���Ō���Order-to-Delivery-Lead-Time�ɂ���
�č��Y�Ԃ����{�Ԃ��A�č��̔̔��������Ȃ킿����ȓX�܂ł̍ɔ̔��̉��ł́AOrder-to-Delivery-Lead-Time�@�X���Ŕ�����菊�L����܂ł̎��Ԃ́A�l�C�Ԃł͌݊p�̐킢���o���Ă���B�q�̂���������ꂽ���ʎd�l�Ԃł́A
�č��Y�ԁG3�`4�T��@���@���{�Y���{�ԁG10�`14�T�@���@�č��Y���{�ԁG14�`20�T
�Ɨ��_�I�ɂ͑卷������܂������A�g���^�̔̔�����̌����ŁA���Ԃ͉��L�̂悤�ȗ��R�Ŕ̔��X�Ƌq�Ƃ̊Ԃł�����wDeal�x������A�����̎��_�ł���ʎd�l�Ԃ̃��[�h�^�C����Z�k����ۑ�͗D�揇�ʂ��Ⴂ�Ƃ̎��ł����B
�̔��X�̓X���ɂƂ����̂́C���[�^���[�[�V�����̐i�č��ł͐F��O���[�h���X�CUser�̍D�݂�����ɂ킽���Ă��܂��̂ŁC�����ȒP�Ƀt�B�b�g������̂ł͂���܂���D�X�傪�I�i�����ł��A���N�Ԕ��ꂸ�ɂ���Ƃ����Ԃ�����ɂ���܂��D���̂��ߔ̔��X�́C�����l�������Ă��X���ɂ���N���}���q��Deal���Ĕ��荞��ł��܂��܂��D
���n�̎��Ԓ�����Lead-Time�Ƃ����̂́A�����܂ł����_�l�ł����āA�X���ɖK�ꂽ�q�Ƀq�b�g�����邽�߂ɁA�̔��X�̓��X�N�`���Ăł��邾�������̍ɂ������c�Ƃ��Ă��܂��B���̎��ԂF����A�����̓��{�Ԃ̔̔��X�͕č��Ԃ̔̔��X�ƌ݊p�ɐ���Ă����Ɣ��f�ł��܂����B
��Ԃ̖��_�́C�s�ꂪ�₦�Ĕ̔��䐔���������Ă������ɁC�ǂ̃^�C�~���O�Ńu���[�L�������邩�Ƃ������Ƃł��D�č����Ő��Y������{�Ԃɂ��ẮC�u���[�L��������̂�3������ł�����C���n�̎��v��100%���n���Y�Ԃŕ₤���Ƃ́C����Ȃ��Ԃ��ʂɕ������ނƂ������X�N������܂��̂ŁC���ʂ͕č����ł̊����Ԑ��Y�͕�8���ڂ�7���ڂŔ[�߂Ă����C�c��͓��{���犮���Ԃ�A�o����Ƃ����������߂Ċm�F���܂����D
�����܂ł͐�����Ђ̎s�ꉞ�����Ƃ����ϓ_�Řb�����Ă��܂������A��������Ƃ��ĉ��P���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�Ƃ��āA�H��̐��Y���C���̏o������A�č��̔��X�܂ł̊����ԍ�(�g���^�̒I�����Y)�������Ɉ��k���邩�ɂ���܂����B
��������b�͘e���Ɉ��܂����A�ʊƖ��̎��Ԃ�m���Ă����������߂ɓ�����������P������Љ�܂��B
�����͕ېŃ��[�h�Ɋ����Ԃ��4,000�䂸�܂Ƃ߂Ēu���A�v�X��D�ւɈ������Ăđ��ǂɗA�o�����Ă��܂����B�����Ԃ��猩�܂��ƁA�������Ă��琔�֑҂��đD�ɏ���Ԃł����B
��ʉݕ��ƈႢ��p�Ԃ́A���ꂼ��t���[���i���o�[�������Ă���A�H��Ń��C�����Ă���D�ɐςނ܂ň�{���ɂȂ��Ă��܂��B���C�����������_�Ŏd���n�����܂��Ă���̂ŁB���̏������ɂ��Ēʊ֎葱��������A�D��ʊ�(�D�ɏ悹�Ă���ʊ֎葱��������)���Ƃ��\�ł���Ƃ��āA���̎肱�̎�œ��ǂɑi���܂����B
���ǂ͂Ȃ��Ȃ�����c�ɐU��܂���ł������A��y�����Ɍ������Ď��͒�N�ސE���܂����B�ސE���Đ��N��A��������O��́w�D��ʊցx�������ꂽ�Ƃ̒ʕ�����܂����B����ŁA�^���D���Ǖ��̍ɂ��팸�o�����̂ł����B
2008�N���[�}���V���b�N������A���E������s���ɂȂ�܂������A�z���_�Ɠ��Y�́A�č��s��ł̔̔������������Ƃ��āA4���ȍ~��ƃg�b�v���猸�Y���߂��o���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�Ƃ��낪�wJust In Time�x��\�ŔƂ���g���^���A���Y�����邱�ƂȂ��Ƀ��[�}���V���b�N�ɓ˂����݂܂����B���̌��ʖc��ȍɂ�����Ă��܂��A���̏����̂��߂ɐ��N�ԁA�Ԏ��������܂����B
���ψ�̒���q�Ƃ��Ē��x�m�v�A�r���_��A�ѓ씪��3�����w�g���^���Y�����x�́w�Z�āx�ƌ����n�ʂɂ��������̏o�����ł����B
�w�g���^�V���b�N�x���@�ɁA�L�c�Ƃ̌䑂�i �L�c�͒j���В��ɒ��C���܂����B
�ނ́w�g���^���Y�����̌��_���A�x���X���[�K���ɁA�Г������v���A�����Ɏ���̂ł����B���̕ӂ̏ڍׂ͕ʓr�wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�R�����ŏЉ�����܂��B
(2) �g���^��Supplier�̊W
���Ă̖f�Ֆ��C�̉����̂��߂ɂ́w���i�������܂ł��č����Ő��Y����I�x�Ƃ������ƂɂȂ�܂��D�����œ��{��Ƃ̃J�[���[�J�[�ƃT�v���C���[�Ƃ̊W�����ĂƂ͈���Ă��邱�Ƃ��Ċm�F����K�v������܂��D
�ȑO�Ƀh�C�c�ł́C�Z�p���傪�ԗ��̊��S�Ȃ�v�}�����������C���Y�Z�p����͐v�}�ʂ�̎ԗ��Y����v���������B��������͂��̐v�}�ǂ���̎ԗ�������ƌ������S���ƂɂȂ��Ă���b�����܂����D
���̊��S���Ƃ��o���Ă���C���i�̕i���͐v�}�ł�������ۏ���Ă���C���Ƃ͉��i���ň����Ƃ���ɔ�������悢�Ƃ����l���ɂȂ�܂��D
����́C���Ă̎����Ԃ͐������ƂɂȂ��Ă���C���E�e�n�̃T�v���C���[����R�X�g�ŗD��ŕ��i���W�ߊ����Ԃɂ��������Ă���܂��D
�č��̃r�b�O�X���[�����̖@���ɏ]���Ă���C�P���̈�������ɑ����̍\�����i���C�O���[�J�[����w�����Ă���̂ł��D
����ɑ��ăg���^�͑S���قȂ����l���������Ă���܂��D
�g�D�̕ǂ���蕥���C�R���J�����g�G���W�j�A�����O�Ƃ����l�����ŁC�J���i�K���琶�Y�Z�p������ꂳ��ɂ͕��i���[�J�[�����荞�݁C�Ⴆ�f�U�C�������߂��w�b�h�����v�̌`��̒��ŁC�����v�̔M���ǂ��������C�ׂ荇�����i�Ƃ̌��h�����ǂ����コ���邩�D�W����ԗ����[�J�[�C���i���[�J�[���������s�ɐv�������߁C�����ɂ��ꂼ��̐������ꂪ���荞�݁C��q�l�Ɉ������ԂÂ����ڎw���ĂƂ��Ƃ荇�킹�����Ă���킯�ł��D
�}�ʂɂ����Ȃ��m�E�n�E�ōו�����茈�߂Ă���̂ł��D
�������������Őv���Ă���̂ŁC�ꏏ�ɊJ���������ԈȊO�ɕ��i������Ƃ������z�͕�����ł��܂���D
��ɏq�ׂ�1995�N�̍��́C�g���^�n�̃T�v���C���[���܂��[���k�Ăɐi�o���Ă��Ȃ���������ł������C���̌�ɁC�ȑO�q�ׂ��悤�ɁC�č����{�̈��͂Ŗ������č��̃T�v���C���[���畔�i��A���������邱�ƂɂȂ�܂����D�s�Ǘ��������č��̃T�v���C���[���畨�����炢��������C���{�ł��t���������Ă�����Ƃ��Ƃ̃T�v���C���[�ɕč��ɐi�o���Ă��������C���n�Ő��Y���邱�Ƃɂ��āyD�z�ŏ������悤�ȁC���{�����̃T�v���C�`�F�[���Ɠ������̖k�Ăɍ��̂��x�X�g�ł���ƒN�����l����悤�ɂȂ�܂����D
2011�N�̓����{��k�Ђ́C���{����̕��i���͂����A2011�N4���`6���Ɋ|���Đ��Y�ʂ��������ƌ����܂��B���{�Ők�Ђ�����C�k�Ăł����Y���ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂͂܂����ƒN�����v���ł��傤�D�g���^�����{��3�������C�ǂ��ő�ЊQ���������Ă��ł����2/3�Œ��1/3�̐��Y�ʂ͊m�ۂł���悤�ɂ��܂������C����͊C�O�ł��������ƂŁC���[���b�p�C�����C����A�W�A�C�k�Ă͒P�ƂŎԗ����Y���ł���悤�ȑ̐����������ɑǂ�����̂ł����D
���������Ԑ��Y�̏h���Ƃ��ĐV�Ԕ������̃s�[�N��100�Ƃ���ƁC���f�������ɂ�20�`30�܂ŗ����Ă��܂��܂��D����䂦����Ԃł͎s��̔̔�����70����80%�ʼnғ������Ă����C����ɑ��邻�ꂼ��̒n��ɂ�����v���X�E�}�C�i�X�́C���{���Ƃ��C�e�n��̏�p�Ԃ����������邱�Ƃɂ��C�H��̉ғ������ێ����C�ٗp�̈��艻��}�鐭����Ƃ��Ă��܂��D
�g�����v�ł̃j���[�X�ŁC���n�����ԃ��[�J�[�̌��n�H��̐��Y�䗦���s���70�`80%�Ƃ������̂́C���Y�ʂ����肳���v���̈ٓ����Ȃ������߂̕���ł������̂ł��D
�b���_���_���ƒ����Ȃ��Ă��܂��܂������C���E�̂ǂ��Ő푈���ЊQ���N���Ă��S�̂��~�߂��ɍςނ悤�ɁC�n�敪�U�^�̐��Y�̐�����{�̃��[�J�[�͂Ƃ��Ă��܂����D
����䂦�C������25%�̒lj��ŁD�����ԕ��i�ɂ�25%�̒lj��ł��ۂ����Ƃ��Ă��C���{���[�J�[�͖k�Ăɂ������v�Ԏ�̐��Y�͖k�Ă����Řd����悤�ɂ��Ă���̂ŁC���鐶�Y�䐔�܂ł͑S���g�����v�ł̉e���Ȃ��ɐ��Y�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��D
���Ƀg���^�͏͒j��̉��ő̐�������i�߂Ă��܂������C�č������K�\��������C�ɂ���悤�Ȑ��̒��ɂȂ��Ă��܂�����C�D�G�ȃn�C�u���b�h�Ԃ����g���^�ƃz���_����є����ėL���ȏɒu�����Ǝv���Ă��܂��D
�ǎҏ��������S���Č�����Ă��Ă��������D
�܂�����G�߂̈��A�������Ȃ�߂��܂����̂ŁC�wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�͍��������x�݂����Ă��������܂��D
2025�N6��30��
(��)J�R�X�g������ ��\ �c�����m
2025�N5��
���� �G�߂̂����A
�䂪�Ƃ̔L�̊z�قǂ̉䂪�Ƃ̔��ɁC�A�x�O�ɐA�����g�}�g�͊��ɕG�̍����ɂȂ�C���N�͘e��̊Ǘ������āC�����y���ނ���ł��D�U�����̊X�H���̍��͐V�ɔR���C�f���炵���i�F�ł��D
���{�͉��₩�ȏ��Ă��}���Ă��܂����C�F���܂͔@���䊈��ł��傤���D
���E�ɖڂ����܂��ƁC�ׂ̊؍��ł́C�O�����ō��������s���Y�o�u�����e���n�߁C���ʂƂ��āC�ƒ�����}�c�����C���̒��ŗ���̃T���X���̔��㌸����������s���ȋC�z�Ƃ����������́C�c��ȕs���Y�o�u�����e�������C�������ˊ�Ɠ|�Y�ˎ��ˏ������̕��̃X�p�C���������n�߂��Ƃ����
���̒�����ɉ��v�J������ł�������Ɩׂ��Ă����h�C�c���C�����̕s���Ń_���[�W���C�X�ɁC�����Ԃ�EV���Ŋ��H�����������͂����C��荂���\��EV������������o��������BYD�Ɍ������C�傫�ȃ_���[�W���Ă��܂��D
�����ĕč��C������ƂƂ̖Ȗ��ȑł����킹�����Ȃ��܂܂ɍ��z�ȗA���ł�錾�������̂ł�����C���E���҂ɂ����Ċ������Ă������̕č���Ƃ��T�v���C�`�F�[���̕��f�Ƃ����傫�ȑ㏞�����ƂɂȂ�CGM�CFord�Ȃǂ̏�p�ԃ��[�J�[�݂̂Ȃ炸�g���b�N���[�J�[�܂ł��H��̊C�O�ړ]�����f����Ɏ���܂����D����ɍL����CAmazon��C�č��̖h�q�Y�ƒS��Boeing�܂ł��C�H����C�O�Ɉڂ��Ƃ����b�܂ł������オ��܂����D
���ꂩ���g�����v�哝�̂��ǂ���������邩�킩��܂��C���ƊE�����ۂɓ����n�߂Ă��܂��܂�������C�傫�ȏ��Ղ��c�����ƂƎv���܂��D
�]�_�Ƃɂ���Ă̓��[�}���V���b�N�ȏ�̏Ռ����S���E�ɑ���ƌ����Ă��܂��D���ɕč��̎�v��Ƃ͐l���̉��ق��n�߂܂����D
�}���ɋƐт��������������Y�́C�S���E��2���l�K�͂̐l�����������ė��Ē�����}��Ƃ������Ƃ\���܂����D�p�i�\�j�b�N��1���l�K�͂̐l�����������C�Ɛт̗��Ē�����}��ƌ��\���Ă���܂��D�����̓g�����v�ېłɂ�鈫�e���ɔ����Ă̓����ł���ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��D
�M�Ђ͂ǂ̂悤�ȑΉ����Ȃ���̂ł��傤���H
[1] ���Ђ������߂̑��w�l�����炷�ȁI�ɂ����点�I�x�̉��
�s���ɍ����|���������C���Ђ��w�{���g���^�����x�ł��w�l�����炷�ȁI�ɂ����点�I�x��簐i���邱�Ƃ����E�߂��Ă���܂��D
�����\���グ�܂��ƁC2020�N����n�܂����R���i�Ђ̔��㌸��ɂ͈ȉ��̓�ʂ�̑Ή��݂�܂����D
�yA�z�����̊�Ƃ��w�l�������x���s���C���㌸�������z���Ă��܂����D
�yB�z�ꕔ�̊�Ƃ��w�l�������x�͍s�킸�C�d�������̏k���ŏ��z���܂����D
�R���i���߂������āC�s�ꂪ�����Ԃ��Ă����Ƃ��C
- �yB�z�̎Ј�������������Ƃ͑����Y�Ɉڂ�C�Ɛт��}�c�������܂����D
- �yA�z�́w�l�������x��������Ƃ́C��W���Ă��l��͏W�܂炸�C�Ɛщ��v���悤�ɍs���ĂȂ����
�ƕ����Ă��܂��D�܂�yB�z���w��@�x���w�@��x�ɕς����Ƃ������܂��D�ǂ�ȕ�������C�yB�z�̓���H���̂��C�l���Ă݂܂��傤�D
[1-1] �Œ��ƕϓ�����l������
�ȉ��ɂ��b���鎖�́C�M�҂����Ђ�����(1967�N)�l�����ɂ�������Ћ���C��Ǝ��K�ɍs������̊Ǘ��҂͂������̂��ƁC���K�ł����b�ɂȂ�������̊ē҂���ĎO�Ďl����ꑱ�������Ƃł��D
�����1950�N�����̃g���^���C�I���̒��C���t���ƁC��������߂邽�߂̒��f�t������(�h�b�W���C��)�ɂ���āC�o����͍����������������J��ɋl�܂�C��s�̒lj��Z�����Ȃ���Γ|�Y����Ƃ�����@�Ɋׂ������ƁD
���̎��̎В��́C�L�c���g�̒��j�ŁC�g���^�����Ԃ����グ��沓c���Y���������D�ނ��w�L�c�v�j�x�ɂ����w��C����F���̐��_�����C�ƒ�I�������싻���ׂ��x���|�ɂƂ��āC�f�Ől���팸�ɂ͔��������D
��s�c�Ƃ̌�������C�ŏI�I�ɂ́C�悸�n�Ǝ҂̊��Y�В������ӎ��C���C���̌�C�Ј��̐l���������s�����Ƃʼn����������ł����D
�����āC���ꂪ�w�l����������O�ɁC�В������ӎ��C������x�ƌ����g���^�̕s�������ł������Ƃł����D
��Ǝ��K���̋x�e���ԂɁC����̑g�����ׂɍ���w���͑�w�o������C�o�����Ă��炢����ɂȂ邾�낤�D�����炱�ꂾ���͊o���Ă����ė~�����D���Ԃ̎���悤�ȉ�Ђɂ���ȁc�x�Ƙb���Ă���܂����D
1950�N�̊�@�̂��Ƃ��p�����Γc�ގO�В��ȉ�����̖��[�܂ŁC�w�l�������x�������ɍςމ�Ђɂ���ɂ́C�ǂ�����Ηǂ��̂��l���C�H�v�����C���H���Ă����̂��w�g���^���Y�����x�������̂ł��D
�ڂ����b�͕ʓr�wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�V���[�Y�ł��`���������܂����C���̒����s���ɂȂ莩�Ђ̐��i������Ȃ��Ȃ������C����͂ǂ̂悤�ɂ��đς��E�сC�͂�~���Ă����C�D���ɂȂ����Ƃ�����������Đ����ɂȂ��邩����ɂ��Ă����ł͂������������܂��D
1-1-1. �w�������p��x�͖{���ɌŒ�
��v�w�ł́C�w�������p��͌Œ��ł���C�J����͕ϓ���x�ł���Ƌ����܂��D
����Ɉق��������̂��C�g���^���Y�����ŗL�������ψ��ł����D
�Ⴆ�C�v���X�^���������p���l���Ă݂܂��傤�D�����u���Ă��邾���Ȃ疀�Ղ��܂��C���Y�����1���艽���������Ղ��C������g���Ύg���Ȃ��Ȃ�̂ŁC�ǂ��l���Ă��v���X�^���������p���͕ϓ���̂͂����ƌ������̂ł��D
����]�ƈ��́C��Ђɏo�Ă��Ďd�������Ă��Ă��C�d�����Ȃ��Ă����͌���D�����Ă������߂ɂ������H��˂Ȃ�Ȃ��D������J����͌Œ��̃n�Y���I�Ǝ咣�����̂ł����D
�l�b�g�Œ��ׂ�ƁC�Ɖ��Ȃǂ̌������p��͌Œ��ƌ��߂��Ă��܂����C�v���X�^�̂悤�ɁC�g���Ŗ��Ղ��Ă����@�ނ̌������p��́C�����̐Ŗ������̔��f�Ō��߂���Ƃ���܂����D
�o�ς̐��Ƃ����́C���N�̌㔼����g�����v�ʼne���ŁC���[�}���V���b�N�ȏ�̑�s�������Ă����������Ȃ��ƌx���炵�Ă��܂��D���Y���ɔ����āC�Œ������炵�w���v����_�x�������Ă����K�v������܂��D
1-1-2. �Ȑl���Ə��l��
10�l��1���ԓ�����60���Y���Ă������C���ɁC�����@������9�l�łł���悤�ɂ����Ƃ��܂��D
�y���P�O�z
10�l���; 60��/h (����) �̑g�ݗ��ă��C��
�y�Ȑl�����P��z
�D�H���Ɋ��S�����@�����C9�l��Ƃ�60��/h��B���ł����Ƃ��܂��D
���̂悤�ɍ�Ƃ������@�̒u�������l������炷�̂��Ȑl���Ə̂��đ����̊�Ƃł͖������ɐi�߂Ă��܂����C�����ɂ͑傫�ȗ��Ƃ���������܂��D
���Y��flexibility�������邱�ƂŁC���Y���͕Ԃ��Đ��Y�����������̂ł��D
���ۂɔ���Ȃ��Ȃ��Ď��ԓ�����̐��Y�䐔�����������ꍇ���v�Z���܂��傤�D
- �O�H�� 60��4�l�C45��3�l�C30��2�l�C�c�c
- ��H�� 60��5�l�C48��4�l�C36��3�l�C�c�c
�ƂȂ��Ă��܂��܂��D
�y���l�� ���P�z
�g���^���Y�����ł́C�w���l���x�Ƃ������P�������߂��܂��D����͎s��̕ω��ɒǏ]���čs���ׂɁC��ɐ��Y���ɔ�Ⴕ���v�����ʼn^�c�ł���悤�ɉ��P�������Ƃ��Ӗ����܂��Dflexibility�ł��D�ݔ��̐�����Ȃ����C��ƈ��𑽋Z�\�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���D
�w���l���x���ꂽ���C���ł́C���̗�Ō����C
- 60��10�l�C54��9�l�C48��8�l�C42��7�l�C�c�c
�ƂȂ�܂��D���̂悤��10%�̌��Y�ŁC�Ȑl���Ɋ|������p�͖��ʂɂȂ�C����Ɍ��Y���i�߂C�����@���l�b�N�ƂȂ������l�����ł����t�ɐ��Y���𗎂Ƃ����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��D�g���^���Y�����ł́C�w�Ȑl���x�̊��S�������H���̓��C���̗��[�ɐݒu���C���C���̓r���͊ȈՓI�Ȏ����@ (����̉���)�ɂ��āw���l���x�Ɨ���������H�v�����܂��D
[1-2] �������C�ǂ̏��Ԃō팸���邩�����߂Ă���
�w�{���g���^�����x�ł́C����w�ړI�͉����x��₢�����đO�i�����܂��D
��Ќo�c�̖ړI�́C�w�����Љ�ł͊��傩��a������������L���I�Ɏg�����v�������炵����ɊҌ�����c�D�x�ƍl���܂��D
�w�{���g���^�����x�ł́C���{���o�c��Essence�w3���悵 (�����悵�E������悵�E���ԗǂ�)�x���x�[�X�ɂ��āC�w�ւ�����l�ԏW�c�̖������ɉh�x�����̖ړI�ɂȂ�܂��D����Going Concern�Ȃ̂ł��D���ƂɗႦ��C�����̔ɉh�ł��D
��Ƃ��l���팸���Đ����������ƌ����̂́C���ƂŌ���C�����Ô���팸����Ȃǂ́C�ꕔ�̍������]���ɂ��Đ������т鎖�Ɠ����ƍl���܂��D�Ō�̎�i�ŁC�g���^�ł�1950�N�����J�肪�������ē|�Y�Ɋ�@�Ɋׂ������C�n�Ƃ̎В����悸���ӎ��C���āC���̌�C��2���̐l���팸�����{�����𐁂��Ԃ��܂����D�ȗ��C�l���팸�͎В��̎�ƈ��������ɂ��郂�m�Ƃ����s�����������Ă��܂��D
1-2-1. �g���^���Y�����ɉ����錸�Y���̑Ή�����
�g���^���Y�����̌�����
- �����x�o���팸���邽�߂ɁC�܂��d��������炷
- �w��E��߂�x���P�ō�ƍH����ύX�����P�v����P�o
- �H�����ɁE�����i�ɂ����炵�C�d����ʂ��X�Ɍ��炷
- �]��l�������C������O���C�i�ւ��Ɖ^���̑��p�x��
- �]��l�����g���ė]��ݔ��̓_���C���E�����ƕۑS�Z�\�̌P��
- �X�ɗ]�����H���ŁC�ɖZ���ɂł��Ȃ���������P�����{
�̏����Ō���̃X��������}���Ă����܂��D
1-2-2. ���Y���̑Ή����\�ɂ���̐�����
���݂قƂ�ǂ̉�Ђł́C�H����̊e�H���Ő��Y����i�ڂƂ��̐��ʂ́C�������ɂ���R���s���[�^�[���g���Čv�Z����C����Ɏw������̂����ʂł��D�����PUSH�^�ƌ����܂��D
�g���^���Y�����ł́C�S�Ă̍H���ɍɂ��������Ă����āC��H���Ɉ����ꂽ�ʂ��������̓��̓��Ɍ��[���Y����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��D������Y�̂��߂̌��ޗ��͑O�H���Ɏ��ɍs���킯�ł��D�����PULL�^�ƌ����܂��D
(1) �w���i�̔[���w����PULL�^ (�Ɍ��[�^)�ɕύX����
���ƒ�Œ������a�����Ă���l�����́C�Ƃɂ���ɂ̒��ŗ������l���č��܂��D�ɗʂƂ��ĕs�����������o���ɍs����[���Ă����܂��D����䂦�ɓ���͍ɗʂ̒��ʼnƑ��̖]�ޗ������ł���̂ł��D
�Ƃ��낪�����̉�Ђł́C��c�Ō��߂�ꂽ���������Y�v�悩��C�wMRP�x�Ɋ�Â����K�v�ʂ��v�Z���C�����Ŕ�������܂��D �������C�����̕K�v�ʂ�����ɓ������āC�������ɁC���Y�i�Ԗ��̎c�ʂ��ǂꂾ�����邩�s���ł��̂ŁC����c�ʃ[���Ƃ��ĕK�v�ʂ��v�Z���܂��D
����ɁC�d����ʂ��s������Ɛ��Y���ł��Ȃ��Ȃ�܂����C����ȏ�Ԃł��C�ݔ��̍쓮�m�F�p�C�j���p���ɗ]���ɔ[��������K�v������܂��D����ȊO�ɕs�Ǖi���݁C���H�s�ǎ��̒lj����Y���Ɏg���鐔�ʂ�\�����ĉ�����K�v������܂��D�X�ɁC�ŏ��[���P�ʂƂ����_����C1,000�P�ʂ�������C20kg�P�ʂ������肵�܂��D�K�v�ʂ�103kg�ł��C20kg�܂��[������P�ʂō݂�C�[���ʂ�120kg�ƂȂ�܂��D
���̂悤�ɂ��āCPUSH���Y�C�����v�搶�Y�Ɋ�Â����� (MRP)�͕K�v�ʂ���ɑ��߂ɔ������鐫��������܂��DPUSH�^�ł�����薈���ɂ͑����Ă����܂��D
���PULL�^ (�Ɍ��[����)�ł́C��Ђ̒��B�i�̍ɗʂ́C���ƒ�̗①�ɂ̊Ǘ��Ɠ����ŁC�g���Č�������������[����̂ŁC�ő�ɗʂ͑����čs���܂���D
�wKanban�����x���̗p����C�ɗʂ͏�ɔ��s���Ă���wkanban�̖����x�ȉ��ɂȂ�܂��D�����āC�wKanban�x�̖��������点�C��Supplier�̊����i�q�ɂƁC���Ђ̃��C�����܂ł̍ɗʂ�i�ԕʂɌ��炷�����e�Ղɂł��܂��D
(2) �H����̊e�H���̐��Y�Ǘ���PULL�^ (Kanban����)�ɕύX
���ۂ̍H��ł͉��\�J���̐����H��������C���ꂪ�T�v���C�`�F�[���Ƃ���?�����Ă��āC���X���X�v�X�̐����H���ɁC�w�����ǂꂾ���C�ǂ̃^�C�~���O�ō��I�x�Ǝw������̂́C�s�\�ɋ߂����Ƃł��D
�������������ɂ́wKanban�����x�̓�����������܂���D
���Ƃ��Ă���ŁC�w�b�x�Ƃ����H�������w���x�̍H���ցCA�CB�CC��3��ނ̒��Ԑ��i���������Ă����Ƃ��܂��D�uA�v�C�uB�v�C�uC�v��3��ނ̘A�Ԃ�t�����w�d�|����Kanban�x���������C�ʂ����Ɏ��t���ăX�^�[�g���܂��D
��H���́uA�v�C�uB�v�C�uC�v��3��ނ̘A�Ԃ�t�����w����Kanban�x���������܂��D��H��������ɗ���p�x�́C���Ԋu��10��/�����ǂ��Ƃ���Ă��܂��D��H���́C���Y�ɂ���Ďg�������i�́w����Kanban�x�������đO�H���Ɏ��ɍs���C�O�H���̍ɂɊ|���Ă���w�d�|Kanban�x���O���āwKanban����x�ɓ���C����Kanban�ɕt���ւ��Ď����A��܂��D
�O�H���w�b�x�́C�O��Ă����w�d�|Kanban�x���Y���āC���́w�d�|Kanban�x�t���ĕ�[���Ă����܂��D
�����ő�Ȃ��Ƃ́C�S�Ă̍H���̍ޗ��u����ɂ͕i�Ԗ��Ɂw����Kanban�x�����Ă���C�����i�u����ɂ͕i�Ԗ��́w�d�|Kanban�x�����Ă���C�H��̒��ɂ͈�wKanban�x�̂��ĂȂ��ʂ�������̕��i�͖����Ƃ������Ƃł��D
�H����̑S�H���Ԃ����̂悤�ɁwKanban�����x�Ōq�����ɂ���āC�����wKanban�x�̖����������鎖�ōH���Ԃ̍ɗʂ����݂ɑ����ł���悤�ɂȂ�܂��D
����ɍɂ����炷���߂ɂ́C�ʂ����̒��̎��e�������炵�čs���܂��D�g���^�ɂ́w1��Kanban�x�Ƃ������t������܂��D�w1�����x�Ƃ������t������܂��D
���ɂ̍ɒጸ�́C��Ǝ҂��C1�̍ޗ��������čH�������C�d�グ�Ă������ŒB������܂��D
�ʐ^�͏���MR2�ł��DMidship-Engine, Rear-Drive, 2Sheater �̗��ŁC���{�ŏ��߂Ẵ~�b�h�V�b�v�G���W���Ԃł����D�M�S�Ȉ��D�Ƃ��������߁C���̐��\��ł��̔����Ă��܂����D���ʂ̎����ԉ�Ђł́C�ʎY���Ă����āC�ɂ��������Ĕ̔�����̂ł����C������S�����Ă����Z���g���������Ԃ́C�n�ڍH���ł͈��1�`2��̃{�f�[���C1�����v���X�i���^�тȂ���n�ڎ��������Ďd�グ�Ă����܂����D�����C�w���l���x�̃��f���H���Ƃ��āC�����S������Z�p�҂Ƃ��Č��w�����Ă��炢�܂����D

(3) ��E��߂���P
��Ɂw���l���x�̐����Ő��Y���ɔ�Ⴕ�č�ƎҐ������炷�Ɛ������܂����������ɂ��w�g���^���Y�����x�Ƃ��Ă̍H�v������܂��D
- 60��10�l�C54��9�l�C48��8�l�C42��7�l�C�c�c
���Y�ʂ�45��/h��������ǂ�����̂ł��傤���H
�����̐��Y��������50�� (TACT-Time=60��/50��=72�b)�������Ƃ���ǂ̂悤�ȑ̐��Ő��Y����悢�ł��傤���D�v�Z������C54����49�܂ł�9�l�Ő��Y���\�ł��D�����̉�Ђł́C9�l�̍�ƈ��ɁC��Ƃ��ϓ��Ɋ���U��Ǝv���܂��D
�����ɑ傫�ȗ��Ƃ���������܂��D�ꎞ�Ԃ�50�ł����1������72�b�D�܂�C72�b�Ɉ�̊����ō������Ƃ������ƂɂȂ�܂��D������̑���Ǝ��Ԃ͈ꎞ�Ԃ�60��10�l�ō���Ă��܂����̂ŁC1��10[���E�l]�ō��鎖�ɂȂ�܂��D9�l�Ȃ�67�b��1�����͂��������킯�ł��D
67�b��1�ł�����͂�������������C72�b��1���̐��ɂ��Ēu������C�^���I��Ȃ璼������Ǝv���܂����C���̌���́C72�b��1�����ł��Ȃ��l�ɗ��čs���Ă��܂��܂��D��Ƒ��������łȂ��C����S��e�C�������Ȃ��Ă��܂��̂ł��D
�g���^���Y�����ł́C�����h�����߂��w��E��߂���P�x���s���܂��D�N�����p�\�R���Q�[���ɖ����ɂȂ�܂����C����͊�O�̉ۑ�������ɑ������܂��Ώ��ł��邩���������Ă��邩�炾�ƌ����܂��D���킵�Ă��邩��C���܂��s���Ȃ��Ɖ������Ǝv�����C���܂����������Ƃ��܂��ł��Ȃ������v���C���Ԃ̌o�̂��Y��Ă������Ƃł��傤�D
�����Ƃ������ł��D�����̍�Ƃ̑����ɒ��킵�Ă��邩��C���܂�����������������C���܂������Ȃ�������������̂ŁC�Ȃ����낤�ƍl����D�����Ă܂����킷��D���Ԃƈꏏ�ɂ��ꍇ�́C�ǂ��炪�����I���̂��������������Ƃɂ���āC�y���݂��o�Ă��܂��D�����ċ��ɒ��킷�邱�Ƃɂ���āC�����ʔ����ƃv���C�h�������Ă��܂��D�����Đ��Y�����オ��C���������̉�Ђ̊�Ղ������Ȃ��Ă��܂��D
�`Keyword�̓X�g���b�`�ڕW�`
�����B�̖������킷��ڕW�Ƃ��āC����܂ł̎��͂ɑ��Đ��p�[�Z���g���X�g���b�`�ڕW���f���鎖�ɂ��܂��D���̗�Ō����CTACT-Time��72�b�ł�����C60����Ă����Ƃ��ɍ�Ǝ��ԂŁC�擪����2�b�̃X�g���b�`�ڕW��^���āC74�b�����v�f��Ƃ�����U���Ă����܂��D
��������ƁC���̂悤�ɂȂ�܂��D
8�l�̃X�g���b�`�ڕW�ɒ��킷���ƈ��ƁC��ƒx��������[�t����1�l�̍�ƈ��ƌ����̐����ł��܂��D
�������邱�Ƃɂ���āC���Y�ɂ�鐶�Y���̕ύX�����Ă��C�e��ƈ��͎��͂𗎂Ƃ����ƂȂ���ɃX�g���b�`�ڕW�ɒ��킵�C�����������邱�Ƃ��ł���̂ł��D
���̂��Ƃ��w��E��߂���P�x�ƌ����܂��D
����ɂ���ĕ������H���́C�^���p�x���コ���邽�߂Ɏg���C�H�����̑ؗ��ɂ����炵�܂��D
�Ȃ������w��E��߂���P�x�́C�g�傷��ΐ����H���ɂ��K�p�ł��܂��D
��͑g�����C������C���͍H��@�B�܂ŁC���ɒ��킷�郉�C���ƁC�x���ɒ��킷�郉�C�������C�v���E�ݔ������C���̔��ɔ�����̂ł��D
�w�l�����炷�ȁI�ɂ����点�I�x�̈Ӗ���
1987�N�C�g���^�������ԂY���邱�ƂɂȂ�C�c���H�ꂪ�����S�����邱�ƂɂȂ�܂����D�����ŁC�H�꒷�E�H�������E�����������E���������� (�M��)���C�{��h�C�c�s���Ă��̐�����������@���邱�ƂɂȂ�܂����DVW�CAudi�CBMW�CBenz���̎ԗ��H�����̂ɁC��������ƌ��w���C�H��W�҂Ɗ��݂Ȃ��ӌ����������Ă��܂����D
�]�k�ɂȂ�܂����C�h�C�c�͔��ɍ�����`�̍��ŁCBenz��VW�́C���{�i�o�ɓ������āC���{�̐l���̏d�S�ɋ߂����Ƃ���C�L���s�ɗg���`��Motor Pool��ݒu���C�����ōĐ��������ē��{�e�n�̔̔��X�ɉ����Ă���܂����D
���ɁC���̃h�A��t�[�h�̌��t���́C�S���Ē������Ȃ��ƍ����ԂƂ��Ĕ���Ȃ��Ƃ������ƂŁC�g���^�̓c���H��̎蒼���v���������ň�����������čs�����Ƃ���Ă��܂��D���{�����ł��ߏ��t�����������Ă������ł��������̂ł��D
1980�N��́C�h�C�c�͖�S�N�̗��j���ւ�C�g���^��50�N�ڂ̐V�Q�҂ł�������C���y�Ƃ��Ďᑢ�ɋ�����悤�ȋ�ŁC�H��̋��X�܂Ō����Ă���āC���ł��ӌ��������ł��܂����D�ڂ����b�͂܂��̋@��ɏ���Ƃ��āC�����̃h�C�c�̎����ԍH�Ƃ̈�ʂ��Љ�����܂��D
�����̃h�C�c�̑�w�i�w���͐�%�� (���݂�30%?)�C�i�w���邽�߂ɂ́C���{�Ō����Ώ��w�N�����獂�Z3�N�܂ł̐i�w�Z�w�M���i�W�E���x�ɓ���܂��D
���N�Ԃ̎Љ� (�܂ޕ���)�o�����o����C����̏����������߂đ�w�̐��ے��ɓ��w (���w�͈Ղ������w�ʘ_���͓��)���܂��B���̐���ɓ��Ђ���Ɓw�J���x��w�o�c�E�Ǘ��x�̐��E�Ƃ��ē����܂��D
��w�i�w���Ȃ��l�́C�v�X�̐E�Ɗw�Z�ɓ��w���C��ɐE��t���܂��D�E�Ɗw�Z�𑲋Ƃ���ƁC���Ǝ��i����ɓ��ꂽ�E�l (�Q�[�[��)�ɂȂ�܂��D�����ɓ��Ƒg���ɉ������܂��D�������܂��Ƒg���̋K��ɂ���ăh�C�c�����ɂ�����W�������ȏ�̋��z�ŏA�E���ł��܂��D
�A�E���܂��Ɓw����J����������x�̌����ŁC�Α��N���ɂ͊W�Ȃ��C�قڈ��̒����ɂȂ�܂��D�ڗ��������т�������ƁC�����͏グ��ƌ����܂��D
��ƈ��̏�ɌN�Ղ���̂́w�}�C�X�^�[�x�ł��D
Benz�̃V���c�b�c�K���c�H��ŁC����}�C�X�^�[�̃I�t�B�X�����w���܂����D�����ɂ͒S������H���̍�ƈ��̑S���낪�\��o����Ă���C�Αӏ��ڂ����L������܂����DA�N�͐��їD�G�ł���DB�N�͕s�ǂ���o���Ă���D����1��s�ǂ������N�r�ɂ��饥�������Ă���܂����D
�s�ǂ̌����Njy��C��Ǝw���C�����̈琬���̘b�͏o���D���s������Ǝ҂�r�����ē���ւ���c�c�ƌ����w�}�C�X�^�[�x�̎p���ɁC�����܂����D
����C����N�r�ɂȂ��Ă��C�h�C�c�̎����ԉ�Ђ̏]�ƈ��͋��͂ȘJ���g���wIG Metal (�C�[�Q�[�E���^��; �����Y�ƘJ���g��)�x�ɉ������Ă���C�ċ���E�C�ďA�E�͗e�Ղł���ƌ����܂��D���̋C����������ɏA�E���ł���d�g�݂ɂȂ��Ă���ƕ����܂����D
����ɋ����ׂ��J���s��̎��Ԃ�m��܂����D�����Ԃ̑g���H�́C�g���̔F�߂��W����Ǝ��ԂɊ�Â��č�Ɨʂ����߂��C��{�ƂȂ鋋�^�����߂��Ă���Ƃ������Ƃł��D���̍�ƂƂ����̂͋����ׂ����ƂɁC�X�p�i��h���C�o�[���g���Ď�Œ��ߕt���鎞�Ԃ��ȂĕW����Ǝ��Ԃƌ��߂��Ă��܂����D
���ۂ̐E��ł��̂Ƃ���ɍ�Ǝ��Ԃ�����U���Ă��邩�ǂ����C���Ǝ�g���̒����������Č��Ď���C�K���葽���̍�Ƃ�����U���Ă���Ƃ��́C��Б��Ɍ��d�ɍR�c������c�c�d�g�݂ƂȂ��Ă���܂����D
���̌��ʁC�����̃x���c�̈�ԗ����ł̃��f��A�̑g����Ǝ��Ԃ͖�20���Ԃƕ�������C�g���^�̃N���E������5���ԂƂ����ƁC�g���̕ǂłǂ����悤���Ȃ��Ǝc�O�����Ă��܂����D�����C��l��l�̍�Ɨʂ����{��1/4�����������ƂŁC���S�����������Ղ��̂���蕿���Ƃ������Ă��܂����D
�����ꌾ�x���c�̘A���͔��_���܂����D��������H���̓g���^�ɂ͕����Ă��邯��ǁC�̔����邽�߂̍H���̓g���^�����͂邩�ɏ��Ȃ��Ɓc�c�D
�����̃x���c�͑�ςȐl�C�ŁC���������č��l�̓x���c����̒m�点���Ă킴�킴�V���c�b�c�K���c�܂ŎԂ����ɏo�����C�Q�X�g�n�E�X�Ń��C��������ł���ƁC���Ȃ��̃N���}���Ԃ��Ȃ����C���E�I�t���܂��Ƃ����ē������āC�Q�ϒʘH�Ō����H����ʉ߂���킪�N���}�����͂��C�����ȍ~���̎ԂŃ��[���b�p�𗷂��Ă₪�ăA�����J�Ɏ����A��c�c�Ƃ����b�����z����Ă��܂����D���̏�ŁC�g���^�����������̂悤�ɂȂ肽�����̂��Ǝv���Ă��܂����D
(1990�N��C�c���H��Ń��N�T�X�̐��Y�J�n���C�H��Ƃ��āC�ē��p�̓d�C�����ԂƃQ�X�g���[�����������܂������C���������őS�ГW�J�ɂ͎���܂���ł���)
�b�����ɖ߂��܂��ƁC������Benz�̒��ł�
- �v�@����@���Y�Z�p�@����@��������
�̏������C�v�͑呲�ł����������m���������G���[�g�C���Y�Z�p�����l�̃G���[�g�W�c���ƌ����܂��D
�w����x�̋L���͐�̌����������C��H���̔����������Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��D
�w�v�x�͖�T�`�U�N�|���āC�����Ȏԗ���v���C�v�}���쐬���܂��D
�w���Y�Z�p�x�͂P�`�Q�N�|���Đv�}����ɁC�H��v���C�ݔ��z�u�C�H���Ґ������܂��D
�w��������x���Y�Z�p����C���Y�ݔ��Ɛ����H���\���������������́C�l�������p�ӂ����v�����}�C�X�^�[���K�ޓK����z�u���Ă��܂��D�ǂ̍H���ɁC�ǂ̍�ƈ���z�u���邩�́C�����ĒN���N�r�ɂ��ē���ւ��邩�̓}�C�X�^�[�̌����ł����D
�w�����̃��X�g�����ɎM�ŏA�E����ƁC��N�܂ŎM����������x�Ƃ������t������悤�ɁC�h�C�c�̎����Ԃ̑g���H��ɂ����Ă��C�^�C�������t����l�́C���̉�Ђɂ�����肸���ƃ^�C�������t�������鎖�����ʂŁC�����̎d�����}�X�^�[�����悤�Ƃ���ƁC�c��Ȕ�p����������ƍl���邩��ł��D
����䂦�ɁC���Y���C�������オ�蓖���ɍ�����H���Ґ��́C�x�X�g�ȕҐ��ł���ƍl���C���̈ꕔ��S�����@�ɒu����������P�͐i�߂܂����C����Ȃ��Ȃ����Ɓ@�@�����Đ�ɏq�ׂ��w���l�� (Flexible�@���P)�x�͍l�����C���������̍ɂ�ςݏグ����C�����Ԑ��Y���C�����~�߁C��ƈ������ق��܂��D�܂�̐��͓����̂܂܂ŁC�����Ԑ��Y���~���邱�ƂŁC�ɗʂ�����̂ł��D����́C���̊��̉��ł́C�J����͕ϓ���Ƃ��Čv�シ��̂ł��D
�����Ă��̗��ɂ́C�N�r���Ă�������̎������m�ۂł���Љ�ۏؐ��x�ƁC�ďA�E�������鋭�͂ȘJ���g��������킯�ł��D
���{�̘J�����̓��ِ� (���Ԑ����Ƃ̗�)
Benz�̎Г��ł́C�e�@�\���Ɨ����Ă��ĐӔC�͈͂����m�ŁC����������̊��������Ȃ��g�D�ł������C1987�N���̃g���^�̏́C���}�̂悤�Ȃ��Ă��܂����D
- �v�@���@���Y�Z�p�@���@��������
�w���x�́CConcurrent�EEngineering ��\���C�g���^�ł�1970�N�J���[��2��ڂ���n�܂�C�S�ГI�ɓW�J���Ă��܂����D�h�C�c�ƈႢ�C�ŏI�H���ł���g������̔ǒ����v����ɏo�����čs���C�J�����̎���Ԃ̕���g�t�����s�Ȃ��C��Ɛ�����̒�Ă����Ă��܂����D
����̓g���^�̒��ł́C�@���Y���̌����C�A�V�ԊJ���ɎQ�悵���Ƃ��������[���̌���Ɋ�^���܂����D�����Č���C�B�������̗ǂ����璆�Îԉ��i���㏸���C���ꂪ�V�Ԕ̔��͂ɍv�����Ă��鎖�����炩�ɂȂ�܂����D
���{�ł́C�呲�ȏ�̓��Ў҂́C�L����w�ɓ��w���C�L����Ƃɓ��Ђ���Έꐶ�y���ł���ƌ����y�������C�����Ȗ� (���Z�ے��̈ꕔ��)�݂̂�ҕ����C��w����Ίw��������搉̂��C�����y�����邽�߂Ɉꗬ��Ƃɓ������c�c�Ǝv����V���Ј��𐔑������Ă��܂����D���ꂽ�ȏ��͂��邽�߂ɁC���̔z���悪�C�ғ��P���Ĉ�l�O�ɂ��Ĉ�ĂĂ����Ă܂����D�Ɩ���i�߂Ȃ����i�������B�̐l�����������C�\�͂̂���l�Ԃ��������C��p�҂Ƃ��ĎГ��ň琬���Ă��܂����D���ʂƂ����w��̒��̊^�I���Ԓm�炸�x�̌o�c�҂������Ȃ�܂����D
�������Ђɂ��ẮC���ƍ��Z�͎������ɁC�H�ƍ��Z�͕ۑS�������̓��Z������E��ɔz���ɂȂ�C�����ōX�ɋZ�p��g�ɂ��čs���܂����D
���͂����镁�ʉȂ̐��k�����ł��D���Z�ł͎����D�悵�C�Љ�ɏo�đ����ɗ��Z�\�͉���g�ɂ��Ă��܂���D���̐��k�����́C������Ƃɂ����ẮC�����ƈ��Ƃ��č̗p����Ă��܂����D
�e��������ł́C��͂Ƃ��ė��h�ɓ����Ă��炤���߂ɋ���P�����s�Ȃ��܂������C����͌����Đ��Ԉ�ʂɒʗp������̂ł͂Ȃ��C���̉�Ђ́C���̐E��̕K�v�Ƃ���d�����ł���悤�ɂȂ�悢�c�c�Ƃ��������̎Ј����������܂����D
�g�������͊����ł����C����̓h�C�c�̂悤�ɎY�ƕʂł͂Ȃ��C��Еʂ̑g���ł�������C��U��ɂȂ�Ή�Ђ��痣��Ă��܂��C���E�ɒʗp���鉽�̎��i�������܂܂ɕ���o����Ă��܂���ԂɂȂ�܂��D�܂�m�l�������n�ƌ����Ă��C�Y�ƕʑg���̋������ď����ɔ�ׂāC��ВP�ʂ̑g�����������Ȃ����{�ɂ����ẮC���̈Ӗ�����Ƃ���͑S���Ⴄ�̂ł��D
�ǎҏ��N���C���̈Ⴂ���悭���ݒ��߂���ŁC�w������Ђ͉���l�̐l���������x�Ƃ����L���̎Љ�I�ȃC���p�N�g���悭�������Ă��������K�v������܂��D
�w�g���^�����Ԃ����������x�Ƃ���ƕ��c�������o���܂��̂ł��̏�́w�M�҂̓ƒf�Ō����Ɓx�Ƃ��Ă����܂����g���^�����݂��邻�̖{�����w�������h�x�ɂ���܂��D�w�������h�x�Ƃ́C�ߍ]���l�̎O���ǂ��Ɏ��Ă��܂���
- �ڋq�̖���
- �����E�n���E���̖���
- �]�ƈ��̖���
- ����̖���
- �o�c�҂̖���
�ƍl���Ă���܂��D
�ŋ߃}�X�R�~�ŁC���Y�̌o�c��Ԃ��b��ɂȂ�C���������C��V���傫���̂ɑ債�����������ĂȂ��Ƃ��Ē@����Ă��܂����C�ނ�͂��������āC�o�c�҂̖�������Ԃɂ����Ă���̂�������܂���D���̕ӂ̂��Ƃ͌���wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�V���[�Y�ł��`���������܂��D
����(3) �]�ƈ��̖����ɍ݂�܂��D
�w�J���͐_����^����ꂽ���ł���x�Ƃ��鋌���̋L�q��M����̂ł���C�M�ƌ����W�ɏA�����`�N�����������M�݂̂�S�����C���U������Ƃ����̂́C�_�̖��ɏ]�������ƂŁC�Ȃ�ł��Ȃ����Ƃ�������܂���D
�������C�m�I�D��S�̍������{�Љ�ɂ����Ă��C�����Ă����Ă������������Ƃ����[�`���ōs���Ƃ������Ƃ́C��ςȋ�ɂł��D
���[�������ł��C�����ς���t�S�����߂ă��[���������C�q�̔��������Ȃ��炳��ɔ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C�����Ƌq�Ɋ��ł��炦�Ȃ����ƁC�m�I�D��S�������ɓ������C�d���𑱂��钆�ɁC��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���D
���������Ɨǂ�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����m�I�D��S��������s�����g���^���Y�������wKAIZEN�x�ƌ����܂��D
��������ł́C�H�Ɛ��i�ł��̂ŁC���̕i�����x��������C���Ƃ͑����̖��ɂȂ�܂��D�m�I�D��S���g���Ē��킷��̂́w��Ƃ̑����x�ɂȂ�̂ł��D
�Ⴆ�CA�N����Ƃ�10%����������������@���������Ƃ��܂��D���̎d���ɉ��p���Đ����͑����Ȃ�Ƃ��܂��D
A�N�̉�Ђ��w��Гs���ŏ]�ƈ������ق���ꍇ�͂܂��В������C����x�Ƃ�����Ђł���C�ނ͂��̈ĂX�ƊF�̑O�ɐ������C�F���d���������ł���悤�ɂȂ邱�Ƌ����������CA�N��J�ߏ̂��邱�Ƃł��傤�D
A�N���C�]�ƈ�����l���ق���C�������P�Ɍ��т��������Ƃ��ĉے����]��������Ђɂ����Ƃ���CA�N����Ă���C���̌��ʒ��Ԃ̒N�������ق���鎖�Ɍq����܂��D�܂���P������Β��Ԃ����ق����l�ȍH��ł́C�����ł��ǂ����Ă������Ƃ����D��S��i����S���Ȃ��Ȃ�܂��D���̑���C�ǂ�����Ċy�����悤�D�蔲�������悤����Ƃ����S���萶���Ă��āC�E��͐Â��ɕ��Ă��܂��D
�݂�Ȃ����������������ē����C���ɐ������邱�Ƃ���낱�т�����Ђɂ��邽�߂ɂ́C�w��Гs���ʼn��ق͂��Ȃ��x���ƁwKAIZEN�x�͕K�{�Ȃ̂ł����D
�v�킸���b�ɂȂ��Ă��܂��܂������C�g�����v�łɂ���Đ��E�o�ς��C���[�}���V���b�N�����Ђǂ���ԂɂȂ�Ƃ����������钆�ŁC��Ђ̐��E�����s���ւ̔����͖��S�ł��傤���C���Ђ̂����߂���w�l�����炷�ȍɂ����点�x�������ɗ��Ă�K���ł��D
[2] ���̑����C���Ėf�Ր푈�ƃg���^�̑Ή�
���N�����g���哝�̎��̑���Ėf�Ր푈�ɂ��Ă��b�����܂����D
�č��̋����v�]�ŁCGM�̃L���o���G���w�g���^�L���o���G�x�Ƃ��ĉ������ē��{�S���̃g���^�X��ʂ��Ĕ������܂����D�ĎԍD���̏��W���[�W�܂œ������đ�X�I�ɐ�`���܂����D�Ō�͔��l�ȉ��̒@������܂ł��܂������C�ڕW��5����ɂ͉����y�����ꂽ�̂�2������䂾�����ƌ����܂��D
����͓��{�ɂ�����g���^�ƃT�v���C���[�Ƃ̊W�̕Ґ��ɂ��Ă��b�����C���ꂪ�č��ɂ����Ăǂ̂悤�ɓW�J����Ă������C�����Ă��ꂪ����̃g�����v�łɂ��Ăǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ����ɂ��Ă��b�������Ǝv���܂��D
[2-1] 1995�N��_�W�H��k�Ў��̒��B���i��
1995�N1��1���t�ŁC�M�҂͕����Ǘ�������q�����܂����D
�g���^�̕�������́C�����͂�����E�̖��[�܂Ŋ����Ԃ��^���w�ԗ��������x�C��C�p���i�������E�S���E�̏C���H��܂ʼn^���w���i�������x�C�����̉��u�H�ꂨ��ъC�O�̍H��Ő��Y����ɕK�v�ȕ��i���^���wKD������ ��ɐ��Y���i�������x�C���������C���P�𐄐i���镔���Ƃ����w�����Ǘ����x�̎l�����琬�藧���Ă��܂����D
���C����Ԃ��Ȃ�1��17����_�W�H��k�����N���܂����D���ꂩ��̕��C���Y�S�����В������Y�̑S�ʒ�~�����߁C�e�����ɂ��˂Č��߂Ă��������C����~���̎��{�����𐋍s����悤�ɖ����܂����D
�����āC�����ԂƐ��Y�p���i���`�̖��É��`�̐��`�����Ԑ�p��RORO�D����~����̂Ő_�ˍ`�ɋ~���������^�Ԑ\���o�ł����āC����̎��O�\�����Ȃ��̂Œf��ꂽ���͑O�b���܂����D
�H��ĉғ��Ɍ����čו����l�߂Ă������ɁC���k�n������̕��i���g���^�ɓ͂��Ȃ����Ƃ�������܂����D
�ЊQ�����͍̂�_�n��ł��D���̉e���łȂ����k�n������̕��i�����i����̂�?�T�v���C�`�F�[���̖��Ƃ��āC���Y�Ǘ����E�w���Ǘ��������S�ɂȂ��Ē������܂����D���̌��ʂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł����D
�h���V���b�N�E�Ζ��V���b�N�����z���C1980�N����{�o�ς̓o�u�������}���C�l��s���Ő��Y���ǂ����Ȃ��ɓ����Ă��܂����D1991�N�C�c����3�H��Ńg���^�}�W�F�X�^�������オ�����Ƃ��C�g���^��Supplier����C�w����ȏ�͍��Ȃ�!�x�ƌ����ߖ��オ�����ƌ����܂��D
Supplier�͈�ʂɂ͈ꎟ������ (Tear1)�C���̉��ɓ����� (Tear2)�X�� (Tear3)�C (Tear4)�܂ł���Ƃ���Ă��܂��D���ɍs���قǂ���K�͂��������Ȃ��Ă䂫�C���[�ł́C������Ƃ�������Ɛl��ōs�����x���܂Ńu���C�N�_�E������C�_�Ƃ̕��ƂƂ��čs���ė��������C�����͐l��s���̒��Ő��Y���}�g�債�čs�����ƌ����Ă��܂��D
���̌��ʁCTear1����B�������̂ɁCTear3�͓��k�ɍ݂������̗Ⴊ���o�����̂ł����D
�g���^�̃T�v���C�`�F�[���}�l�W�����g�́C�ˑR�̎��́C�J�����c����Ώۂɍl���Ă���C���i�͕K�����Д����Ƃ��C�i���Ɖ��i�������ɋ��킹�C�����𑣂��Ă��܂������C����́C�g���^�̑g���H��͈��m�����ɍ݂�Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��Ă��܂����D
1995�N���݁C�g���^�̑g���H��͇@��B�n��C�A�����n��C�B���k�n��ɕ��U���Ă���C�n�k�卑���{�ł́C���E��C�n�k�C�֓������^�n�k�C���k���n�k�C�k�C���n�k�C�x�m�R���Γ��X�̑�ЊQ���\��������܂��D�ЊQ�̎����������Ԃ����ĕ����Ɋ�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁC���̎����Ԑ��Y���_�E�����Ă͘b�ɂȂ�܂���D
���̎��C�g���^�͓��{���w��B�n��x�w�����n��x�w���k�n��x��3�������ǂ̒n��ɑ�ЊQ���N���Ă��C���̒n��͐��Y���ێ��ł���悤�����Ƃ�������j���f���C�O���[�v��̂ƂȂ��Ď��g�ݎn�߂܂����D
1997�N�A�C�V����P�o���u����
���@P (�v���|�[�V���j���O)�o���u�Ƃ́C�}�u���[�L�������^�C�������b�N���Ȃ��悤�Ɉ��͒�������z�Ǘp�b�����H���i�C���d�r���炢�̑傫��1997�N2��1���ߑO4�����C�A�C�V�����J�H��ŏo�C4���Ԍ���D�Ď������̂́C�g���^�̎g�p�ʂ�99%��������P�o���u�����H���������D���S�g���^�̍H�ꂪ��~�܂����D
�A�C�V���{�͕̂����H����i�߂�ƂƂ��ɁC�}�ʂ����J���ċ@�B���H���[�J�[�ɐ��Y���͂��˗����܂����DP�o���u�̐������˗����ꂽ���[�J�[�̒��ōő��œ͂����̂�2��5���ł����D�����C�����Ԑ��Y�̍ĊJ���ł��܂����D
�@�B���H���[�J�[�̋��͂ɂ���ċɂ߂ĒZ���ԂŁC����̐��\������P�o���u�������ł������ƁC���������H��@�B���C�S�͂������Đ��삵�H��̕������ł������ƁD�g���^�O���[�v�Ƃ��Ẳғ���~���Ԃ�5���ԂŎ��߂����Ƃ́C�g���^�O���[�v�̌����̌����Ƃ��Ęb��ƂȂ�܂����D
��@����̊ϓ_����̃T�v���C�`�F�[�����v��i�߂Ă��܂������C����ΊO�l�喼�����Ɂw��_�W�H��n�k�x�̍Ĕ��h�~��}���Ă��Ă��āC����喼�ɂ͔����肪�������ƁC�唽�Ȃ����C�X�ɗ͂����āC�w�O�������x�ɗ͂����Ă����܂����D
2011�N �����{��k��
3��11���ߌ��Q���{���P������k�Ђ́C�}�O�j�`���[�h9,0�Ƃ����C�ϑ��j��ő勉�n�k�ł����D���̒���C���ݕ��ɋ���ȒÔg�������C����Ȕ�Q�Ƒ����̐l���������܂����D����ɂ��̒Ôg�́C���q�͔��d����p���u���C�����g�_�E���ƌ����̔������̂��N�����C�����̕��˔\���U�炵�Ă��܂��܂����D
�����Ǘ������Ƃ��āC���É��`�͖��É��s�̈�p�ɂ���̂ɁC���`�Ɛ��s���Ȃ����̂悤�ɗ���Ă���̂��^������������Ă����D��k�Ђ̈ꃖ���㌻�n��K�ꂽ���C���`��1�K�����͒Ôg�̔�Q�ɑ����Ă��܂������C�����͖�����2�K�ȏ�͔�Q������܂���ł����D�����Đ��s�͑S���Ôg�Ƃ͖����ł����D
�W�҂ɕ����ƁC�ɒB���@����Ôg���o�����C�C�݉����ɓc�������̂��֎~�C���c�݂̂��������D���̍��Ղ��w���x��w�q�x�w���x�̒n���Ɏc���Ă���ƌ����܂��D
���������������͊댯�Ƃ����Δ�܂ł���ƌ����܂��D����́C�Ôg�ʼnƉ��𗬂ꂽ��Q�́C�Ɖ��̌��݂͍s���@�����v��܂�����C�s���̑Ӗ��䂦�̐l�Ђł����D�ƍl����������܂���D
���q�͔��d���̔�Q�ɂ��ẮC�߂��̏��쌴�q�͔��d�����C�Ôg���ӎ����č���Ɍ��Ă����Ƃ��l����ƁC�댯�����Č��ݔ���������߂������d�͂̌o�c�ҐӔC�͖Ƃ�Ȃ����̂ƍl���܂��D�ٔF�����s�����������߂ƍl���܂��D
�b�����Ƃɖ߂��܂��D
�g���^�����Ԃ́C�k�Д�������C���[�`���ɏ]���S���C�����~���āC����̔c�������{�����ƌ����܂��D
���ꂾ���̑�ЊQ���ẮC�L�c�͒j�В������������n�ɔ�сC���{���P�������\�L�̍ЊQ�ɑ��ẮC�܂��l�����C�Љ���̕����C���̎��ɉc�Ɗ����Ɉڂ�ׂ��ŁC������������邽�߂ɁC���n�Ŏw���������ƕ����Ă��܂��D
�����ē��k�����̂��߂ɁC��茧�ɉ����ċ{�錧�ɂ��g���^�O���[�v�̍H���U�v���āC�ӎ��I�Ɂw��B�x�w�����x�w���k�x�̂R�吶�Y���_�\�z���������C�V�H������݂��܂����D
TNGA (Toyota New Global Architecture)�́C������̗ǂ��N���}�Â���̂��߂̐v�W���ƍl���C����ɂ���Ďԗ��̍\�����i�̕W�������i�߂C���i�̎�ނ�����C�ʎY���ʂ��o��Ƃ����l���Ői�߂Ă��܂����D
���C�����{��k�Ђ̌o���́C�ُ펞�ɂ�����T�v���C�`�F�[���̌��S���������炷����̊����C�������ւ̗͂��������̂ł����D
����́C���{�ōЊQ�̒��ŋ�������Ă����T�v���C�`�F�[���}�l�W�����g��TNGA�ɂ�镔�i�̋��ʉ��C��Ƀg���^�Ƌ��ɐi�o���C�g���^���V�F�A��L�����͂�Supplier�Q�̓����ɂ���āC�g�����v�ʼnۂ̕č��嗤�̒��ŁC�g���^�������ɗL���ȏ������ł���̂����C�������܂��D�����҉������D
�����́C�L���ȉ�Ђ����X�Ɛl�������̘b������p���ɕ��������C���Ђ̃X���[�K���w�l�����炷�ȍɂ����点�x�Ɏ��ʂ��g���Ă��܂��܂����̂ŁC�wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�͍��������x�݂��܂��D���e�͂��������D
2025�N5��21��
(��)J�R�X�g������ ��\ �c�����m
2025�N4��
�����̋G�߂̏��M�\��
4�������C���{���z���܂����D
�F�l���������߂����ł��傤���D
���Ђ̂��閼�É��s��̐��̓y��́C�Z���̂��߂̗V�����Ƃ��Đ�������Ă��܂����C�����ɂ͎���30�N�̐���g��̕��ɂȂ��Ă��āC��D�̉Ԍ��ꏊ�ł�����܂��D���N�̖��J�͂��x���C4���̑�1�T�ł����D���T�́C�߂��ɂ���X�H���̔��d�������J�ł��D
�ّ�̒�ɂ́C�t�̖��o��`����2��ނ̒������܂��D��ڂ͋�S���Ĉ�Ă悤�₭�t���w��O�L�т��R���D������́w�܉��x�C����͕đ�ˏ㐙��R�ŗL���ł����C�M�B�ł��t��ɐH����Ă���C���Ƃ���ڐA�������̂ł��D�䂪�Ƃł͂�����H���ďt����������K�킵�ł��܂��D���N����N�ʂ�Ƒ��ŐH���C�t�������������܂����D
���₩�Ȑg�̉�肩��ڂ��O�ɂ��ƁC�n���K�͂̑卬�����Q�����Ă��܂��D
�w���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�x�C�w�C�X���G���ɂ��p���X�`�i�U���x���ɑ�\����镐�͏ՓˁD�ُ�C�ۂɋN������H�Ɗ�@���X�C�����ɉɂ�����܂���D
�������Ȃ�Ƃ����Ă���X�̐����ɒ�������w�g�����v�Łx��������Ԃ̖�肾�Ǝv���܂��D
�����́C�g�����v�Ŗ��̂����C�M�҂��̌������w���Ď����Ԑ푈�̗��j�x�����`�����܂��D
�L���ȁw���q�̕��@�x�ɂ́C
������ �悸������ ������̂��ɐ킢�����߁C
�s���� �悸�킢�� ������̂��ɏ����������ƂށD
�Ƃ����̂�����܂��D
����̃g�����v�ł́C���炩�ɊŊz���̂��グ�܂������C�����̉����� ���̗����̍��������āw�������x�����Ă��܂��D���q���猩�܂��Ƃ���͕�����ł��D
���{���̊Ō��c�̊���ŏ��@����������Ă��炢�������̂ł��D
�Ƃ͌������̂́C���悢��4������A�������Ԃ�25%��4��3������C�A�������ԕ��i�ɂ�5��3������ېł���鎖�ɂȂ��Ă��܂��D�e���[�J�[�Ƃ����J�����̍ɂ�����Ă��܂��̂ŁC�s���̔̔����i�ɕω��������̂́C�ɂ���Ă���ƌ����Ă��܂��D�A���Ԃ��ǂ̂悤�ȉ��i�Ŏs���ɏo��邩���ڂł��D
TOYOTA�ݐВ��ɓ��Ď����Ԑ푈��2��o�����Ă��܂��̂ŁC���̊T�v�ƁC�����ʂ����ĕč��s���TOYOTA�͂ǂ̂悤�ɐi�����Ă������̂��T�v��������������ŁC����̃g�����v�łɔ@���Ɏ��g�ނ���OB�Ƃ��Đ����������Ǝv���܂��D
(1) ��P�����Ď����Ԑ푈 1980�N�`
- 1973�N�̃I�C���V���b�N�ȍ~�C�R��ǂ��C�i���̍������{�̏��^�Ԃ��A�����J�s��ŋ}���ɃV�F�A���g�債�čs���܂����D
- ����C�A�����J�̎����ԃ��[�J�[�́C��^�ŔR��̈����Ԃ����S�ł���C�i���ʂł����{�̃��[�J�[�ɗ��Ƃ����ł����D���̂��߁C���{�Ԃ̍U���ɂ��C�A�����J�̎����ԃ��[�J�[�̔̔��䐔�͌������C�Ɛт��������܂����D
- �A�����J�̎����ԎY�Ƃ̘J���g��(�S�Ď����ԘJ���g���CUAW)��c��𒆐S�ɁC���{����̎����ԗA���̋}���ɑ���s�������܂�C�u�ٗp���D���Ă���v�Ƃ������������Ȃ�܂����D
- 1980�N���a�}�̃��[�K���哝�̂��A�C
���R�f�Ղ�搂����a�}�Ƃ��Ă͗A���������|����킯�ɍs���Ȃ��̂ŁC�A�����J���{�͓��{���{�ɑ��Ď����ԗA�o�̎���K�����������߂�悤�ɂȂ�܂����D - ���{�̎���K��:
�A�����J���{�̋������͂ɑ��C���{���{��1981�N5���C�ΕĎ����ԗA�o�̎���K���[�u�����܂����D�����͔N��168���������Ƃ�����̂ŁC���̌㐔�N�Ԍp������܂����D���i���E��R��̓��{�Ԃ͎s���ł͈������肾���ŁC�v���~�A�t���ł̎�������o��قǂł����D - �č����{�̈ӌ�������ŁC���{��HONDA�̓I�n�C�I�B�CNISSAN���e�l�V�[�B�ɐ��Y�H���i�o�����܂����D�A�����J�����ł̌��n���Y��{�i�������C�f�Ֆ��C�̊ɘa��}��܂����D
- TOYOTA�́CGM��NUMMI�Ƃ������ى�Ђ�ݗ�(1983�N)���܂����D����́C�w�g���^���Y�����x���w�т����Ƃ���GM�̃X�~�X��ƁC�k�Ă̎����ԕ��i�́wSupplier�̎��ԂƁC�����Ǝ҂̎g�����x�Ȃǂ�m�肽��TOYOTA��沓c�p���Ƃ��ӋC�������Ăł�����Ђł����D
GM����h�����ꂽNUMMI�����v���Ɛe�H��ɂȂ鍂���H��ō��h���C�����H��̌���Ǘ����������p�������Ă����܂����D���ԓ��ň�ĂĂ���TOYOTA�̌���Ǘ�System���CGM�I�肷����̗D�G�Ȑl�ނƋ��ɒ���p�������钆�ŁC���H���R�Ƃ����Ǘ��̐��ɍč\�z����čs�����̂ł��D��ԕ��ɂȂ����̂�TOYOTA���g�������Ǝv���܂��D���̈���w���P�x�Ƃ����T�O�́wimprovement�x�ł͕\���ł��Ȃ��C���Ăɂ͂Ȃ��������wKAIZEN�x�Ƃ��ׂ����C�ƕĐl�ɋ����܂����D1985�N�ɖ{�i�ғ��J�n�������̍H��̊���Ԃ���wNUMMI�̊�ցx�ƃl�b�g�Ō����ł��܂��D
�b�͂킫���ɂ���܂����CNUMMI���̂�2010�NGM�̓|�Y�ƂƂ��Ɉ�U���U���܂����C���N�e�X���ЂƋƖ���g���C����NUMMI�H��͌���w�������x�̌`�Ńe�X���Ђɏ��n����܂��D
�wUAW�x�̉e�����ɂ͍݂�܂����C�k��1�Ԃƌ���ꂽ�i���Ɛ��Y�����������������H����C�e�X���͎�ɓ��ꂽ�̂ł����D�]�ƈ�����������C�f���炵���H��ɂȂ�ƒN�����v���܂������C�����̃e�X���̕i�����͎��ɂ��܂���D
����C�������ŁC�w�Ɠd���[�J�[����EV��������x�Ƃ������݂�܂����C����TOYOTA�Ŋe�H�ꂩ��l���W�ߐV�H��𗧂��グ�C�V�^�ԃ\�A���Y�����o�������M�҂ɂ́C���Ǝ킩��Q�����C�����I���ʂ�̔����Ă���Ƃ���Maker�̕i���ۏɋ^�������Ă���܂��D�\���E�ԗ��ЁE�Ďn���s�\���X�̎��̂��N���Ȃ����Ƃ��F��݂̂ł��D - �b�����ɖ߂��܂����CNUMMI�Ŋw���Ƃ��x�[�X�ɁCTOYOTA���͂ŃP���^�b�L�[�B��TMMK�H������݂��C���N�J�i�_ �I���^���I�B��TMMC�H������݂��܂����D1986�N�ł����D����ɂ��100����/�N�̐ݔ��\�͂��m�ۂ����̂ł����D
���{�̎����ԃ��[�J�[���A�����J�����Ő��Y���n�߂邱�ƂŁC�A�����J�����ł̌ٗp�n�o�ɂ��v�����܂������C�����ɃA�����J���[�J�[�Ƃ̋����͂�范�����܂����DGM�EFORD �ECHRYSLER�̂�����BIG3�́C���͂ȘJ���g���wUAW�x�̒�R�C���ԈˑR�Ƃ�����ƕ��y�ɑj�܂�C�y�ʉ��C��R����i�݂܂���ł����D
1989�N�wThe Machine That Change The World�x����
1985�N���[�K���哝�̂́C�w40�N�O�ɏĂ��쌴�������{���C�Ȃ��폟���̕č��𗽂��悤�Ȏ����Ԃ����Ɏ������̂���������x��MIT(�}�T�`���Z�b�c�H��)�̌����O���[�v�wIMVP (International Moter Vehicle Program)�x�ɖ������̂ł����D
1989�N�ɒ������ʂ�����C�ȉ���(A)(B)(C)�����{�̔��̌��ł���Ƃ���܂����D
- �č�Deming���m�̒����wTQC�x��^�ʖڂɓW�J���Ă���D
���̈�Ƃ��Đ�������ł��wQC�T�[�N�������x������ŁC����̍�ƈ����C�����B�̐E��̉ۑ�������C�����B�ʼn��P���Ă������ŁC�i�������Y�����𐬂������邾���Ŗ����C���̊����̒��Ɏ��������̂�肪���������Ă���c�c�D - �wTWI (Training Within Industry)�x��č����瓱�����Ċ��p���Ă���D
���{�̐����Ƃ͍���TWI ���g���ėD�G�ȍH����{�����C�����ō��i���̏��i�Y���Ă����̂ł����D
���G�wTWI (Training Within Industry) �č��Ŏ��{���ꂽ�C����E��풆�̏��W���ꂽ�H���ɑ����ē������ꂽ��w�Ȃǂ̖��o���҂��C�ꍏ��������l�O�̍H���Ƃ��ē����Ă��炦��悤�Ɏw�����錻��ē҂̂��߂̋���v���O�����x - MIT�̌o�ϊw�҂��Ԃ��ɁCNUMMI (GM��TOYOTA�̍��ى��)�C���{���̐e�H��C�����H����O�ꂵ�Ē����������ʁC�����ׂ����������܂����D
�S���E��Best�ƍl���Ă���Ford ����Throne��������グ����ʐ��Y�����Ƃ��S���قȂ���Concept�́w�g���^���Y�����x�ŁCSupplier���܂߃O���[�v�S�̂������Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�̂ł����D
Essence���Љ��C10�̕��i���琬�藧�H�Ɛ��i���C10�ł̉�c�����ɗႦ��C�����100�����̂ɁC�w��ʐ��Y�����x�ł́C�悸�e��100���A���R�s�[���C�S���������Ƃ����10�����Z�b�g���Ċ��������܂��D�w�g���^���Y�����x�ł�1�`10�ŕ����R�s�[�@�Ɋo�������C1����������Ă������@���̂�܂��D�������������Ԃɍ���Ȃ��Ă��C�����̎�������������̂ł��D���̂悤�ɃM���M���̍ޗ��ŁC�M���M����Timing�ł��C�Ԃɍ������������̊����i���ł��鐶�Y�����ł����D
�č��Ƃ��Ă̑Ή���
(A)��TQC�ɂ���
�č��̌����Hispanic�ɑ�\�����悤�ɁC�Č���ɘb���Ȃ��ږ��Ȃǂ������C���{�̂悤��QC�T�[�N�������͖����ł��邪�C���{�̊Ǘ��҂��w�������x�͌���C���ŁC��i�̂��@�����ŃS���t�E�J���I�P�E�����Ɍ������Ă��錻���c�����Ă��āC���̓��{�ɏ����߂ɂ͊Ǘ��ҁE�o�c�҂�Ώۂɂ����w�o�c�i���x�ɏœ_���i��C�wTQM (Total Quality Management)�x�ƌ�����@��҂ݏo���āC�S�č��ɓW�J�������D�X�ɂ�����g���Đ��ʂ��グ����Ƃɂ��wMalcolm Baldrige National Quality Award (�}���R���E�{���h���b�W��)�x�����Ƃ��Ď��^����d�g�݂�������̂ł��D
1990�N�ȍ~�C���{�ł�������݂̕č����Ƃ���܂��Ă��܂��D(GM�EIBM�EFedEx�EAT&T�ETexas Instruments �ERitz-Carlton Hotel�EKodak�E3M�EBoeing Airlift�E�c�c)
���̍��C���ł�Lap Top�^�p�\�R���C������Note�^�p�\�R�������C�₪���wWindows 95�x�����y���C���ꂪ�č���Office�����I�ɕς��܂����D�����������W��������C�d�q������C���ꂪ��^�d�Z�@��ERP�Ɍq����C�S�ГI����System�Ƃ��Ċ������čs���̂ł����D
��̗���Љ�܂��ƁC1995�N�C�A�[�J���\�[�B�ɂ���č��̋���X�[�p�[�w�E�H���}�[�g�E�X�g�A�[�Y�x�̖{�Ђ�K�₵���Ƃ��C�k�đS�X�܂̖�10���_�̏��i�̍�������̔��ꂽDETA�Ǝd���ꂽDATA�����C���O�̉q���ʐM�Ŗ{�Ђ��c�����āC���͂���ƌ����܂��D
�k�đ嗤���L���̂ŁC�t�͓삩��k�֓o���čs���C�~�͖k�����֍~��Ă��܂��D
�]���̔̔����т����Ƃɂ��āC�ǂ��ǂ��̓X�܂ł͖����͂ǂ̕i���ǂ̂��炢����邩�D���݂̍ɗʂ��킩���Ă܂�����C�����̌ߑO���ɉ����ǂꂾ����[����悢�̂��C�v�Z�ł��܂��D����Ɋ�Â��ăZ���^�[�f�|����e�X�܂ւ̔z���v�悪�ł��C�ŏ��̍ɂōő�̌��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł���c�c�D�Ƃ������Ƃł����D
��ЂƂ��Ă̏��i�̔���c���3%�ȉ��ɗ}���邱�Ƃ��ł��C���ꂪ�A�����J�ň�Ԉ����X�ƌ����鏊�Ȃł�����܂����D
���̂��߂ɁC����̂܂܂̎s��̓������K�v�ŁC�̔��C�x���g�͈��炸�C�wEveryday Low Price �x�̕��j���т��Ă���Ƃ����܂��D
�w�E�H���}�[�gl�x���͓̂����^�c�̐��ɂȂ��Ă��܂������CSupplier���T���ł����Ή����Ă���Ȃ��̂ŁC���T���v�\����Supplier�Ƌ��c���Č��߁C����c��̃��X�̓T�v���C���[�Ɛܔ�����Ƃ������[���ʼn^�p���Ă���Ƌ����Ă���܂����D
1995�N�����Ő�[�͂����܂Ői��ł����̂ł����D
����C�����̓��{�ł́C���̕������ɐ�y���������O�ō��グ���e�Њe�l�́w�o�c�Ǘ��̐��x��1980�N��܂ł̋}�����𐬂������܂������C��������Ђ́w�o�c�Ǘ��x���D��Ă��邩��Ɗ��Ⴂ�����wJapan As No.1�x�̎��ȓ����Ɋ|����C���ẮC���Ƃ�Global���ɑΉ��ł����w�o�c�Ǘ�System�x���w���ɂ��܂����D
1990�N��ɓ���ƁC���{�ł́C��O�ɓˑR1/30�̒����œ��������̋���J���s�ꂪ�J���C���E�K�͂Ō���Ύ��{��`�͋��Y��`�������Ƃ������ƂɂȂ�}篃O���[�o���o�ς��i��ł����܂��D�S�n���K�͂̎s�ꋣ�����������𑝂��C�o�c�Ǘ��̐��̕s��������{���Y���Y���ƒx����Ƃ��Ă��܂��܂����D
(B)��TWI�ɂ���
�e�Ђ͑�풆�Ɏ��{���Ă������߁C�č����{�͓��ɑ�����܂���ł����D����C���́wLean���Y�����x�ƃZ�b�g�ɂ��Ĉꕔ��Ƃŕ������܂����D
(C)�o�ϊw�҂Ɓw�g���^���Y�����x�Ƃ̏o�
�����ɓ�������MIT�̌o�ϊw�ҒB�́C�w�g���^���Y�����x��Concept�ɋ����܂����D�������C���̒��ɂ͉��Ă̊�Ƃł͎���ɂ����v�f�����X����܂����D�����Ŕޓ��́C���݂̉��Ċ�Ƃ������ꖁ�����|�����TOYOTA�ɒǂ��t���C�ǂ��z���鍀�ڂɌ������Ҏ[�����C�K�C�h�{�s���܂����D���ꂪ�wThe Machine That Change The World�x(1989�N)�ł����D���҂̃E�H�}�b�N���m�́C�����Ђ��グ�C���H��ʂ��Ď����҂Ƃ����wLean Thinking�x���㈲���܂����D�����̖{�́C�č���萻����Ђ�TOP�ɓǂ܂�C�����wJust In Time�x�͊e�Ђɓ�������Ă����܂����DGE�ЁC�{�[�C���O�ЂȂǂ͗L���ł��D
(2) ��2�����Ď����Ԑ푈 1993�N�`
�����CGDP���ʂ̕č��C���ʂ͓��{�ł����D
�N�����g���哝��(����})����ɓ��Ď����Ԗ��C(1993�N�`1995�N)���ĔR���܂����D���̔w�i�Ƃ��āC1980�N��㔼����C�A�����J�̎����ԎY�Ƃ͎���ɂ݂����v�����Ȃ��������߁C���{�̖k�Đ��Y�Ԃɑ��Ă��C���i�ƕi���Ō������C�č��Ԃ͎s��V�F�A��傫�������܂����D
BIG3�̌o�c�w�́C���Ђ̉��v�������r�[�����ɗ͂����C���{�̎s�ꂪ���I�ł���C�A�����J���i�̗A����j��ł���̂������Ԗf�Ղ̕s�ύt�̂��ƂƎ咣���܂����D���Ɏ����ԕ���ɂ����āC�A�����J�͓��{�ɑ��C���i�̗A���g���f�B�[���[�Ԃ̊J�������߂܂����D
��ȏo����
1993�N
�N�����g���哝�̂́C���{�ɑ��C�����ԕ��i�̗A���ڕW��ݒ肷��悤���߂܂����D���{�́C�ڕW�ݒ�͎s�ꌴ���ɔ�����Ƃ��ċ��ۂ��܂����D
1994�N
���ĕ�o�ϋ��c���J�n����܂������C�����ԕ���ł̍��ӂ͓����܂���ł����D
1995�N
�A�����J�́C���{�Ԃ̍�����(���N�T�X)�ɑ���100%�̊ł��ۂ��Ɣ��\���܂����D�����̃��N�T�X�̊v�V�[�g�́C�e�L�T�X�Y�̋��v���g���Ă��܂����̂ŁC���v�̔̔��ێ��𖼖ڂɃ��N�T�X100%�A���ېł����Ή^�����N�����Ă���܂����D
�B���ɂƂ��Ă�TOYOTA�Ƃ������́w�䂪�e�L�T�X�̉�Ёx�ɂȂ��Ă����̂ł����D���Ђ̂悤�ɁC���Y�ɂȂ��Ă� �ƈ���Lay off�����C�n��s���ɐϋɓI�ɎQ�����邱�ƂŁC�n��Z���Ɏe���ꂽ�̂ł����D
�e�L�T�X�B�������̔��Ή^�����ǂꂾ�����������킩��܂��C���N�T�X��100%�łȎ���߂ɂȂ�܂����D
�A�����J�̏�p�Ԃ���{�Ŕ���
���̑���C�č�������z�̕��i���w�����邱�ƂƁC�č����w�V�{���[�L���o���G�x����{�d�l�ɉ������w�g���^�L���o���G�x�Ƃ���TOYOTA�̃f�B�[���[�Ŕ̔����邱�ƂŊ����Ԃ̈Č��͎��܂�܂����D(1996�N�`2000�N)

�u�L���o���G�v�́C�[�l�������[�^�[�Y(GM)�̏��^4�h�A�Z�_���ł���D�X�|�[�c�J�[�Ƒ�O�Ԃ𒆐S�Ƃ��������̃V�{���[���ŁC�����1982�N�ɒa�������D
�A�����J�Ԃ���{�ł�葽���̔����邽�߁C�g���^��GM�Ԃ邱�ƂɂȂ�C1996�N����C3��ڂ̃L���o���G��4�h�A�Z�_����2�h�A�N�[�y�������̔������̂ł���D
�L���o���G�́C���C�ɑ���N���}�������D�������C�G���W�������͂���Ȃ�ɑ傫���C�^�]����ɑ��鑖�s���o���r�X�����ʂ��������D1989�N�ɍ����̎����ԐŐ�������ɂȂ�C3�i���o�[�Ԃւ̐Ŋz���r�C��3.0���b�^�[�ȉ��͌y�����ꂽ�D�Ƃ͂����C�L���o���G���̂̎����ŁC3�i���o�[�Ԃ̐Ő���o������ȕ��S����̂͏���҂ɂƂ��Ăނ������������D
���ĂƂ����Ԃ̌o�ϓI�ύt��ۂ��Ƃ́C�N���}�ɂ����Ă͂ނ��������C�����Ȃ��������ꂸ�ɂ���ۑ�̂ЂƂƂ����邾�낤�D�Ȃ��Ȃ�C�A�����J�l�ɂƂ��ď����ȃN���}�͋����̑Ώۂł͂Ȃ��C�t�ɓ��{�ł͑傫������N���}�͎�ɗ]�邩�炾�D����ɏ㋉�Ԏ�Ȃ�܂������C�����Ȏ��p�Ԃő傫���N���}�͈ꕔ�̊S�������ɂ����D
CM���o���o�������C�̔��X���撣�����̂ł����C�v���悤�ɂ͔���܂���ł����D����̃g�����v�U�̏ꍇ�́C�ǂ�ȎԂ�Ƃ����̂ł��傤���c�c�H
���̕ӂ�̋�J�b�͉��LYouTube����ŏڂ�����������Ă��܂��D
�A�����J�������ԕ��i����{�̍H��Ŏg��
���ʔ��킳�ꂽ�č��Y�����ԗp���i�ɂ��ẮC�g���^�Ƃ��Ă͏d��Ȗ�肪����܂����D�w�g���^���Y�����x�ł��w�������x�Ƃ����T�O����C�i�����͍H�����őS�ĉ������C�H�����o�����m�͑S�č��i�i�ɂȂ�悤�ɍH���v���܂��D����������ƁC����s�Ǖi���������Ă��C���̍H�����őΏ����C���i�i�݂̂����̍H���ɍs���悤�ɂ��Ă���܂��D
��p�Ԃ̑g�����C���ł́C1,500�`2,000�_/��̕��i��g�ݕt���Ċ����Ԃɂ��܂��D�e���i��0.1%�̕s�Ǖi�����݂��Ă��C�����ԃx�[�X�ł͍��i�Ԃ�1����������ƂɂȂ�܂��D
�Ƃ��낪�C�����̃A�����J�̌o�ϊw�ɂ��w�K���i���x���w�ߏ�i���x�Ƃ����T�O������C�s�Ǘ���0.1%��0.01%�Ɖ����Ă����ƁC�����R�X�g�������I�ɑ����Ă���Ƃ��C����ł�3σ(0.3%)�ʂ̕s�Ǘ����R�X�g�~�j�}���ł���Ƃ���Ă��܂����D
����CTOYOTA�̌���ł́C���u�Y�Ɖ�����Ă���̂ŁC�����ݒ�ŕs�ǃ[���ɂ���C�ȉ��������x�Ő����ł���̂ŁC�s�Ǘ��[����Nj����邱�Ƃ��C��ԗ��v�ɂȂ�ƌo���ł�������Ă��܂����D
�����C�č����畔�i��A�����Č���ƁC�{���ɐ��p�[�Z���g�̕s�Ǖi���������Ă܂����D���̃��x���ł͓���g���^�̃��C���ɒ��ړ����ł��Ȃ��̂ŁC��U�S����������H��ɑ���C��������g�ݗ��čH��ɔ������邱�Ƃɂ��܂����D
�]���̃g���^�̃T�v���C���[����̕��i��ɔ�ׂāC��ύ������̂ɂȂ�܂����D
���̌�C�S�ĂɃg���^���Y����(Lean���Y����)���s���n��ƂƂ��ɁC�����ԋƊE�ł́C����肷�镔�i�͂����܂ł�100%���i�i���펯�ɂȂ�܂����D
�ȏオ��1���E��2�����Ď����Ԑ푈�̕M�҂��猩���������ł��D
1997�N�ȍ~�C�X�ɐ������̍H������݂���ȂǁC�č��ɗn�����ނ��߂̎{���ł��Ă��܂����C����͎�������y���݂ɂ��ĉ������D
�@�ւł́C���j��k�炸�C�����̂��Ƃ݂̂̏�������ׂ̂ݕ��Ă���̂��c�O�ł��D
���̋L�����F���܂̎Q�l�ɂȂ�K���ł��D
���C�A�ڂ��Ă��܂��wTOYOTA��NISSAN�̗��j��J�R�X�g�_�Ŏa��x�͍��x�݂��܂����D
2025�N4��21��
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
