�A�ڃR�����w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ڎ�
JBpress�A�ڃR�����w�{���g���^�����x
�r�W�l�X���T�C�gJBpress�ɂ����āA2008�N����2013�N�܂ł̊Ԃɍ��v104��̃R���� �w�{���g���^�����x ��A�ڂ��Ă��܂����B
���ݘA�ڒ��̃R���� �w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ƕ����ēǂ�Œ����ƁA���[��J�R�X�g�̍l�������������邩�Ǝv���܂��B����A���L�̃����N�ɃA�N�Z�X���Ă݂ĉ������B
�ߋ��̏��M�\��
2020�N1��
��\�V�N�̂����A
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�F���܂̉v�X�̂�����Ƃ����W�����F��v���܂��B
���A�l�ŕ��Ђ���N�͑傫�Ȑ��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł��܂����B
�����ł́A������4�N�قǂ̊ԁA�ꕔ����Ɨl�̏㋉�Ǘ��҂̌��C�����˂��A�w�i�R�X�g�_�x�Ɋ�Â���Order-to-Derivery-Lead-time�Z�k�����̓W�J�̂���`�������ĎQ��܂������A�����ǂɂ��Ă͏]����1�^3�܂ŒZ�k���邱�Ƃ��o���C���C����擪�ɗ����ĉ����i�ߑ傫�Ȑ��ʂ��グ�����Ƃ��Ǘ��҂̊F���܂̎��M�Ɍq����C�����̌��C�ړI���ʂ������Ƃ��o���܂����BClient�l�����Ŗ����C���ЂƂ��܂��Ă����̎����ւ�Ɏv���Ă���܂��B
�����ł́A6���ɍP����wLean Summit in Shanghai 2019�x�̈�Ƃ��āA�ۈ�����w�i�R�X�g�_�x�̍u�K�������{�������܂����B���ꂪ�����ƂȂ�A�͓�Ȃɂ��鍑�c��Ɨl�́w�i�R�X�g���v�x�̂���`����9������J�n���܂����B���o������������������܂��C�����̌������̓I�w�����o���Ă��܂��B
���肵�����_�ł́C���{�Ƃ̍��͑傫���̂ł����C�ޓ��̋z���́C���s�͂͑f���炵���C2020�N�x���ɐ��ʂ������C2021�N�́wLean Summit�x�Ŕ��\���悤��ψӋC����ł��āC���N�̕��Ђ̎�v�ȋƖ��ɂȂ�܂��B
����2020�N�̏d�_�ڕW�́A
- �w�i�R�X�g�_�x���p�ꌗ�ւ��L�߂Ă�������
- �������S���Ⴂ�l�����ƍX�Ȃ�w�i�R�X�g�_�x�̌�����������
�{�N���ǂ�����낵���������̂قǂ����肢�������܂��B
�����͐����ɑ��������A�����Ŋ������y���b������͂����܂��B
�y�����ɔ�������ꂽ�b�c�c�z�p�X�|�[�g���ؕ�����ɂȂ����I
�����ł͍����S���̐ؕ����̂ɐg���ؖ������K�v�ŁA�O���l�̓p�X�|�[�g���K�v�ł��̂ŁA��N���A�����ō����S���ɏ�邱�ƂɂȂ�A�����̂悤�Ƀp�X�|�[�g��n���Đؕ��̍w���𒆍��̗F�l�ɗ��݂܂����B
�u�����Ă��܂����B�v�ƌ����Ă��̗F�l�͎��Ƀp�X�|�[�g������Ԃ��Ă���܂����B�u�ؕ��́H�v�Ƃ����₢�����ɁA�u�ؕ��̓p�X�|�[�g���ɓ����Ă���v�Ƃ����Ԏ��ł����B
�l���Ă݂�A�q���A�z�e���̗\����p�X�|�[�g�ōs���Ă���A�����ƌ����Γ����R�����p�X�|�[�g������Γ��ꌔ�̖��������Ă���Ƃ�������c�c�̂œ�����O�Ƃ������܂��B
���{�ł�1960�N�A���S�̍��ȗ\��System�}���X�Ƃ��Ĕ������A�V�����Ԃ̔��B�ƂƂ��ɐ��E�Ɍւ��System�ł���܂����B����ȍ~�i���͑����Ă��܂����A�ߘa�̍����ł́A�w�������C�e�[�v�̎����̐ؕ��x�Ɓw�菑�����[�x���܂��c���Ă��镪�����A���E��Top�����i�[���猩��A����x��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����B
�y���������{�ɒǂ����Ă����c�c�z�����ŃV�����[�g�C������
2015�N����K�ߕ����Ǝ�Ȃ̍��߂Łw�g�C���v���x�͎n�܂����Ƃ���Ă��܂��B��s��̃z�e���ł́A�ǂ��ł�����g�C���ɂȂ��Ă��Ă��܂������A�܂��܂����{�̃V�����[�g�C���ɂ͏��荇���Ă��܂���ł����B
12�����A��������̋A�r�̏�C�˖��É��ւ́A����70�N�L�O�N�Ɍ��Ă��Ƃ�����C�Y������̐V�^�[�~�i������ł����B�����̈АM�����������������āA�傫�����ȋ�ԂŁA�r�W�l�X�N���X�p���E���W�͍ŏ�K�ɂ���A�ݔ��͊������Ă��܂����B
�g�C���ɓ���Ɓc�c�����ɂ͂Ȃ�ƃV�����[�g�C��������܂����I�����ŏ��߂Ă̏o��ł����I�R���g���[���p�l���ɂ́w�r�f�x�̕\���͂Ȃ��A�w���g FRONT�x�Ƃ���܂����B���ꂪ�����̐V������ƂȂ�̂ł��傤�B���{�̍Ō�̉��A�V�����[�g�C�������������̒��ɗn�����ݎn�߂��Ǝv���ƁA�������悤�Ȏ₵���悤�ȕ��G�ȋC�����ɂȂ�܂����B

2020�N���U
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
2019�N8��
�c�����������\���グ�܂�
�ߘa�̌����}��100�]�����o���܂����D���C�V���Ј��̏��N�́C���Ќ�̏���̋���P�����o�ĐE��ɔz������C�{�i�I�Ȏd���Ɏ��g�ݎn�߂����Ǝv���܂��D
�E��̐�y����l�X�ȐE��̃��[�����������C�����g�ɂ��邱�ƂŐ���t�c�Ƃ����Ǝv���܂����C���������Ў��ł̎В��̌P�����v���o���Ă��������D�o����C��w�̓��������A�E������i���Ёj�̓��Ў��ł̎В��P�������C�l�b�g�Œ��ׂĂ݂Ă��������D
��������Ђ̎В��P�����C�w�E��̃��[�����ꍏ�������g�ɂ��C�Е��ɓ����ő���͂ɂȂ�I�x�̂悤�ȁc�c�C�̂̌������ʼnԉł������ł��|���𒅂āw���͔����C�ł��ł���̉ƕ��ɑ����ɐ��߂Ă��������c�c�x�ƌ����悤�ɁC�V���Ј��̌��E���Z�������悤�ȓ��e��������C���̉�Ђɖ������Ȃ��c�c�Ƃ��l�����������D
��̗�����b�����܂��D
�����O�C����n���s�s�Ŋ����f���ĊԂ��Ȃ����S�������҂̉Ƒ����s�R�Ɏv���C�₢���킹���Ƃ���C�w�v�Č����x���ԈႦ���w�Č����s�v�x�Ɠ]�L�~�X������C���̌��ʎ�x��ɂȂ��Ă������Ƃ��������܂����D
�}�X�R�~���]�L��Ƃ��_�u���`�F�b�N�������[�����������̂Ɏ��{���ĂȂ������Ƃ�����ƊǗ���̖���Ƃ��Ď��グ�ĕ��Ă��܂����D
�F���܂����̎����͎��ɂ��Ă���Ǝv���܂����C�ǂ������c�������Ă��܂����H
�_�u���`�F�b�N����Ƃ������[������点�Ȃ��������Ƃ͖����Ƃ��đ厸�Ԃł����C���ꂾ���ŗǂ��̂ł��傤���H
������̑傫�Ȗ��́C�{�l�̖����̌����@�ւ̏��̂�������菑�������ōs���Ƃ������ԈˑR�̂܂ܕ��u���Ă��������ɂ���Ǝv���܂����@���ł��傤���H
���݂ɁC����������s�ɂ�����k�����̖{�X�ŐH�������Ƃ��C�X�������A�ɗ��܂����D���̎��C�X���͒ʖ�@��Ў�Ɏ��Ɖ�b���C�w���h�����x���܂����D
����C���s�����ʖ���̒����l�Ƃ݂͌��̃X�}�z�Ԃ�QR�R�[�h�̌��������C���`���b�g���C�X�}�z���m�̒ʐM���m�F���ċ��܂����D
��i���Ǝv������ł�����{�ɔ�ׁC�����N�O�܂œ��{����ODA���Ă���������EDI �i�d�q�������j�̕��y���@���ɐi��ł���ɂ��C���̌�����ڂ̓�����ɂ����̂ł����D
���C�w���������v�x�ƌ������t�����s���ċ��܂����C����͓��{���������Ă��鋌�ԈˑR�Ƃ����Ɩ��̎d�g�݂�ς��Ȃ�������Ȃ��Ƃ����w�Ɩ����v�x����ڂ����炵�C�l�̂����ɂ��Ă��܂����낵������p�������Ă��܂��D
�b�͔�т܂����C�_�Ɨp����w�q�y�x�Ƃ������t������܂��D�L���Ȏ���������炷�y����ێ����邽�߂ɔ엿�����N��������܂����C�l�̂ɉ�����r�^�~���̂悤�ɁC�앨���K�v�Ƃ�����ʂ̃~�l�����͔엿�Ƃ��Ă͗^����C�������앨�ɋz������y�납��͔N�X�����Ă����Ă��܂��܂��D���̂��߂ɎR�y�ȂǁC�~�l������L�x�Ɋ܂��ʂ̏ꏊ�̓y�𓊓��������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��D
���b�������ɖ߂��āC���{���\����悤�Ȋ�Ƃ̎В��́C�V���Ј��Ɍ����Ă̌P���ł́C��ɏq�ׂ��w�q�y�x�̔@���C�w�a���ē������x�C�g�D���y�Ƀ~�l�������[���邪�@���C�V�N�Ȋ��o�ʼn�Ђ̋Ɩ������߁C���_�����C���s�������ꂸ���v�Ɍ����ăh���h�����킵�ė~���������|�̓��e�ɂȂ��Ă��܂��D
���������܂��ƁC��ɏq�ׂ������f�ł̃~�X�̂悤�ɁC�w����͂ɂ����̂����x�Ⴆ�wFax�x�Ȃǂ�����C�w����EDI�����o���ċ��Ȃ��̂��x����Ƃ��Ď��グ�C���̖����������甃���ďo�ĊW������������C���v�𐄐i���饥���D����Ȏp����Ђ�Top �͊��҂��Ă���̂ł��D
����Top�̊��҂ɉ�����ɂ͂ǂ�������悢���c�Ƃ����ƁC�V���Ј��͓O�ꂵ�Ď��͂ɐl�ɁC�����݂̎d���ɐi�ߕ��ɂ����w���́H�Ȃ��H�i�[�HWhy�H�c�x�ƁC�[���ł���܂œO��I�Ɏ��₵�Ă��������D2�N�Ԃ���͏o���Ȃ��C�P�N�ڂ����̓���������ł��D
�w���́H�Ȃ��H�i�[�HWhy�H�c�x�̎���Ŕ[���ł���C��Ђ̎d���̎d�g�݂�������C�o���o�������悭�d�����o�����b�m�����g�ɂ������ƂɂȂ�܂��D
�w���́H�Ȃ��H�i�[�HWhy�H�c�x�̎���Ŕ[���ł��Ȃ���C�������������̂��w���Ȃ��̎d���x�ɂȂ�܂��D�����i�ɋ�\���āC���̖�����������d���Ɏ��g��ł��������D
��i�����ӂƂ��镪��̎d����S�����邱�Ƃ́C�����ɂƂ��Ắw�n���x�ł��D��i�́w���ߍׂ���Follow�x�����ĉ��C��i�ɖJ�߂���ɂ͑�ςȋ�J������܂��D
�����\���Ď��g�d���̒��g�́C��i�͕s����ł�����n����Follow�͂���܂���D����v�悵�C���琄�i����킯�ł�����C�B�����������C�d�����y�����Ȃ�܂��D
�����C���͈̔͂ł́C�Г��ł̓g�b�v�̃X�L����g�ɂ����C�v���ɂȂ�铹�ł��D
�g���^�ɉ����鎄�̌o���ł́C�����V�������Ƃ��n�߂悤�Ƃ���ƁC�K���w2-6-2�̖@���x�ɂԂ���܂��D�܂�W�҂̈ӌ����T�ˁw�ϋɔh20���C���ɔh20���C�����[60���x�ƌ����\���ɂȂ�̂ł��D���̐ϋɔh20�������Ȃ��̒���������Ă���܂��D
���̂悤�ɂ��ĉ��v�I�Ȏd����i�߂�ƁC��В���20���̐ϋɔh�i���������ɏ��i����\����j�Ƃ̐l�����o���܂��D
��Бg�D�̒��ł̏��i�E���i�́C���͂����Ō��܂邱�Ƃł͂Ȃ��̂œw�͂���� Top �܂ł�����Ƃ͕ۏ��܂��C���v������i�߂Đ��ʂ��グ�Ă����Ƃ������т́C��Ђ���������ł����Ԃ���d�v������C���̐�含�����������L�Ӌ`�Ȏd���ɏA���C���b��ƍ����������U���ĉ��܂��D
��Ђ� Top �̊��҂ɉ����邽�߂ɂ��C��Ђ𐬒������Ј������ׂɂ��C�����ĉ���莩�����g�����̐�含��g�ɂ��L�Ӌ`�Ȑl����S�����邽�߂ɂ��D�V���Ј��̏��N���w���́H�Ȃ��H�i�[�HWhy�H�c�x�̎�����Ԃ����āC��Ђ̕�������_�����Ԃ�o���C���݉�������Ƃ��납��n�߂Ă��������D
���N�̌䌒�����F��܂��D
2019�N8�� �g��
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
2019�N5��
�w�ߘa�x��@����ɂ���
���O��H���C���B�͖ڏo�x���V�����w�ߘa�x�̌����}���鎖���o���܂����D
���ɂ��ڏo�x�����Ƃł͂���܂��D������@��ɗl�X�ȓ��ʔԑg����������܂������C���ɂ́C�q�ϓI�ɓ��{�̌�����l����Ɗ���̒v���I�Ȗ�������Ă���C���}�ɉ������Ȃ��ƁC�w�M���V���x�w���[�}�x�̂悤�Ɂw���{�x�ɂ��h�������オ�������c�c�ƌ����n���ɂȂ肩�˖����c�ƌ�����|�̕�����܂����D
�����C�i���jJ�R�X�g�������̑�\�Ƃ��āC���}�ɉ������ׂ��ۑ�Ƃ��Ē��������Ƃ����X����܂��̂ŁC���琔��ɘj���������ł��b�������Ē�������ł��܂��D
����ɓ������āC�R��ׂ��@�ւɋ��錤���҂ł���C�w�҂Ƃ��Č��Ђ�����܂����C����Ƃ̎����Ő��ʂ��グ�Ă������̒́C����̑̌���C�������瓴�@�����`�����Ȃ��Ɛ����͂�����܂���D���̘_�@�ŁC�ߘa�̌��ɉ������ׂ��ۑ����Ă��������Ǝv���܂��D
�F�w�ߘa�x�̓v���t�F�b�V���i���̎���ł���
5��3���C94�Ő���������13����̖@�v���C2�l�̑��q�C5�l�̑��C13�l�̑]�����܂މƑ�26�����W�܂��Ď���s���܂����D�A�蓹�C�Ƌ�E�l���������́C���ł͂Ȃ����p�ŏ��N����̎��ɗl�X�ȃR�g�������Ă��ꂽ���Ƃ�C���ꂪ�y��ƂȂ���77�̍������C���M�������Č�����P��E��Ǘ����v�̂���`�����o���Ă��邱�Ƃ����ӂ����̂ł����D�ڍׂ��y�G�r�f���X�|1�z�Q��
�w�e�ɋ������Ĉ�c�x�Ƃ������t����̕���E���A�z����܂��D�ޓ���2�����畃�e����|���d���܂�C3���ɂ͏�����݁C�̕���Ƃ����|�̓`���҂ł���Ɠ����ɖ��D�Ƃ��Ĉ�Ă��Ă����܂��D�y�G�r�f���X�|2�z�Q��
�t�@���Ƃ��Č���ƁC�ޓ��͉i���`����w�����Ă��āC�e�E�q�E���ƉƑ����o�Ŏŋ�������Ă��܂�����C�˂ɒ����I�Ȏ���Ń��m�����Ă��܂��D�̕���E�ɕ��������Ă��������ł͉̕���́w���W�x�ǂ��납�w�`���x���o���Ȃ��ƍl���C�f���e���r�C�~���[�W�J���ɂ��o�����C������̕���Ɏ��g�ނ��ƂŔɉh���ێ����Ă��鎖��������܂��D
�̕���ȊO�ł��C�|�\�E�ł͉̎��o�D�̎q���B���C�e�̌��p�����Ĉ炿�C���ɂ͐e�̎w�����ē����ƊE�ɎQ�����C�听���Ă���l���������܂��D
�X�|�[�c�ɖڂ����C�e���������ċ�����ƌ������C�c�������猵�����P���ō˔\��L���C���E��Ɋ���I�肪�o�Ă��܂����D
�싅�ł͕������I�肪�c�C�t�B�M���[�X�P�[�g�ł́C��c�^���I�肪�撣��C�ޏ��B�Ɏh������Ⴂ�I�肪���X�ƈ���Ă��Ă��܂��D
�����Z�ł��C2020�N�̓����I�����s�b�N�Ɍ����đI��̈琬�����ɏ��o���C���̐��ʂ��������C�{���y���݂��Ƃ���������܂��D���Ɍ��\�Ȃ��Ƃł��D
���̈���Ŏ��ƊE�ɖڂ����ƁC����ƈ���āw�����x�̌��ɃY���Y���ƌ��Ă����Ă����w�s�s���Ȍ����x������܂��D
����������k��C���̌����ڂ������b�����܂��傤�D
���a�̌��ɐ푈�ɔs��i1945�N�j�œy�Ɖ��������{���C��l�̓w�͂ŕ������Ă����C�悸�w�@�ۋƊE�x���C�p���Ńe���r�Ȃǂ́w�Ɠd�ƊE�x���C������1980�N�ɂ́w�����ԋƊE�x�܂ł����C�폟���Ő��E��̍H�Ƒ卑�ł���Ǝ��F����č��ɗA�o�U�����|���C�w���Ėf�Ր푈�x�Ƃ܂Ō�����悤�ɂȂ�܂����D�������wJapan as No.1�x�ƌ����o�u���ɐ����L���V�ɂȂ��Ă�������ł�����܂����D
�����̌��i1989�N1��8���`�j�ɂȂ��ĊԂ��Ȃ����j�I��ϊv���N���܂��D����́C�\�A�����i1991�N12��25���j�C�č��̒P�Ɣe���̐��i1992�N�����`�j�ɂȂ������ł����D���̎��_����C�O���[�o�����Ƃ��w������v�z�ɂƂ���Ȃ����R�f�Ձx�����łȂ��w�o�ρE�����E�Љ�ȂǁC������̐���č��^�ɕς��邱�Ɓx�Ƃ����Ӗ������킹���悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����D
���̎����C���Ɠ��N��̌o�ϊw�ҁE���J�ޔ��m���w�O���[�o�����Ƃ́C�Ⴆ�Č����C���̉^����ɑ����̍�����I�����s�b�N���̑I�肪�Q������悤�ɂȂ邱�Ƃ������x�Ƃ�������������Ă����L��������܂��D�����ꂽ�n��o�ςł���C�ǂ�ȏ����ł��펯�I�Ȋ����ł��������ׂ���̂ł����C�O���[�o����Ƃɂ���āC���E�K�͂̃}�[�P�b�e�B���O����J�����ꂽ�w���͓I�ȏ��i�x���C��ʐ��Y�ɂ�����w�����ɖ��s���Ɂx���������C�n���Ƃ͂ЂƂ��܂�������ł��낤�����ƌ����Ӗ��Ɨ������܂����D
�Ă̒�C�I�����s�b�N�����_�����̌o�c�҂̃O���[�o����Ƃ̍U���ɁC�h���X�`�b�N�o�c�҂̓��{��Ƃ͎s���D���C�|�Y���������܂����D���{���\������Y�����Ԃ������������J�肪�������Ȃ胋�m�[�ɍ~��i1999�N�j�H�ڂɂȂ��Ă��܂����̂ł����D
���m�[���珕�l�Ƃ��Ĕh�����ꂽ�����_���X�g���̌o�c�҃S�[�����ɂ��C���Y�͐��N�ŗݐϐԎ������������C������V���𐬂��������c�Ɛ�^����鎖�ԂɂȂ�܂����D
����������C���{�l�o�c�҂��w�\�́x�ɋ^�╄���ł����悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂ł����D
���̍��C�w���̂����w�x�̋������Ԃ�������c�������́C�o�c�҂�Ǘ��ґw�ɑ��ėL���ȃh���b�J�[�����̒����C�w�v���t�F�b�V���i���̏����x�C�w�`�F���W���[�_�[�̏����x�C�w�C�m�x�[�^�[�̏����x�C�w�}�l�W�����g�x�C�w���H����o�c�ҁx�C�w��ƂƂ͉����x�C�w�e�N�m���W�X�g�̏����x����2000�N����2005�N�̊Ԃɖ�p�����ɏo�ł��C���v�𑣂��Ă��܂����D
���̂悤�ȁC�o�c�w���������ڂ���Ă��鎖�ԂɈ�a�������������䐒�j�����w�Z�p�ҁx�̏d�v����i���C�����w�u�^�����g�v�̎���x�i2015�N�u�k�Ёj�̒��ŁC�w�O���[�o���Ȏs��ŏ����i�ނ��߂ɂ́C���i�v���̐S�ł��邱�ƁD���i�v�̓^�����g�i�ٔ\�̐l�j�ɂ����ł��Ȃ��̂ŁC�X�|�[�c�E���I�������悤�ɁC���i�J���ł���Z�p�҂��W�߁C�琬���C�R��ׂ�������^���鎖�Ŋ�Ƃ��������ׂ��c�x�Ǝ咣���Ă��܂��D�܂����������ł��D
�ŋ߁C���{�d�Y�̉i�����w��w���ƌ����Ȃ���������\���ǂ߂Ȃ��o�ϊw������C���[�^�[�̖͌^�����Ȃ��H�w���������饥���C�x�ƒQ���āC��w���v�ɏ��o���ƌ����L�����������Ƃ�����܂��D
����Ɍĉ����Ă��C��Ƒ������v�Ɏ��g�ދC�z�������C���̑����Ƃ��āC�o�c�A�̒�������w�V�����̗̍p�̂�����ς��饥�c�x�Ƃ�������������܂����D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����́C�]���̂悤�ɑf�ނƂ��ĂS���Ɉ������C���ňꊇ�̗p���C�Г�����Łw���А�p�̃x�e�����x�Ɉ�ĂĊ�����ƌ����w���{�^�̗p���x�x����C�����C����͂ƂȂ�l�ނ��C�\�͂Ɍ����������^�ō̗p����Ƃ������Č^�̗p���x�Ɉڍs����Ƃ����Ӗ��������܂��D���ꂪ���[�ɂȂ��āC��w������͂ɂȂ鋳��̌n�ɕς���Ă����Ǝv���܂��D
�����w��ƂƑ�w�̐l�ވ琬�Ɋւ���ۑ�x�ɂ��ẮC����������������������܂����C����͎���ȍ~�ɏ����āC����͓y��ƂȂ�c�������班�N���ɂ�����l�ވ琬�ɂ��Ă̂��b�������܂��D
�����͈ȉ��̂悤�Ȓ�v���܂��D
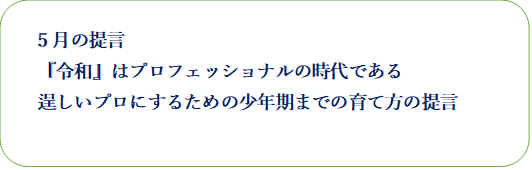
- ���ƊE�ł��C�X�|�[�c�E��`���|�\�̐��E�̂悤�ɁC�c��������v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ĉ�Ă��w�l���x�ƁC��ʋ��{������g�ɂ����w�l�ށx�Ƃ��w�s�ʂ���鎞��x�ɂȂ饥���D
����́C�e�͉䂪�q��L���Z�i��ʋ��{�j�ɓ����ƌ����I����E���C�w���̃v���t�F�b�V���i���ɐ��肽�����{�l�̈ӎv�x�d���C�x�����邱�Ƃɐ�ւ���ׂ��ł���D�y�G�r�f���X-�P�z�Q�� - ���N���܂łɏo���������́C�܊��Ŋw�Ԏ��̌��������C�w���ۂ́g�^���h�𗝉������b�̌��x��g�ɒ����邱�Ƃ��̗v�D
���ꂪ�����ď��߂Ď��Љ�ł́w���t�ɂ����x����ł��w���ۂ̐^�̗����x���ł���悤�ɂȂ�D�y�G�r�f���X-�P�C-�R�z�Q�� - ���N���ɉ����厖�Ȃ̂́C�g�����l�ԊW�ł���D���Ɂw���e�x�Ɓ@�w�Z�M�i�o�j�I���݁x���傫�ȉe�����y�ڂ��D�y�G�r�f���X-�P�C-�Q�C-�R�z�Q��
�y�琬�̉���z
���̂悤�ɕ��͂ɓZ�߂܂��ƁC�w������O�̂��Ɓx�������Ă��鎖�ɂ��C�Â��ł��傤�D���́C�w�����̌��x�ł͂��́w������O�x�������Ă��������Ƃ����Ȃ̂ł��D
�悸�w������O�x�̕K�v�����w�i���̗��j�x�ƌ������ʂ���������܂��D�a������46���N�o�����n����ɁC�w�Ғœ����x���a�����Ă����5���N�C�w�M���ށx���a�����Ė�2���N�C�z���E�T�s�G���X�i�q�g�̑c��j�a�����Ė�20���N�o���Ă���Ƃ����Ă��܂��D
�Ԃ�����܂��Ƃ��C��e�̎q�{�̒��ŁC�w1�̎��x���זE������J��Ԃ��C�ŏI�I�ɂ��w37���̍זE�x����\�������l�̂ɂ܂Ő������Ă����܂����C�q�{�̒��ł����ˑ��זE�ːҒœ����˗����ށ˚M���ށːl���ƁC�����̗��j�����Ȃ����Ă���5���N���̐i�����g���[�X���Đl�Ԃ̐Ԃ����ɂ܂Ő������ďo�Y���}����Ƃ����܂��D
���܂ꂽ������Ԃ����͖_�ɂԂ牺�������Ƃ��o����قǂ̈��͂�����܂����C�Ƃ��C�ɂ݂�������������x��������\�͂͂���܂���D�w�i���̎ړx�x�Ō���C20���N�O�́w�z���E�T�s�G���X�̏�ԁx�Ƃ������܂��D���̏�Ԃ���g�D�I�E�����I�Ɍ���ɒʗp���郌�x���܂ň����グ��̂��C�w���N���܂ł̈琬�x�̖ړI�Ȃ̂ł��D
�w�p�\�R���x�ł���C�����Ă������̓}�b�T���ȏ�Ԃł����C�w�v���O�����i�f�W�^���j�x���C���X�g�[�����C�K�v�ȃf�[�^�[��ǂݍ��܂���ΐ����Ԃŋ@�\����悤�ɂȂ�܂��D
�������C�Ԃ����́C�G���āC�Ȃ߂āC�����āC���āc�܂�܊����g���ẴA�i���O�f�[�^�݂̂ŊO�E�����m���C�]�Ɏ�肱�݁C����A�i���O�E�R���s���[�^�[�v���O������]���ɍ��Ȃ���C�e������ڂ��Łw���t�x���o���Ă����܂��D
���t�������C�����ł���悤�ɂȂ�ƁC����Ɂw����x�����܂�Ă��܂��D
�w�Ă͓c�ނ���l���x�w�����͎\�̖�����a���x�ƌ����悤���w���́x���o�������C�ʎ��œ��ėp���ɏ�����C�w�āx�Ɓw�����x�́w�w�K�x���o�����c�ƌ�����C��������s����̂��w���x�̐��̂ł��D���́w���͂ŏ����ꂽ���i���m�̎����j�x�𐔑����L�������l�i�X�}�z�ʼn��ł������o���錻��ł͉��l������܂��c�j���C�푈�������������w�G���[�g�x�Ƃ��ėv�E�ɏA���C�w���J�̕�����J���c�x�Ƃ����Ƃ͐^�t�̖�����S���Ă����������C���{�̉e�������Ȃ��Ă������v���̈�Ǝ��͍l���Ă��܂��D
����w�c���x�ł́C���N�����Ƃ��ēV�c����c�A�������C�������܂��D�c�@�͎���\����āC�o��������a���Ő��������ƌ����܂��D���̈Ӗ��̉��߂͊F���܂ɂ��C�����܂��D
�����g�̏��N����̑̌����y�G�r�f���X-�R�z���Q�Ƃ��Ă��������D
�g���^�����Ԃɂ��w���n�����x�Ƃ����w�N�w�x������܂��D�n�ƎҊ��Y�����w1���ɂR��ȏ�Ό��Ŏ����Ȃ��Z�p�҂͗v��Ȃ��x�Ƃ������t���C�w���n�����x�̒[�I�ȕ\���Ƃ��đS�V���Ј��������܂��D���̌�Łw�����Ƃ������ɂ��܊����瓾�����݂̂�����ɂȂ����炾����x�Ɛ�������܂��D
�L�c�Ƃ̓`�L��ǂނƁC���g���ˊ��Y���ˏ͈�Y���ˏ͒j���i���В��j�Ƒ�X�C���N����ɕ��e���p�����āw��Ɖƍ��x��w�鉤�w�x�����p����Ă����l���`����Ă��܂��D�p�����w�N�w�x�̈���w���n�����x�ƌ䗝�����������D���̓`�����g���^���̈�̗v�f�ł���ƌ����܂��D
����̎��̒m�P�n�C�m�Q�n�C�m�R�n�̐^�ӂ����������ł��傤���H
���q�l�₨������̋���̎Q�l�ɂȂ�K�ł��D
�ȉ��C�Q�l�ɂ����w�G�r�f���X�x���L���܂��D
�y�G�r�f���X�|1�z���̔w�����狳���������
1913�N�M�B�ɐ��܂ꂽ���͒��t������ē����Ƌ�E�l�Ƃ��Ă̘r�𗊂�ɏ㋞���C���͂œ���ɓX���\���C1940�N�̋�����ł��}���C�������܂�C���ꂩ��c�ƌ����Ƃ��ɏ��W����C��͎���A��ĐM�B�̎��Ɓi�R���̑�S���j�ɑa�J���܂����D
-
�I�헂�N�����������́C�����̑q�ɂ̈ꕔ����C���Y�͑�H������Ƃ�����Ԃ��玖�Ƃ��ĊJ�����܂��D�c�ɂł͉Ƌ���ł͔т��H���Ȃ��̂ŁC���͖ؐ��̎�s����Ǝ��ɍl�Ă������̔����܂����D
�Ԃ��Ȃ����ւ̖،˂��K���X�˂ɕς��铙�C���������|���n�߁C�₪�Đ������P�̎����ɏ��C�䏊�╗�C��̉��z���n�߂܂��D�X�Ɏ��͂ō�����h�t�̋Z�p���}�X�^�[���C���́w���ł����x�ɐ����Ă����C10�N��ɂ́C�E�l2���C�Z�ݍ��݂̒�q1���������܂ŏ������L���Ă����܂����D�i�N�ƉƂƂ��Ă̑��ʁj
-
���͌������d���܂ꂽ�E�l�ŁC1���̏I���ɂ́C�d����͑|�����߂��C����ނ͂��̓��̓����������Ē�ʒu�ɕЕt�����������g�����Ԃɂ��ċ��܂����D�E�l����ҁC����͎����ō��ׂ��Ƃ��C��30��ނ���������ɂ��Ă��܂����D�i�E�l�Ƃ��Ă̊�{�p���j
-
�فX�Ɠ������̔w�����d���������̒��Ŗؐ�ŗV�тȂ��猩�Ĉ�������́C�؍H�Ɋւ����b�m�����C�w��O�̏��m�K��ʌo��ǂݥ����x�I�ɐg�ɒ����C�����������ŋ�����|���̏�艺�肪������悤�ɂȂ�܂����D�i�����̓`���j
-
���w���̍��́C�o���オ��������m���_���X�������J�[�ɍڂ��ē͂��C��������n���Ă���̂���ڂŁC���i�����̌��_��̌����܂����D���̓���������ƁC����������i�����C���͍ޗ��̎d����ɍs�����肵�C�o�c�ɉ����������J��̉����邩�̌��̌������Ă��܂����D�i��ƌo�c�̌��̌��j
�y�G�r�f���X-�Q�z�̕���E�ŋ߂̏P��
- 2019�N 1��14��
- �s��C�V����13��ڎs�욣�\�Y�������P��
- ���j�E�����i2013�N3�����j��8��ڎs��V�V�����P��
- 2�ŏ�����C6�ŐV�V��
- 2019�N 1��
- ���{�K�l�Y��2��ڏ��{���_���P��
- ���j�G�s����ܘY��10��ڏ��{�K�l�Y���P���i43�j
- ���@�G���{�����Y��8��ڎs����ܘY�i11�j���P��
- 2017�N 2��
- ��������Y
- ���j�@�������@��3��ڒ��������Y�i5�j���P��
- ���j�@�N�V�@��2��ڒ������O�Y�i3�j���P��
�y�G�r�f���X-�R�z���̏��N����̑̌�
-
���w�Z�ɂ�����܂ŁC�R���̑�S����������̎��Ƃɑa�J���Ă����̂ŁC���C����͖ܘ_�̂��ƁC�n����{�܂ł̉ƒ{�̐��b�C�Y�Ă��E�Ċ���E����R�؍̂�Ȃǂ̎R�d���C�{�\�E�����C���X�E�ݖ��E�ǂԂ낭����܂ł̔_�R���̎d����̌����邱�Ƃ��o���܂����D�����Ă��ꂽ�͕̂�̒햅�ł����D���ɂU�ΔN��̏f���́C�Z�̂悤�ȑ��݂ł悭�ʓ|�����Ă���C��̎��Ƃ̑�Ƒ��̖����q�̂悤�Ɉ�Ă��܂����D
-
���w�Z����́C����ƂU�Ή��̒�ƁC���K���E�lA����̂T�l��炵�ł����D��͈ߐH�Z�S�Ă̖ʓ|������w��������x�Ƃ���A����ɐڂ��ċ��܂������C�H�����́w�������x�̑傫���͇@���C�AA����C�B�Ƒ��̏��ł����D�Ƒ����]�ƈ����ɂ���Ƃ������{�I�o�c�̌��_�Ŋw�т܂����D
-
�킪�c�����ɓ���ƁC�_�Ɋ��ɂ͕�͋ߏ��̔_�Ƃ̎�`���ɍs���悤�ɂȂ�C���̎��̌ߌ�̋x�e���Ԃ̂����o���ƁC�ꂪ�������Ēu�����ޗ����g���Ă̗[�H�̎x�x�́C���̎d���ɂȂ�܂����D���̎�����n�܂����w�j�q�~�[�ɓ���x�K���͂��̌�C�q�C���܂ő����Ă��܂��D����Ԃ����w�j�������Q��x�ł���C���B�v�w�Ƒ��q�v�w�ɓ`����ċ��܂��D
-
���w���̎���C�T�C�قǎ����Ă����e�̐��b�͎��̓��ۂł����D�����C�y�肩�瑐�������Ă��āC���������߂��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��C�a�Ƃ��ė^���Ă��܂����D�킪���w�Z�ɂ�����Ƃ��̎d���͒�Ɉڂ�܂����D���̎��C�L�`���Ɠ��ۂ����Ȃ��^�����ړI�������̂��ƕ�����܂����D
�`�ȏ�`
2019�N5�� �g��
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
2019�N2��
�G�߂̌䈥�A
��N�́C�����J�P���Ƃ��āC�����Ȃ╶�ȏȂ̖�l�̜u�x��C���Ȍ��͂����e�Ȓ��̖�l���Ǘ��o���Ă��Ȃ���b���b��ɂȂ��Ă��܂����B���N�ɂȂ��āC�V���Ɍ��J�Ȃ̋ΘJ���v�̕s�����������炩�ɂȂ�C�X�ɑ����̓��v�����ŕs�����s���Ă����l�q�ŁC���̋L�����ǂ܂�Ă��鍠�̍���ł͘_��̐^�Œ��Ǝv���܂��B
�����`�̍����ɂ���i�@�E���@�E�s���̎O���������C���݂̓��{�̋c�@���t���ł́C�ő��h�̓}���t������b�ɂȂ�C�^�}�c���ɂƂ��čs���������Ƃ������Ƃ́C�}��⒇�Ԃ��U�����邱�Ɠ��Ӌ`�ɂȂ��Ă��܂��܂��B���̌��ʁC���匠�͂��������s���{�̑ǎ�肪�S���Ȃ��Ȃ�C�w��l�́C��l�ɂ��C��l�̂��߂̍s���x�ƌ����A�����������悤�ȏ�ԂɂȂ��ċ���̂ł��B
�s���̍����Ɋւ�鍡��̖��́C�^�}���ʼn߂ł��Ȃ����ł��̂ŁC�s�����������鍑��{���̖�ڂ��ʂ����Ă���邱�Ƃ����҂��������̂ł��B�����āC����̕s�����������C���ꂪ�������������͉����C10�]�N�Ԃ������ꂸ�ɍ����܂ŗ��Ă��܂����̂́C�����@�\�̉����ɂǂ̂悤�Ȍ��ׂ�����������Ȃ̂��C�^����Nj����C�Ĕ��h�~�ׂ̈̐V�����@���𐧒肵�Ă̖������ɂ��Ăق������̂ł��B
�X�ɁC�e���r��ʂŌ������C����̒����́C�w�p���x������w�菑���x�ɂȂ��ċ��܂����BICT�Ƃ�IOT�����v�̖ڋʂƂ���Ă��鍡���C�w�菑���x�ŏW�߂��c�d�s�`�ɂǂꂾ���̏��ʂƐ��m��������Ƃ����̂ł��傤���H�����ǂ̊�Ƃł����^�v�Z�͂d�q�o�ōs���Ă�����Ԃ��l����ƁC�R���s���[�^�[���́w���c�d�s�`�x�����o���̂��œK�̒����@�ł���Ǝv���܂��B���@���s���ł������ƌ����_�_�Ɠ����ɁC�����p���Ɏ菑�������o�����C���������͂ŃR���s���[�^�[�ɓ��ꋋ������𐄒肷��Ƃ������@���̂��̂��C�w���a����̈╨�x�ł���C��i���E�������x��ɂȂ��Ă��鎖���}�X�R�~�Ŏ��グ���C�s����@�̒x�ꂻ�̂��̂��c�_����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�s���̂��Ƃ���������܂������C�w��̍D�ނƂ���@���������畗���Ȃ��x�ƌ������t�̂悤�ɖ��Ԃł��C���{���\����悤�ȑ��Ђł��s����肪�������Ă��܂��B���{�I���y�̑�g�D�Ƃ����_�ł͍s�������Ԃ̑��Ђ��C��������Ƃ��₷�����������o�����̂ł́c�Ƃ����������l�����܂��B
���Ђ́C���ӂƂ���̂͐�������ł����C������̔����܂߁C�����𐋍s���Ă��邠����E��́w�Ɩ����v�x�̂���`���ƂƂ��Ă��܂��B
���̗��ꂩ�猩���ꍇ�C�����̍s���Ɩ��ԑ��Ƃ��s�����s�����v���̓��ЂƂ��Ẳ����������������������܂��B���̉�������ɊF���܂̉�Ђ̌�������m�F���Ē����C�����ɗ��Ă�K���ł��B
�ǂ����Ă����ۓI�Șb�ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁC1995�N�����S���̔��Ⴂ�̐������傩�畨���Ǘ������Ƃ��ĕ��C�����Ƃ��̌o������ɂ��āC��L�̕s���h�~�Ɍ������g�ݕ��i���Ђ̉����j����������܂��傤�B
�y����-1�z�Г��Ɍ��ƐE�ꂪ����A���Ԃ�c���ł��Ă��邱��
���C�������A�����Ԃ�S���E�̔̔��X�ɓ͂����w�ԗ��������x�C���E���ɓ_�݂��Ă��鎩���Ԑ��Y�H��ɕ��i��͂����w���Y���i�������x�C���E���̒ÁX�Y�X�ɂ���C���H��ցC�C���p�̕⋋���i��͂����w�⋋���i�������x������܂����B���ƕ��̂Q���͎Г��Ɏc���C�Ǘ��̃m�E�n�E���p�������C���͉�Ђ��w������͂��ێ�������c�ƌ������ψꎁ�̈�P����������Ă���C��L�����O���ɂ͒��x�̍��͂���܂������C�w���ƕ����x������C�����̊ē҂̈ꕔ���C�v�X�̋��͉�Ђ̌����Ƃ��ē��ĉ���Ă��܂����B���ʂƂ��āC�g���^�Г��̌��ƐE�ꂪ���f���ɂȂ�C���{�����݂̂Ȃ炸�C�S���E�̌��ƐE��̎��Ԃ�c�����Ă��܂����B
�y����-2�z�������������邱��
��L�����O��������`�Łw�����Ǘ����x������܂����B�����̏�ł͕����O���Ŏ����͂��Ȃ��Ă����܂����C���̃R������2016�N1���Ɂw�C�͎O�{���ň��肵�Ă��邪�C���͉��̎l�{�̑�������̂������x�̂Ƃ���Ō�������܂����悤�ɁC�g���^�ɂ͊Ǘ��Ɋւ���Ǝ��̍l����������܂��B�����O���̗v�����M���M���܂ō팸�����C���P���Ȃ��Ǝ|�����Ȃ��i���P��Needs����j��Ԃɂ��C�X�ɕ����O�����ŏd������Ǝv����Ɩ���1�J���ōs���悤�ɁC�����O������D�G�Ȑl�ނƋƖ����w�����Ǘ����x�ɏW�߂Ēu���C���L�̂悤�ȋ@�\���������Ă���܂����B
- �@�\-1�@�����e���̓Ƒ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɋƖ���Check����
- �@�\-2�@�S���E�̕����Ԃ�Check���C���P�ǂ�g�D���⋭���ĉ��
- �@�\-3�@�V�K�i�o�n��ł̐헪�I�����Ԃ̍\�z
- �@�\-4�@�o�c�{���ւ̕����헪�̒�ĂƑg�D�I�W�J
�y����-3�z�Öْm���`���m�ɂ��Ē~�ς��Ă��邩
���C���āC�������烌�N�`���[���ċ������̂́C�w�f�Ձx�Ƃ����Ɩ��̕��G���ł����B
�����Ɋւ��邱�Ƃ͍����ȁC�H�Ɛ��i�͌o�Y�ȁC����ޗ��ɖ؍ނ��g���Ɣ_���ȁC�Ǝ҂Ƃ̊W�͌��J�ȁC���X����ɘj��C�������C�@�������łȂ��ȗ߂�ʒB���C�l�X�Ȍ`�Ŏ��ׂ����[�������X����C�e�Ȓ��Ԃōׂ����������ꂽ���̂ł͂Ȃ��C����Ŏ{�s���钆�Ŏ����Ɛ���������Ă��āC�@����ǂ�ł������͗����ł�����̂ł͂Ȃ��C����̊���Ƃ��Ăǂ̏�ʂł͂ǂ�����c�ƌ��������m�ɂȂ��ċ���ƌ����������܂����B���̂��߂ɖ@����p��̐��������Ŗ����C�g���^�Ƃ��Ă̎��g�ݕ��܂ŏ��������w�f�p��W�x�������B�ŕҎ[���C���E�̏��Ƃ��Ċ��p���Ă���̂ŁC������������悤�ɂƕ�����1����n����܂����B
����ŁC���P�̐i�ߕ��ɂ́C���P�}���̑_�����܂��܂��ł����B�����ŏ�i�ł��镨���S�������̗������o���w�g���^���Y�E���������iTOYOTA�@Logistics�@System �j�x�ƌ������̂ŋ��ȏ����܂Ƃ߁C�p���ɖ|�đS���E�̕������_�ɔz�z���C�g���^�̑S���E�K�͂̕����l�b�g���[�N�������ڕW�Ɍ�������KAIZEN��i�߂�̐������܂����B
�y����-4�z��芪�����̕ω������m������Ԃ������Ă��邩
�����قǂł͖������̂́C���{�̊����@�\�͌l�Ƃ��Ă̍ٗʂ��F�߂��Ă��āC����ٓ����Ɏ����܂�̏d�_�Ƃ��̃��x��������Ă��܂��B�����̏��͊����ǂނ����ł͎��W�ł��܂���B��������̂��ߍׂ��ȏ����^�C�����[�ɓ��肷�邽�߂ɁC���̎��̕����Ǘ����ɂ́C�������N�ފ����ꂽ�����Q�^�Ƃ��ċΖ����Ē����ċ��āC�����F�X�����Ē����܂����B
�ŐV�Z�p���̎��g�݂ł́C�����Ǘ����������ɂȂ��āC�����Ȃ��i�߂�ETC�̎��p���CETC�̑��ʓI���p�̎��؎����ɎQ������ȂǁC��Ƀg�b�v�����i�[�ł�����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă��܂����B
�y����-5�z��Ɏ��E��̋Ɩ����v�Ɏ��g��ł��邩
1995�`1999�N���̓g���^�̐������ł��������߁C�ȉ��̂悤�ȐV�KProject���ڔ������ł����B
- �@ �x�g�i���H��
- �A �����V�ÍH��
- �B �ăC���f�B�A�i�H��
- �C �ăE�G�X�g�E�o�[�W�j�A�H��
- �D �������t�H��
- �E �C���h�H��
- �F �t�����X�H��
- �G �����l��H��
- �H �|�[�����h�H��
- �@�@���X
�Ɩ����P�ł�
- �p������Order-to-Delivery-Lead-Time�Z�k����
- �����J���|����Order-to-Delivery-Lead-Time�Z�k
- �A�o�p�̖ؔ�����C��R���e�i��
�����ɓW�J���Ă��܂����B
����ɁA���͉�Ђ̉��P������W�J���Ă��āA�g�b�v����̈˗��̋Ɩ����v�͖����ōs���A�w�������匤�x�Ə̂�����P�}���̌��C��ł́A���N�̉��P���ʂ͋��͉�Ђ̂��̂ƂȂ�A���N�x�͋��͉�Ђƃg���^���ܔ�����Ƃ�����茈�߂ɂȂ��Ă��܂����B���P���邱�ƂŐl���炿�A���v���オ��̂ŁA���C���ӂ��E��^�p�ɂȂ��Ă����̂ł����B
�܂Ƃ߂�Ɖ��L�̂悤�ɂȂ�܂��B
- �y����-1�z�Г��Ɍ��ƐE�ꂪ����A���Ԃ�c���ł��Ă��邱��
- �y����-2�z�������������邱��
- �y����-3�z�Öْm���`���m�ɂ��Ē~�ς��Ă��邱��
- �y����-4�z��芪�����̕ω������m������Ԃ������Ă��邱��
- �y����-5�z��Ɏ��E��̋Ɩ����v�Ɏ��g��ł��邱��
�����̗v���͂����܂ł����Ђ̉����ł����A��Ђ͎��Ђ̊e����̃m�E�n�E�̈ێ��Ǘ��̂��߂ɂǂ̂悤�ȕ�����u���Ă���̂��H���ꂪ�L�`���Ƌ@�\���Ă���̂��H�@�_�����Ă݂Ă͂������ł��傤���B
2019�N2�� �g��
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
2019�N1��
��\�V�N�̌䈥�A
�����܂��Č�ڏo�x���������܂��B
���Ђ̖{�N�x�̖ڕW��
�i�P�j�w�{���g���^�����x�w�i�R�X�g�_�x�̕��y�ɓw�߂܂�
�i�Q�j�V�i�̉�v�w�҂Ƌ��Ɂw�i�R�X�g�_�x�̐i�������܂�
�i�R�j���͂��̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ����܂�
�Ƃ��܂����B
�{�N���������̒������肢�v���܂��B
�V�N�ɓ������Ă̏�����\���グ�܂��B
���U����̃e���r�����ł��C�������N���ɂ��w�����Ō�̥����x�Ƃ������t�������Ă��܂����B
������e���r�ł͏H�{��
�w���N����Ă�����̍s��������ƌ����āC�����l�����ɐ��ɖӏ]����̂͌��ł���B���ׂ̈̍s�����H���̂����ł悢�̂��H����ᖡ���Ď��g�ނׂ��ł͂Ȃ����H�x
�Ƃ�����|�̌䔭���̕���������܂����B
���̏H�{�̌䌾�t���C���̋��ɋ����܂����B
�ƌ����̂́C���ɂ͕�����30�N�Ԃ����̂Â���̂������o�u������̖ӏ]�ŗ��Ă��܂��������������C���P�ƂƂ��Ă��镾�Ђ��猩��Ǝ���ꂽ���Ԃł������Ɗ����Ă��邩��ł��B
�ǂ��ł����|����悤�ɁC���o�V���Ɂw�J�C�[���������d���x�ƌ����L�����ڂ�
�w(1)���̃n���R�C�K�v�ł����x�w(2)�q��Đ\���ɂ��ߑ��x�Ƃ���܂����B
���������C�w���������v�x�ƌ���������w�Ɩ����v�x�X�Ƃ��Đi�܂��x�������Ă��܂��B
���{�͔_�ƍ��ŁC�w�����Ȃ���͂Ȃ��x�w�䕗��߂̐��V�x�Ƃ������t������悤�ɁC�ǂ�ȍ���ȏ������Ă��K�����ɖ߂饥��ƐM����S������܂��B
���̐S���������āC1980�N��̃o�u���̎�������_�ƍl���Ă��܂��C1990�N��̕s���C2000�N��̃��[�}���V���b�N�C���X�͈ꎞ�I�Ȃ��̂ŁC�����Ɖ䖝����Ζ����̔ɉh�����o�u������ɖ߂�饥���ϑz�ɋ���Ă���30�N�������ł��������킴��܂���B
���̌��ʁC���ۓI�@�ւ���ȉ��̎c�O�ȕ]���Ă��܂��B
- �J�����Y���@��i7�J���ł͍ʼn��ʁ@OECD36�J����21�ʁi2017�N�j
- �j�������x�����L���O�C144�J����114�ʁi2017�N�j
- �̎��R�x�����L���O�ł́@180�J����72�ʁi2017�N��p�؍��ɔ������j
���Ђ̖{�Ƃł���w����̈ێ��E���P�x�ł��b������C�J�����Y�����Ⴂ���Ƃ��C�ɂȂ�܂��B�ڂ����͌㔼�ł��b�����܂����C�悸�͑g�D�̈���Ƃ��Ċ��Ă���F���܂́C��ɏЉ���H�{�̌䌾�t���䂪���Ƃ��ċ��ݎ��C���Ђ́H�����́H�䎩���̂��d�����q�ϓI�Ɍ������Ƃ��납��͂��߁C�N�����ς�邱�Ƃ��@�ɁC���������v�ł͂Ȃ��C�Ɩ����̂��̂̉��v�Ɏ��g�ނ��Ƃ����E�߂��܂��B
�y���{������n�ɂȂ��Č��������R������Ђ̍l�����z
1989�N����2019�N��30�N�Ԃɐ��E�̂��̂Â���͂ǂ��ς�������C���Ђ̑������́C���L�́y�`�z�y�a�z��S���E�œW�J���Ă��������C���{�����͕s���S�R�Ă������Ƃ������̂ł��B�ȉ��~���E�܂�Ő\���q�ׂ܂��B�����܂ł������ł���C�����ɉ߂��܂�����
���E�I�ȕϊv�̈��1980�N�̓��Ď����Ԑ푈�ɂ���܂��B�����̃��[�K���哝�̂ɂƂ��ẮC1945�N�ɓO��I�ɏĂ��쌴�ɂ��C���̌�10�N�Ԑi���R�i�p��ł�Occupation Army�j�ɂ���āC�O��I�Ȑ��]���炵�C2�x�ƕĉp�ɏ��˂��Ȃ��悤�ɂ�����Ŏ������������Ă�������{�ɁC�č��̊�Y�Ƃł��鎩���Ԃ��ӂߗ��Ă���͉̂��̂��I�H�@�O��I�ɒ��������ȉ��̓��ނ̌o�c��@���r���𗁂т��̂ł����B
�yA�zFORD���z�����R���x�A�����X�ɔ��W�������g���^���Y�����iTPS�j
�yB�z�č��̃f�~���O���m������TQC
�����̎�@�̂��̌�̓W�J���ڂ�����������܂��B
�y�`�z�g���^���Y�����iTPS�j���牢�Đl�p���wLean Production System�x�����܂�S���E�ɓ`�d���܂����B�f�d�Г����擪����ē����C�����ł��w���v���P�x�ƌĂ�Ă��܂��B���C�C�X���G����Goldratt���m��TPS����TOC�iTheory Of Constraints�j���l�Ă��i1984�N�j�C�X�ɂ����]������Throughput��v��҂ݏo���܂����B
���E�̊w�҂Ɏ���ăg���^���Y�����͐�D�̌����ΏۂŁC�\������v�f���ЂƂ�̎�@�Ƃ��ė��_�t�����C���[�`��������C���ɍL�߂��܂����B
���Ƃ��@�u����ƈꏏ�ɂȂ��ĐV�Ԃ��J�����Ă��������v���wConcurrent Engineering �x�Ƃ��ďЉ��C�u����������Essence�v���wSCM�x�ƂȂ�C�E�����System����͂���u���m�Ə��ɗ���}�v���wValue Stream Map�x�ƂȂ�܂����B�u�V�ԊJ�������O�������d�����āC�ォ���肪�o�Ȃ��悤�ɂ����@�v���wFront Loading�x�ƏЉ��Ă��܂��B�g���^���Y������2�{�̒��̈�u�������v�͂��̂܂��wJIDOUKA�x���̂����́u���P�͖����ł���v�ƌ����������w6�Њ����x�Ƃ���C�u�ُ�����݉��i�����鉻�j�����鎖�v���wVisual Control�x���X����������܂��B
�g���^���̂��g���^���Y�����Ƃ����Öْm�̉���`���m�ɏ\���o���Ȃ��ŋ�����ɁC�č����炱�̂悤�Ȍ`���m������ďo�ł���C���ꂪ�S���E�ɔ��M����C���{�ɋt�A������Ă���̂ł��B
2000�N��ɓ���ƁC��L��@��D�荞��ERP�����y���X�ɍŋ߂ł͌��z�����~�ŃN���E�h�^��ERP�����y�����̒��ɂ́C��L����h�������ŐV�̉��P��@���D�荞�܂�C�S���E�̂��̂Â���W�҂��g���n�߂Ă���ƌ����܂��B
������{�ł́C���Y�Ǘ����Ɏ��C��w�ň�ʋ��{��g�ɂ��������̐V�l���H��̐��Y�Ǘ��̌���ɔz�����C�ނ��4�`5�N�O�ɐ�y�ɋ����C���ݐ��Y�Ǘ��̎���������Ă���l��E���y�ɂ��āC���̐V�l�����炵�čs���������Ƃ����v���Z�X�𑽂��̊�Ƃł͑����Ă��܂����B�w�����܂łɂǂꂾ���̐��Y������ɂ�点�邩�x�ƌ����H��̐��Y�������߂Ă��܂��@�\���C���Ƒ��Ђ␢�E�̐����Ƃ͂܂��������W�ɁC��y�����y�ւ̋��炾���ōς܂��Ă����Ђ����ɑ����̂ł��B
�����̊�Ƃ̃g�b�v���������������݂�����ɋC�������C�䂪�Ђ̕��������E1�ł���C���̂܂ܐi�߂�̂������̓��Ǝv������ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����c�O�Ȃ̂́C�g���^��1937�N�n�ƂŎႢ��ЂȂ̂ŁC��������ɑn�Ƃ�����肩�猩��Ɓw�V�Q�ҁx�Ƃ��Ĉ����C�����Ő��܂ꂽ��L�̐��X�̎�@���y�̂��ڂ݂��Ȃ��������Ƃł��B
�g���u�����N�����Ă���O�H�C���ŁC�V���[�v�C�_�ː��|�Ȃǂ͂��̓T�^���Ǝv���܂��B
�yB�zTQC�ɂ��ẮC1980�N�č��������ɗ����Ƃ��̓��{�̐�������ł́C1960�N�㔼����̗p�J�n�������ʍ��Z���̍�ƈ����C���Ă�m�I�D��S�����wQC�T�[�N�������x�Ō�����P�ɓ������Ă��܂����B���̌��ʁC�H�ꌻ�ꂩ�玩���I�Ɉ����č��i���̐��i���o���Ă���̂ŁC��Бg�D�̉^�c��̂ł���o�c�w��Ǘ��ґw�́C�o�c�헪�]�X�̓�����Ƃ��l�������Ă��C�����Ƃ̐l�ԊW�����ǂ�����Δ�����Ԃɂ���C���۔���g���Đڑ҂ɖ������Ă��܂����B
���̏�Ԃ��m�F�����č��̒����c�́C��Ќo�c�̐��Z�p�͖����C�����ς��i�ւ̋C�����Ƒ��ЂƂ̐l�ԊW�Â��肾���̊Ǘ��ґw���������{�̎�_�ł���Ƃ��āC�č���Ƃ̊Ǘ��ҋ���ɗ͂����CTQM�ƌ�����@���m�����C�X�ɕč��Ƃ��Ă̖J�܂Ƃ����w�}���R��-�{���h���b�`�܁iThe Malcolm Baldrige National Quality Award�j�x�𐧒肵���̂ł����B���g���[���ЁC�[���b�N�X�Г�������Ɍĉ����ċƐт�L�����ƌ����āC����Ɏh������č��̐����Ƃ͑��𐁂��Ԃ����Ƃ���Ă��܂��B
1999�N���Ă����@�����Ƃ��CTQM�ƌ����Ǘ���@�ŁCTPS��i�߂Ă��饥��Ƃ�����Ƃ����������̂���ۓI�ł����B
�Ԃ��Ȃ����{�ɂ��Љ��C1995�N�g���^�ɂ���������C�����Ǘ������Ƃ���TQM�̐�����܂����B�ȉ��C�̌������ƂɓW�J�@��������܂��B
�悸����ɉ�Е��j�C������j���Ĉȉ��̎菇�Ŏ��{���ڂ����߂܂��B
- Mission-Statement�@�i�����Ǘ������Ƃ��č��N��Mission�͉�������̓I�ɕ\���j
- Performance-Measure�i���̐��ʂ̕]���͉��ŁC�ǂ̂悤�ɑ��肷��̂��j
- Commitment�@�i�K�B�ڕW�Ƃ��Ă̐��l�j
- Target�@�@�@�@�i�o��������܂ŒB���������Ƃ����ڕW�l�j
��i�̕����S�������Ƃ̊ԂŁC��i�̖ڎw�����j�W�J�Ƃ̐��������m�F��C���В��o�Ȃ̉��ŁC����s���ŏI���F�ƂȂ�܂��B���̎��g���^�́CA3�p��1���ɂ܂Ƃ߂�10���ȓ��ŕ��鎖�����߂��Ă��܂����B
�����ɂȂ�ƁC���{���ʂ�Commitment�̐��l�̉����܂ōs�������ƁC�c����Ă���ۑ蓙��A3�ꖇ�ɂ܂Ƃ߂ď�i�ɕ��C�Ō�Ɋ���Ɠ������В��o�Ȃ̉�c�ŕ��܂��B���̐��ʂ��ܗ^�ɔ��f����܂��B
���Y�ɂ�1999�N�S�[�����v�̒��Ƃ��ē�������C�悸�S�[���В����炪��L(1)(2)(3)���f���C�����B��������ׂ̍s���ڕW���e�����Ɋ���t������Ǘ��E�S���ɓW�J�������ƂŁC������V�����v�𐬂�������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B����Commitment�̃t�H���[�������C�Ǘ��E���敾���Ă���ƌ����\������܂����B
�����C��Ƃɋ߂Ă���F���܂ɂ��f������ƁC��L�̂悤��TQM�̐����͖����C�̂�TQC�ƌĂ�ł������C�ŋ߂�TQM�Ƃ����Ăі��ɕς�����̂ł�����Ƃ�����Ԏ����悤�ɂȂ�܂����B
�^�ʖڂɕč����̂s�p�l��W�J�����̂̓g���^�Ɠ��Y�������̂łͥ���ƐS�z�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
���_�Ƃ��ĕ��Ђ́C������30�N�Ԃœ��{������n�ɂȂ��čs�����̂́C��L�y�`�z�Ɓy�a�z�̓W�J���s�\���ł������ׂƍl���ċ���܂��B�y�`�z�̓W�J�͕��Ђ̐��ƂƂ���Ƃ���ł��̂ŁC�����ł������ɗ��������Ɗ���Ă���܂��B
2019�N���U
�i���jJ�R�X�g������ ��\ �c�����m
