�A�ڃR�����w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ڎ�
JBpress�A�ڃR�����w�{���g���^�����x
�r�W�l�X���T�C�gJBpress�ɂ����āA2008�N����2013�N�܂ł̊Ԃɍ��v104��̃R���� �w�{���g���^�����x ��A�ڂ��Ă��܂����B
���ݘA�ڒ��̃R���� �w�i�R�X�g���v�̍l�����x�ƕ����ēǂ�Œ����ƁA���[��J�R�X�g�̍l�������������邩�Ǝv���܂��B����A���L�̃����N�ɃA�N�Z�X���Ă݂ĉ������B
�ߋ��̏��M�\��
2017�N11��
��Ђ́w�Ǘ��K��x��w�Ɩ������x�͂����݂ł��傤��
���l�̎��Z�\�̓`���̊�@��2007�N���Ƃ��Ď��g���A��Бg�D�̊Ǘ��K��̓`�����蔖�������̂ł͂Ȃ����H��
���̂Ƃ��뗧�đ����ɁA���{���\���鐻���Ƃŕs�ˎ�������Ă��܂��B���̎�ȃ��m�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B
- 2017�N
- �@ �x�m�d�H�E���Y�����Ԃ̌��������
�A �_�ː��|�̕i���f�[�^�[������ - 2016�N
- �B �O�H������Catalog�R��̎���
- 2015�N
- �C ����-�����ɘj��s�K�؉�v
�D ���m�S�������f�[�^�[����
�E �^�J�^-�G�A�o�b�N�s�
�����̐����ƊW�҂́A���̕��Ĕ����Ђ��߂܂����C���S�ł́u�䂪�Ђ͑��v�v�Ƃ��v���̂��Ƃł��傤�B
�Ƃ��낪�A�g���^�ł̌����30�N���̌�R���T���^���g��20�N�̎��ɂ́A���Ɍ����u50���E100���v�ŁA��L��Ƃ͕a�}�ς��~�}�Ԃ̌䐢�b�ɂȂ��������ŁA���{�����������a�C�ɜ���ċ���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�����łȂ����Ƃ��F��A���̕����Ă��錜�O���ȉ����b�����܂��B
����́A2007�N���́A���͉�Бg�D�̋K��ނ̓`���ɉe�����Ă���̂ł͂ƌ������O�ł��B
���̉�Бg�D�̋K��ނɊւ��錴�̌��͖�50�N�O�̃g���^�̃f�~���O�܂̐R�����ɂ���܂����B
�����A�R���̐搶�������i���������w��������A������āA��i�͎v���Y�݂Ȃ���A���̎w�E�̈Ӗ����邱�Ƃ𗝉����A��̓I�ɉ����ǂ������ׂ������f���A����̊Ǘ��̐����e�L�p�L�ƍč\�z���čs���܂����B
��i�̂���`�������Ȃ��玄���w�̂́A �w�����𖾂炩�ɂ���x�Ƃ������Ƃł����B
���Ƃɂ́A���̍��Ƃ̖ڎw�������m�ɂ������@������A���̉��ɖ��@�A�Y�@�A���X�̖@��������܂��B���Ƃ̂�����R�g�́A���̖@���ɏ]���Đ�����Ă���킯�ł��B�����Ă����̖@���ɂ͕K�� �w�����̎葱���x�����L����Ă���̂ł��B
�������Ђɒu��������A���@�ɑ������� �w�n�Ƃ̐��_�x�Ƃ� �w�А��x�ƌ������o�c�N�w������A�]�ƈ��ɂ� �w�A�ƋK���x������܂��B��Ђ���̓I�ɉ^�c����ׂ� �w�g�D�}�x������A�e�g�D�̊������e���K�肵�� �w�Ǘ��K��x�ƁA�g�D�łǂ̂悤�ȕ��S�Ő��s���邩���L���� �w�Ɩ������x����������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ɂȂ�܂��B
������̑��ʂ́A���͉����̉�Ђł�����Ă���Ǝv���܂����A �w���j�Ǘ��x������܂��B����́A
��Е��j �� ������j �� �H����j �� �����j �ˉە��j �� �W���j
�ƁATop���疖�[�܂œ����W�J����āA���X���X�ƕω����Ă����s���Љ��ɓI�m�ɉ�Ђ������ς��ēK�����Ă����������w���܂��B�O�҂� �w�ێ������K��x�ŁA��҂� �w���v�����x�ɓ�����܂��B���҂����݂��邱�ƂŁA�����̋Ɩ������Ȃ��Ȃ���A��Ђ͎��ȉ��v��i�߁A�ω��ɑΉ����Ă�����̂ł��B
�f�~���O�ܐR���̐搶�����w�E�����̂́A������ێ����邽�߂� �w�Ǘ��K��x�E�w�Ɩ������x�ƁA�����ς��Ă��� �w���j�Ǘ��x�ɕs���������ƌ������Ƃ������̂ł����B
�R�����Ԃ͋͂�1�N���x�ł������A�H�ꋓ���Ĕ������炯�ł������H��� �w�Ǘ��K��ށx�w�Ɩ������x�����A���[�ނ���ߓO�ꂵ�܂����B�����͎��}�̂ł������̂�1�N�ԂŁA���{�H�ƋK�i�i�i�h�r�j��J��@�̓��֘A�������܂߂�ƁA�������̕Lj�ʂ��A�����ۊǂ��鏑�I�ɂȂ��čs�����L��������܂��B
���̊����̒��ō��ł��N���ɋL�����Ă��鎖��2��Љ�܂��傤�B
�i���Ǘ��䒠

���������A����Ő��Y���Ă��鐻�i�̕i�������̕�W�c���ω����Ă��Ȃ������A�����_���ɒ��o����Sample�i�ʏ�4�j�̑���l�i�v�ʒl�j�̂���ɂ��� �wXbar-R�Ǘ��}�x�����A����ŕω����Ď����Ă��܂��B
����́A�挎�̎��т��瓱���ꂽ95���M���̊Ǘ����E��UCL�i����jLCL�i�����j���L�����L�^���ɍ����̕��ϒl��œ_���Ĉُ�̗L�����m�F���Ă�������Ƃ����Ǘ��Ȃ̂ł��B
����͑O���̕i�����x���ɑ��č����������i�����x�����ێ����Ă��邩�ۂ��̓��v�I���肵�Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��āA���̊Ǘ����@�ł́A�挎�̎��тɑ��� �w���P�ʁx�� �w�T�P�ʁx�̔�r�I�����Ȏ����̕ω��͒͂߂܂����A�ݔ��̗Ȃǂ̂悤�� �w���P�ʁx���� �w�N�P�ʁx�ɘj��W���W���ƕς���čs���ω��͒͂߂܂���B�����͂ނ��߂ɁA���X�̊Ǘ��̂��߂ɎZ�o���ꂽ���X��UCL�ALCL�̐��ڂ��O���t�ɂ��āA�������ω��𑨂��邱�Ƃ��K�v�������ꂪ �w�i���Ǘ��䒠�x�Ȃ̂ł����B
���͂��̃f�~���O������̒��ŁA�i���Ǘ��Ƃ͉�����m�邱�Ƃ��o���܂����B
�̉����ɂƂ��Č�������܂��傤�B��T�ɐl�̊�b�̉���36���`37���ƌ����Ă��܂����A���ۂ͓��X�̕ϓ����l���̕����傫���A�l�̓��X�̃o���c�L��0.2���ȓ����ƕ����܂��B
�l�����傫���̂ŁA���܂���36.5���ł������Ƃ��Ă��A�݂�l�ɂƂ��Ă͔��M��Ԃł��邵�A�݂�l�ɂƂ��Ă͒�̉���Ԃ����m��Ȃ��̂ł��B�����Ȕ���́A�������肵�A����܂ł̑̉��Ƃ̍������v�I�ɗL�ӂŗL�邩�ۂ��̌�������Ȃ��ƁA�ُ킩���킩��������Ȃ��̂ł��B
���݂ɏ����́A�r����D�P�̏����̂��ߊ�b�̉���0.3���قǏオ�邱�Ƃ��m���Ă��܂��B����̖�����b�̉��𑪒肵������Δr������m�邱�Ƃ��o����Ƃ���Ă��܂��B
��Ђ̌���̏������ŁA���������_����Sampling���Ă���Εω���͂ނ��Ƃ��o���܂����A�������ɘj��ω��́A���X�̃f�[�^�[������ׂČ��邵���Ȃ��̂ł��B
�b��_�ː��|�ɖ߂��A�o�|�ނ̋��x�� �w�i���Ǘ��䒠�x���쐬����Ƃ��� �w�Ǘ��K��x���`������Ă���A�|�ނ̋��x�̕�W�c�𐄒�o���܂�����A���x�s���ŕs���i�ɂȂ�䗦�����X�v�Z�ł��܂��B��������A�o�וi���Ƃ��Ă� �w���ہx���O�ɁA�����i���̕ω��ő����邱�Ƃ��o����n�Y�ŁA �w�����ُ�x�Ƃ��Ď��Ə����ł̑���ɂȂ��Ă���͂��ł��B
�܂����̌l�������������Ƃ͓��R�ł����A��Бg�D�Ƃ��Ă� �w�i���Ǘ��K��x���Г��œ`������Ă���A���̂悤�Ȏ��Ԃ͂��蓾�Ȃ��̂ł��B
���̂悤�ɁA���[�������߂�������ނɎc���Ēu���A�l���ւ���Ă��������[����K�����鎖�� �w�@����`�x�ƌ����܂��B
���̑ɂɂ���̂� �w�l����`�x�ł��B
�w�@����`�x�Ɓw�l����`�x

����5�N�قǁA�����̂悤�ɒ�����Ƃ̉��P��`�������Ă��܂����A�K�ꂽ�������{�̍H��́A�ˊo�̂���l�������������ƂŁA�{�l���������Ƃ����E�ɏA���A�S�Ă��ނ̈ꌾ�Ō��܂��Ă����܂��B�����܂ŋ}��������ߒ��ł͕K�v�ł��������ƂƎv���܂����A���ꂩ��V�s��ɐi�o����Ƃ��ɂ́A���̈ӎu����̑����͋��͂ȕ���ƂȂ�܂��B
�������A���̈�l������������Γ����J����ƂȂ�ƁA�u�x���ċC�������Ȃ� �w�����g�킸�C�������x�����������Ă��܂��B�|�������s���A�������m�����ɉ���đ��̈������荇�������āA�������̂��̂����Ă���������ꂪ����5��N�̗��j�ł����A�c�邩�瓟�����܂œ������ۂ������܂��B
�����̂��Ƃ��ƈ��S�͏o���܂���B
���{�ł��A�Ԃ��Ȃ��J�����Վ�����̃��C���e�[�}�̈�� �w�����J�P�u�x���x�ł��傤���A�@�Ă𗝘H���R�Ɛ����o���Ȃ���b�̖��ɂȂ肻���ł��B
�@���� �w�@����`�x��ڎw���A �w�@�̌n���x�����Ă��A�`�������܂��s���Ȃ�������܂��A���Ƃł��u�x�����s���� �w�l����`�x�ɑւ���Ă��܂��̂ł��B
����ꎄ��Ƃ͓��ɁA1990�N��̃o�u���̕���i�����̒|�̃J�[�e�����J�������Ƃɂ�饥��j�ō̎Z���������̗p���T�����ׂ̐���f��A�}���ȋƖ���ITC���A�}���ȊC�O�W�J�Ȃǂ̌��ς̒���v�Ɩ���Display��Keyboard�ɂȂ��Ă��܂��A�K��ނɖڂ�����Ȃ��Ȃ�A�Г��ł� �Ζʂ������ňӎv�a�ʂ����ʂ��������Ă��Ă��邱�Ƃ����W�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
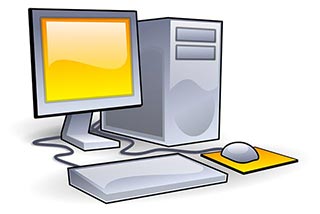
11���ɂ͗��N�x�̉�Е��j�Ƃ��ĐV���Ȃ�e�[�}��T�������Ǝv���܂��B����Ɍ����āA���Ђ̋Ɩ��� �w�l����`�x�� �w�@����`�x�������ɂ߁A �w�K��ނ̍Đ����x�𗈔N�x���j�ɎU��g�ނ��ۂ��̌䌟���̎����Ǝv���܂��B
2017�N9��
�M�B�̎R���ň�������́C�o�R�ƌ����Ζ�ǎd���̉����ł�������܂���ł����B
��������͊C�ł���C�D�ł����B���Ԃƃf�B���M�[�i���^���b�g�j�삵����C�N���[�U�[�i��`���b�g�j�ɃN���[�Ƃ��ĎQ�����C�O�m���[�X�ɎQ�����Ď�������܂����B
�������キ�Ȃ����ŋ߂́C�q�D�ɏ���ẴN���[�W���O�ɊS���ڂ�C�v�w�Ŋy����ł��܂��B����ȊW�ŁC����́C��D�����N���[�W���O�D�̂��b�����`�����܂��B
����N���[�W���O�D�͎��H�������̉���
����6���w���n���C�N���[�Y�x�ɎQ�����܂����B�D��MSC�Ђ́w�|�G�W�A�x(�ʐ^�@)9.2���g���C��q���3,223�l�C��g��1,039�l�ł����B
![9���g���]�̃|�G�W�A 9���g���]�̃|�G�W�A](images/home/Poesia.jpg)
�S��294�b�C�S��32.2�b�Ƃ�������D�Ȃ̂ɁC��]�C���ړ������݂ŁC���͂Őڊ݁E���݂��ċ��܂����B�D���傫�����ă^�O�{�[�g�̔n�͂ł͖��ɗ����Ȃ��Ƃ��ŁC�߂��ŊĎ�����݂̂ł����B�q�s�͐��� �w���H�������x�ł����B
���Ԉ�ʂ̗��q��Ԃ����q�@������������C�Ԍɂɓ���Ȃǂ��Đ��|�E�ݔ��_�����܂����C���̋q�D�͐��N�Ԃɘj���č`����`�ւƍq�s�𑱂��Ă��āC���|�E�ݔ��_���͍q�s���Ȃ��玩�͂ōs���Ƃ̂��Ƃł��B
��ʓI�ɉ��m�q�C����D�́C���D���璴��^�D�ɂ�����܂ŁC�m��Ŏ��͂ŏC������͂������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���C�̏Ⴗ��G���W���̃s�X�g�������܂ŏo����\�͂������Ă���Ɖ]���܂��B
�������ݕ��D�ƈ���� ���̋���ȋq�D�͈��S�ɍq�s�����邾���ł͑ʖڂŁC1,600�]�̋q���������C3,200�l�]�̏�q�̖����Ȃ���q�s���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
������q�̎g�����V�[�c��^�I���̎�芷���E����C�q���̐��|�C�H���̏����C�q��O�������Ȃ����߂̌|�l�B�̃G���^�[�e�C�����g���X�ɁC1,000�l�]�̏�g����24���ԑ̐��ŗՂ�ł���܂����B
�ޓ��̎d���U��̈�[�́C�S�����烁�[�g��������ؐ��̎萠��Ɍ��Ď��܂����B�ʐ^�A�ɂ��邷�ׂ��ׂ̔������ؖڂ��������萠��́C�b�ɗ����Ĕ������i�F�����鎞�ɒN������ɐG���̂ł����C�D�̉����ł����̔������͕ς��܂���ł����B

���̔閧�́C�����������\���[�g�����T���h�y�p�[���|���C�h�蒼���C�ʐ^�B�ɂ���悤�ɗ{�������āw�y���L�h�藧�āx�̕\�������Ă����̂ł����B���̋C�ɂȂ��Ă݂�ƁC�����C�ǂ��C�����������₦�ԂȂ��h��ւ��Ă��܂����B

������C�`�ɒ┑���ʐ^�C�ɂ���悤�ɋ~�������C��ɍ~�낵���^�]���Ă��܂����B�����C��^�D���ڊ݂ł��Ȃ��ό��n�Ȃ̂ŁC���D�̋~�������e���_�[�i�ʂ��D�j�Ɏg���Ă��܂����B
����̏ꍇ�̋~���������I�Ɏg�����ƂŁC��q�ɂ͈��S����^���C�o��ߌ��ƈ�Γ̉^�p�Ɋ��S���܂����B

���̂悤�ɁC���̋���D�̉^�p�͊O���ɗ��邱�ƂȂ��C�����鎖�����X�P�W���[���ɓ��ꍞ�݁C�����B�����Ő��������Ă���悤�Ɍ����܂����B���� �w���H�������x�̉�ł����B
���̑D�� �w���H�������x���H��Ǘ��ɒu�������Č���Ǝ������郂�m����������܂��B
�����ԃ��[�J�[�́C1���C5���C8���ɂ����10���Ԃ̋x�݂��g���ĊO�����[�J�[�����C�V�^�ԗ����グ�̂��߂̐ݔ��������s���Ă��܂����B���ꂪ��ቻ����ƁC�{���͓���ł��ׂ��ݔ��_����F�̐��|�C���̉��C�Ȃǂ��C���������ł��ƘJ����Ƃ��Čv�コ���̂ŁC�������̐��Y�������_���ĊO���ɏo���C�o��Ƃ��Čv�シ��悤�ɂȂ��Ă����܂����B
��ʂ� ���H��Ȃǂł́C�H������C�ޗ����������C���ۈ��S�̗v�̏����H�ꑤ�ŏ������āC�A���o�C�g�𗊂݂܂��B�H�ꑤ�ŏ������镔���ɂ��̂Â���̃m�E�n�E������C���̏�ԂŃA���o�C�g�����N����Ă��m�E�n�E�͂قƂ�Ǔ`���܂���B
��Ɏ����ԉ�Ђ̗�������܂������C1990�N���̂�����o�u���̕���ƌ���ꂽ�����炱�̌X���������ɂȂ�C������20�]�N�C���݂̑��Ƃ̂قƂ�ǂ̍H��ł́C���H�ꑤ�ŏ������Ă��鍀�ڂ��O���ɏo���C�A���o�C�g�ɂ�点�Ă���P����Ƃ𐳎Ј��ɂ�点�Ă��܂��Ă��܂��B���̌��ʁC�A���o�C�g�I�Ȏd�������o���Ȃ��Ј����唼�ɂȂ�C��Ђ̂��̂Â���̃m�E�n�E���p�����Ă��āC�O���̂�����d���ɑʖڏo���ł���l�ނ́C��N�ԍۂ̈ꕔ�̐l�B�̒��ɂ������Ȃ��Ȃ��Ă��鋰�ꂪ����܂��B
��Ђ̍H��ł͔@���ł��傤���H
�����ł��b�������C���̑D�� �w���H�������x�Ԃ�͎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
2017�N8��
�w���n�����x�̎��I�w���̌��x
����� �w���n�����x�̎����o������ �w���̌��x�����b�����܂��B
���N��2017�N�A�����g���^�ɓ��Ђ����̂�1967�N�ł��̂Ő���50�N�߂������ƂɂȂ�܂����A�g���^�ʼn߂�����33�N�ԁA���̂����w�ł�7�N�ԁA���̌�R���T����Ђ������Ă�10�N�Ԃ̊������x���Ă��ꂽ��̒��́A�����炨�b�����܂� �w���n�����x�� �w���̌��x�ɂ����̂ł����B
�w���̌��x����1
���Ћ����s��ꂽ2�����Ԃ́w���ꉞ���x
�V���Ј�����ł�2�T�ԁ~4�E��� �w������K�x������܂������A����͂����܂ł������Ƃ̑̌����_���ŁA��Ɨʂ�1�l�H���̈ꕔ�ɉ߂��܂���ł����B
�������A �w���ꉞ���x��1�l�H�Ƃ��ăJ�E���g���ꂽ�v���ł�����A���̖{���͑S������Ă��āA�ꍏ��������l�O�ɂ��Ďd�������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B����͐��� �w���ԍH�x�Ƃ��č̗p���ꂽ�l���g���^�̌���łǂ������āA�ǂ���l�O�Ɉ�Ă��邩�� �w�̌��R�[�X�x�ł��������킯�ł��B���̎��̑̌����A���̃��C����Ƃɑ��l�����̊�b�ɂȂ�܂����B
���̎��Ɋw���Ƃ̊�����Љ�܂��傤�B
-
�w�R���x�A��Ɓx�͉���̃G�X�J���[�^�[��2�K�ɏオ�낤�Ƃ��Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�����Ă��A�����Ă��A�K�i�͍~��Ă���J��Ԃ��ŁA�ω����~�����Ȃ�܂��B
���i������ɂȂ�A����ւ���̂��y���݂ɂȂ�܂��B
�P��Ԏ퐶�Y��� �w���Ԏ퍬�����Y�x�̕����ω��������Ċy�����̂ł��B - ���i�ƃ{�f�[�̐��x�����킸�A�������Ȃ�����t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���Y�����������̂ŕ��������܂��B
- ��Ƃ̒��ɉۑ�������A�H�v���Ȃ����Ƃ�����ƃQ�[���̂悤�ɂȂ�y�����Ȃ�܂��B �wKAIZEN�x�̈Ӗ����������Ă��܂��B
-
�w�����Ɓx�قǁA���b�オ�o�ė��邵�A����̂��҂��������Ȃ��܂��B
���l�̏o���Ȃ���Ƃ��o���鎖�������̃v���C�h�ɂȂ�܂��B - SPS�i���i�Z�b�g�����j�͎��R���D����̂ŁA �w���肪�����f�x�A���Ԃ�������Ď�����Picking���������y�������A��Ǝp���̕ω����t�����Đg�̂ɗD�����B
- ��ƒ���Leader������Ă��Đ����|���Ă����̂��������������A�C���]�����Ă����ƌ����āA5���Ԃ��炢����1�������Ƃ�����Ă����̂����Ɋ������B
- ���ߕt���H��̑���Ɋ���āA�x�e�����Ƒ��F�Ȃ������ō�Ƃ��o����悤�ɂȂ�������A���ߕt�������Đ��ۂ����ʂł���悤�ɂȂ��������傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂����B
����炪�g�ɂ������A�ŁA�����g���v�ƍ�Ɛ��ɂ��Ēk���ł���悤�ɂȂ�܂������A����̒��ԂƂ��Ď������悤���Ȃ�܂����B
���̂��̌o������A�H�Ȍn��w�o�g�҂�1�l�O�̋Z�p�҂Ɉ�Ă邽�߂ɂ́A������Ԃ������� �w��H���Ƃ��Č���̌������邱�Ɓx�����E�߂��܂��B
�w���̌��x����2
�w�Ǘ��\�͌���v���O�����x�̑�M�o��
�����̃g���^���Г��̐����猩��ƁA1965�N�f�~���O�܁A1970�N�f�~���O���{�܂��A������}��܂������A��10�N�o�߂���1979�N�ɂ́A��ܓ����̕��ے�����N���}���A �w�Ǘ��\�̗͂x�����O�����悤�ɂȂ�܂����B
���̈���Ńg���^����芪�����́A
1970�N�܂�1�h��360�~�ł������A1971�N�̃j�N�\���V���b�N���o��1978�N�ɂ�1�h��176�~�ɋ}�����Ă��܂��Ă��܂����B
1973�N�ɋN������1���Ζ��V���b�N�Ō������i�͖�20�{�ɂ��������A���̌㉺�����Ă������̂�1979�N�ɂ͑�2���Ζ��V���b�N���N���܂��B��1980�N����͖{�i�I�Ȕr�C�K�X�K�����n�܂饥��Ƃ����ɂ߂Č���������}���Ă��܂����B
����ɑΏ����ׂ��A1979�N1�����畔������ΏۂƂ��� �w�Ǘ��\�͌���v���O�����x���J�n����܂����B
��̓I�ɂ� �w�H�꒷���j�x���Ē�߂� �w�e�������j�x�̒��̍ŏd�_���ڂ����グ�A���̋�̓I�� �w�W�J�x �w�i���x�� �wA3�p���x1���ɓZ�߁A 8�����ŗ��H���R�ƕ�����Ղ� �w�����x�ɐ������楥��Ƃ������̂ł����B
��i�ł���M�����͓����W���ł��������ɂ�����}���������Ă���܂����B
�������ȕ�����2�l�ŋ�S�S�邵�Ď菑���Ŋ��������A���N�`���[���Ĕ��\���ɑ��荞�݂܂����B���\�̏��M���������w��w���x�͑������Ă�����̌��t�Ƃ���M�������獐�����w�o���̈������������Ƌ�J����x�ƌ��݂܂Ō����܂������A�W���̕��ۂŕ�����������Ē��������́A���ɂƂ��Ă͑�ϋM�d�ȑ̌��ł����B
�w���ꉞ���x�� �w�Ǘ��\�͌���v���O�����x�� �w���̌��x�� �w���n�����x���� �w����x�ɏo�|�� �w�����x���ώ@���A ���́H���́H����Ƃ������Nj��� �w�^���x��T�蓖�đ�Ƃ��� �w�s���K�́x������ɂȂ����ƍl���Ă��܂��B
���P�̂���`�������Ă��钆����Ƃ̘b
��������͖���1�T�Ԃقlj��P�̂���`�������Ă��钆����Ƃ̘b�ł��B
����͍ŐV�̐ݔ����ݒu���Ă���A����Maker�̊�V�X�e������������AOffice�ł͎����E����Display��Keyboard��O�ɖفX�Ɠ����Ă��܂����B�Ƃ��낪����ɂ͍ɂ̎R������A����ł͌��i������A�ƂĂ��L���Ȋ�V�X�e���̐��ʂƂ͎v���Ȃ��̂ŁA���ӂ� ���́H���́H�𒆍��l�ɂԂ��܂����B
���̌��ʁA�����ׂ����ɁA�N����V�X�e����Logic��m�炸�A���i���[������Ă����̓��̂����ɓ��͂���Ηǂ��ƍl���A�A��ԍۂɓZ�߂ē��͂��Ă��܂����BSupplier�ւ̔[���w���́A�v�ύX�������Đ��Y�v�悩��S�čČv�Z���Ď���͂��鐻�i�Q������A2�`3���x��Ĕ������Ă��镔�i������܂����B
���ɂ͌o�c�҂̐e�ʂ��ƌ����āAKeyboard���낭�ɑłĂȂ��悤�Ȑl������A�d�����x���ǂ��납�A�x��Ă����C�ŋA���Ă��܂��n�������ł����B
�Ƃ���ŁA�F���܂̉�Ђ͏�L�̒����̗�𑼎R�̐Ƃ��Ă��m�F�������߂��܂��B
8���ƌ����A�{�N�x�̐V���Ј������Ћ�����I���E��z���ɂȂ鎞���ł�����܂��B
��������ɍ�ƈ��Ƃ��Ĕz���ɂȂ�ꍇ�̐E�ꋳ��́A�K��������A�H��戵�̊�b�P���A��ƌP���A��Ɨv�̏��ɂ�� �w���˂Ȃ�Ȃ����x�w����Ă͂Ȃ�Ȃ����x����@�����܂�Ďd���ɏA���܂��B
���̒m�邩����A�����H��ł͂��郌�x���Ŏ��{����Ă��܂��B
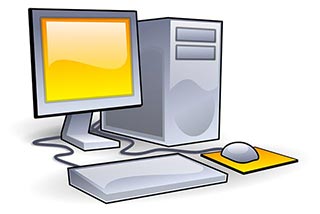
���̈���ŁA�w�ǂ̑呲�҂͎������ɂ��āADisplay��Keyboard��ɂ��Ă̍�ƂɂȂ�܂����A��Ђ̑呲�V���Ј��̏ꍇ�͂ǂ�Ȋ�b���炪�Ȃ����̂ł��傤���B
Keyboard����̊�b�P���ͥ���AComputer Literacy �͂ǂ��c�����Ă��܂����H��V�X�e����Logic�͋�������ł��܂�������
Display�ɕ\������Ă���f�[�^�͉����łǂ̂悤�ɂ��Čv�����A�ǂ̂悤�ɂ��ē��͂��ꂽ�A���̃f�[�^�[�Ȃ̂ł��傤���H
�V���Ћ���݂̂Ȃ炸�A���݊e������Display��Keyboard�ł���Ă���d���̑��_���ƁA�Ɩ������̌����������E�߂��܂��B
���ɂ��̂Â���̊�{���Ɋ�{ �w���Y�v��x�͂ǂ̂悤�Ȋ�{�f�[�^�[�����ƂɁA�N���A�ǂ̂悤��Logic�ŗ��Ă��āA�ǂ�Ȏ葱���Ō��肳��A�ǂ̂悤�ȑ����œW�J���Ă���̂��H
����̉�ЂŒ������܂������A������ �m���L�����Ј��̊��ł���Ă��܂����B
2017�N7��
�������w���n�����x�ɗ����Ԃ�ׂ�
���C���{�����������E�̊�ՁC���䑏��4�i�̉��i���ɕ����Ԃ��Ă��܂��B
29�A���ƌ�����O�̋L�^�����C7��2���ɂ�30�A���Ȃ邩���������t�@���݂̂Ȃ炸�S�������ő���ۂ�Ō�����ċ��܂��B������ăe���r�e�ǂ͋����ē���l�i�̂���܂Ő������Ă����o�܂�C����̓w�͂Ȃǂ̘b������グ�C�����E���\����悤�ȊF�l��������Ă��܂��B�����������܂�Č��Ă��܂����B
�e���r�����Ȃ��玄�͒m�l���畷���� �w�l�ނ́yA�z,�yB�z�̓�̔\�͂�g�ɂ��邱�Ƃō����̔ɉh����ɓ��ꂽ�x�ƌ����m�l�̘b���v���o���܂����B�ȉ����̎�����܂߂āC���C���{�ŋN���Ă��鎖�ւ̎��̌��O�����b���������Ǝv���܂��B
�yA�z�l�ԂƐl�Ԃ��q���\��
�悸���̈�ł���Communication�ɂ��ẮC���\���N�O�̋��Ί펞�㖘�k��܂��B ���̍��l�ނ͊���̉Ƒ������̌`�œ��A�ɏZ��ł��������������Ă��܂��B�Q����Ȃ��Đ������C�����B��苭���l������邽�߂ɂ͂��Ȃ荂�x�Ȉӎv�`�B���K�v�ɂȂ�܂��B�����͖R������b�ƁC��̕\���g�U���U��ł��݂��̋C����l����`�������Ă����ƍl�����Ă��܂��B���̏�Ԃ����\���N�������̂ŁC�\��₵�����ő���̋C�����𐄂�����ƌ����l�ދ��L�̔\�͂�g�ɂ����̂ł����B
���̌�e�n�ɎU��C�Ǝ��̌���╗�K��g�ɂ��Ă����C�W�����獑�ƂƂ�����K�͂ȏW�c���c�ނ悤�ɂȂ��čs���܂����C�c�悩������p�������̔\�͂�����̂ŁC���t�̕ǂ��z���āC�������ӏ܂���C�O���f�悪��f�����̂��ƌ����܂�����������B
�yB�z�l�ԂƎ��R�E���q���\��
���R�E���ώ@���C�l����������\�́C�H���̉ʎ���T�����Ă�\�͂Ȃǂ��w���C���̔\�͂̂��A�Ől�ނ͐����������܂����B�X�ɐi��œ������������炵�ĉƒ{�Ƃ��C�����Ă���q���юU�炳�Ȃ��A�������C������͔|���鎖�ő�ʂ̍�������ɓ���C�X�ɕz��D��C�ߕ������C�Ɖ������܂����B
�₪�đ��z��̓�������?�����C?�ɍ��킹�ďW���S���Ŕ_��Ƃ����邱�ƂŌ������グ�h���h���L�ɂȂ��čs���C�l�ނ͕��������グ�ė����̂ł����B
���́yA�z,�yB�z�̔\�͂͒N���������Ă��܂����C�Љ�̐i���ɔ������Ɖ�����Ă����C�yA�z�̗D�ꂽ�l�͐l�X�𑩂˂�d���ł���w�m�x�w���x�ɏA���C�yB�z�ɏG�ł��l�͎��R�E�̌b��l�X���K�v�Ƃ��鏤�i�ɕς��Ē���C�w�_�x�w�H�x��S���悤�ɂȂ��čs���܂����B
���̕��S���蒅���C�X�ɍו����E��剻���i�ނƁyA�z�ƁyB�z�̋C�����ȉ��̂悤�ɕ�����Ă����܂����B
�yA�z�ӂƂ���l�ԌQ�i�Љ�Ȋw�I�j�̓���
��Ћ߂̖w�ǂ̐l�����̕��ނɓ���܂����C��O�ɂ���w���x��w�w���x�̐��ۂ����C���̐l�ԊW�Ɉ�Ԃ̊S�������C���ɗn�����݁C���������邱�Ƃɕ��S���܂��B�X�ɔ\�͂̂���l�B�́C���̐l�ԊW�̒���Leader Ship������悤�ɂȂ�,�X�ɂ��̐l�ԊW�𑀂鎖�Ɋ�т�������悤�ɂȂ�܂��B
���ʁC���Ђ�@���ɐ��������邩�ƌ��������Ƃ��C�Г��̐l�ԊW�ɋ����S�������C�ǂ̔h���ɑ����Ă��������L�����C�N�̂��������ׂ����Ȃǂ�k�������鎖�ɕ��S���܂��B�\�͂̂���l�͎Г��ɑR��ׂ��l�����\�z���܂��B
���ɒ������l�͎ЊO�ɂ������l�������グ�ċ��܂��B�����Ĉ�U�Г��ʼn������ׂ��ۑ肪���������Ƃ��ɂ́C���̐l�����������đf�����������Ă��܂��܂��B���ꂪ�Г��ŗh�邬�Ȃ��]���C�o���X�������l�߂₪��Top�ɂȂ�ꍇ�������悤�ł��B�q�ϓI�ɂ�����ێ��ɂ͂���͕K�v�Ȃ��Ƃł��B
�������C���̉����@�� �w�����̎��Ђ̘g�g�݁x�̒��ōs���邱�ƂȂ̂ŁC�s��Ƃ̃Y�����痈����ɂ́C�t�ɁC���Ԃ����������Ă��܂��܂��B
�ꍏ�𑈂����}���u�� �w�����̎��Ђ̘g�g�݁x�̒��ōs���Ƃ��Ă��C�{��č쐬���ɂ� �w���n�����x�ɓO���āyB�z�̐l�Ԃ��g���Ď��Ђ̎d���̐i�ߕ��ƌ���̎s��Ƃ̊W���������_�����C������Ďs������[�h�ł��Ă��邩�ۂ����m�F����Ƃ��납��n�߂Ȃ���ΐ���܂���B
���̓_����ӂ�Ɖ�Ђ� �K���p�S�X������Ă����܂��B
�yB�z�ӂƂ���l�ԌQ�i���R�Ȋw�I�j�̓���
�l�ԊW�������R���ۂɋ����S�������C��O�ɂ���w���x��w����x�̐��ۂ��C�ɂ��܂��B������m���߂悤�Ƃ��Ĉ�l�Ŋώ@������C�l�����肷�鐫�Ȃ�����C������w�ϐl�x�Ƃ��w��l�x�Ƃ��Čy�̂��ꂽ�肵�܂��B
���w���l�̐S�x��w���̏�̕��͋C�x���@���邱�Ƃ����Ȃ̂Łw�j�x�i��C���ǂ߂Ȃ��j�x�Ƃ��Ĕn���ɂ��ꂽ�肵�܂��B���������R���ۂɑ��銴���͉s���C��Ђɂ����Ĉُ�����Ď��̂𖢑R�ɖh������C�i���s�ǂ̐^�����𖾂����肷��̂͂��̐l�B�Ȃ̂ł��B
�X�ɔ\�͂ɒ������l�͎s��̕ω���Catch���āA �w�V���i�x���Y�ݏo������C���Ђ̋Ɛт��ώ@���� �w�o�c�ۑ�x�����݉�������ȂǁC��Б����̂��߂̍ł���ȕ�����S���l�ނƂ��ĕK�v�Ȑl�ނȂ̂ł��B
�l�������z���o���Ȃ����̓e���r�h���}�́w���_�x�� �����E����C�w�ȑ{���̏��x�� ��}���R���������������B���������̃L������ǂ��\�����Ă��܂��B
��������́C���̕�����ŁC��Ƃ̉��v�E���P�Ɩ��Ɍg����Ă�����ƂƂ��Ă̗��ꂩ��C����4�`5�N���̂Â��茻��Ŏ��������n�߂��S�z������������܂��B
�yA�z���ŋߕ��������
���q���ׁ̈C�q���B���Q��ɂȂ��ėV�Ԓ��ł̉������ւ̂�������CLeaderShip�����Ă̋��������̂��ꂪ�Ȃ��Ȃ�C�ʂƌ������ċc�_�������������@��������܂����B
�X�ɃX�}�z�̕��y�ŁC�ׂ荇���č����Ă����ɃX�}�z���̂������݁C�Q�[�������邩�C�����̓��N�̃����F�ƊG�����̒ʐM�����饥��Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B������킹�Č��킷��b�́u�����I�����I�ق�ƁI�����`�I�v�ő�\�����悤�Ȍ�b�̏��Ȃ���b�B���ꂪ10�]�N�O��w�ŋ��������Ă������̊w���B�̃R�~���j�P�V�����ɑ�������ł����B
���̊w���B�̐��オ���C��Ђ̎�����S��30��Ƃ��ē����Ă���̂ł��B
�yB�z���ŋߕ��������
���R�E�Ƃ̐ړ_��S���yB�z�́C�����Ƒ�ςȎ��ɂȂ��Ă��܂��B�q��Ē��̐���͓s���炵�̂��߁C���̎q���B���厩�R�������̌܊��Ŋ�����@����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�w�Z���ނ̕��͂�摜�Ŋw�Ԃ�������܂���B
1990�N��ɂȂ�ƃC���^�[�l�b�g�����y���C��������ǂ̂悤�ȏ�������o���C���ڐ��͖c��ɂȂ�܂������C���e�͕����Ɖ摜�ɂ͕ς��Ȃ��C�ق����ƂɒN�ł����e�o���邽�߁C�w�Q�ӏۂ�]���x�ƌ�����x�̋��b�ʂ�̏���Ă���̂������ł��B
���̈���ŁCComputer�̂�����2000�N��肪���݉����C��������z���邽�߂Ɋe��Ƃ͎Г��̊�V�X�e�����X�V�����ƌ����Ă��܂��B���̌��ʁC��Г��ł͉c�Ƃ���̒���������͂�������CComputer���u�ޗ������v�u���Y�w���v�u�[�i�w���v��������Ă����̂ŁC �w���n�����x�ɂ��m�F�͑S���s�v�ŁC�e�����͂��� �u�w���v�ɏ]���č�Ƃ���Ηǂ�����Ƃ�����20�N�߂������Ă���ƌ������ɂȂ�܂��B
�Ј��̔N��猩��ƁC�ے��w�̒����ȉ��V���Ј��Ɏ���܂ŁC���Јȗ��CDisplay���Computer����̎w�������āCKeyboard��@���ĉ���Ƃ�����Ƃ���������ꂸ�C�ǂ��Logic�œ����Ă���̂��C���ꂪ�ǂ��Ȃ��ċ���̂��C�ǂ�Ȏ��ԍ��Ȃ̂� �w���n�����x�Ŋm�F�ł��Ȃ��܂܍�Ƃ��Ă��饥��ƌ������Ԃ�����̂ł��B
�ȏオ�C���˂Ă�������Ă������̌��O�ł��B
�ŋ߁C���́u���O�v�������ƂȂ��Ă��܂����B
�}�X�R�~�������ɉ��߂���C ���ł����������Ȃ����̂́C�č��̌������݉�Ђ� �w���n�����x�ɂ�钲���������C Display�iComputer���o�������_�j�Ŕ��f���Ĕ������C���̌��Display��Key-board�őΉ����Ă������߂ŁC�����ƌ����yA�z�̐l�ނ���� �w���n�����x�̏o����yB�z�̐l�ނ����Ȃ������ׂƗ����o���܂��B
�^�J�^�̓|�Y�����l�ŁC�����}���o�c�������ƕ����Ă��܂����C�^���Nj����C�s��̓��������ɂ߁C�ꍇ�ɂ���Ă̓N�r���o��ŎВ����������yB�z�̐l�ނ����Ȃ������ׂł���ƌ����܂��B
�O�H��MRJ�̊J���x����C�J������Ő^���u����v��ǂ����߂�yB�z�̐l�ނ̐�Ηʂ��s�����Ă��邽�߂ƕ����Ă��܂��B
����Ȍ��O������Ă����Ƃ��Ɍ����̂��C
���w���ł��铡��l�i�̖ڂ������銈��ł����I
�����̐��E�́C���ۉ�����ēƎ��̃��[�������郂�m�́C���̐��w�ł���C���ɁyB�z�̐��E�ł��B���̊���Ɏh������āC�����w�������킵�n�߂��ƌ����܂��B��ϊ����������Ƃł��B
�싅�̐��E�ł����������w���̒��{�I�肪���E�̋�����ɑ劈������Ă���l�q�ł��B�싅�͑���̓������u���ɓǂ݁C�����̑̐��̗����U���m�I�X�|�[�c�ō݂�ƕ����܂����B
���ɁyB�z�̐��E�ł��B�ޓ����h���ɂȂ��āyB�z�̐l�ނ��y�o���邱�Ƃ��肤����ł��B
�Ō�ɊF���܂ɂ��肢���������ƁE�E�E
�����w���̏��N�́C
�l�ԊW���C�ɂ����C����l�i�⒣�{�I�肪�撣���Ă���悤�ɁC �ǂ�ȕ���ł��ǂ����� �w���肽�������̖������x��ڎw���Ă�����Ă��������B
���ꂪ������ς��C�����ς��Ă������C�Љ���߂�l�ނɂȂ��čs���܂��B
���������̉ߒ����C�F����� �w�[�������l���x���̂��̂Ȃ̂ł��B
���ɉ�Ђɋ߂Ă��āC���̌��O�ɓ�������F�l�́C
Display���痣��Č���ɍs���C�ւ���Ă��鐻�i����Ɏ���Đ悸���̎����𖡂���Ă��������B
���ɁCKey-board��@���ďo��������ւ̎w���́C�����ɏo����C���ۂɂ͂ǂ�ȍ�Ƃ��n�܂�C�ǂ��I���C�I�������ǂ�Ȍ`�ł��ꂪSystem�ɓ��͂����̂��C �w���n�����x�Œ��ׁC���Ђɒ��Ō䎩������������Ă���̂�������m�F���ĉ������B
���ꂪ�I�������C���̃z�[���y�[�W�ɘA�ڂ���Ă��� �w�i�R�X�g���v�̍l�����x �V���[�Y�����ǂ݉������B�ǂݏI���ƁC���Ȃ��� �w�����b��C�����b��x��^���Ă���铹�������Ă��邱�Ƃł��傤�B
2017�N6��
�挎�̂���[���C�V�����Ŗ��É��ɋA�낤�Ƌ��s�w�ɒ������Ƃ��C�w�̒��ɑ吨�̍��Z���Ǝv���鐶�k�B�����ɍ����Ă��܂����B���ɒ��ɐK��t���č���Ƃ����o���������Ȃ����ɂ́C���̎p�ɋ���Ȉ�ۂ��āC�{�E�ł���u���Y�v�u�����v�Ɋւ��Ă̎v�������ݏグ�Ă��܂����B
�m1�n�c�̋q���^�Ԏ��̓��
���S�l�P�ʂ̐��k�B���������邱�Ƃ͑�ςȂ��Ƃł�����C���P�ʂʼn^�s����V������Just In Time�őΉ����邱�Ƃ͑�ςȂ̂ŁC���߂ɗ��đ҂����邵���Ȃ����Ƃ͗����o���܂����B��������搶���̂���J���Â�܂��B
�����V����������ςŁC�قږ��Ȃɋ߂���ԂŁC�������莞�^�s���Ă���V�����ɁC�����Ȃ�P��Ԃɐ��S�l�̒c�̋q���悹����_�C����������E������ł��傤�B��A�̋q�ɂ͖��f���|���Ȃ��悤�Ɏ����\�ɂ͏����Ă��Ȃ��c�̐�p��Ԃ��d���āC�����Ԃ̍��Ԃ�D���ĉ^�s���Ă���l�q�ɁC���Ǝv���܂����B
�g���^���Y�����̗���Ő������܂��ƁC�V�����̒ʏ�^�s�́C�V��j�������u�Ė����Ȃ��������C��Ԍ���1�l�P�ʂŔ̔����Ă��܂��B����̓g���^���Y�������ڎw�����ɂ̎p�C�������������Ắw1�����x�ɑ��Ȃ�܂���B���̌��ʌڋq�͑҂����ɏ�肽����Ԃ̐Ȃ��m�ۏo����̂ł��B�H��ł��C�s��̗v���������ɑΉ��o����̂ł��B
�t�� �w�������x�� �w1�����x���o���Ă���H��ł́C�働�b�g�̒����͐܊p�� �w�������x�� �����Ă��܂��̂ō���̂ł��B
���Ɏ��������Ńg���^��Supplier���P�����Ă����Ƃ��C�A���`�g���^���̎����ԍH�ꂩ��˔��I�ɑ働�b�g�̒�������э��݁C���̎����ԉ�Ђ̕��͍ɂ�����đΉ�������Ȃ������ꂢ�v���o������܂��B
���̂��Ƃ��������̂ŁC�C�w���s�q�̈����Ɋ��S�����̂ł����B
�����ĉc�ƊW�̕��ɐ\���グ�����̂́C��ʂɎ���̂͌��\�Ȃ̂ł����C�[�i�͐��� �w�������x���Ď��Ђ̐��Y�𗐂��Ȃ��悤�ɂ��Ăق������̂ł��B
�m2�n�̂̓n���M�ͥ���
���݂̗�Ԃ́u�莞�s��ʁv�A���ŁC�q��҂����Ȃ��^�q�ł����C�̂̓n���M�ł́C��p�̏M������C��C�̑D���������̂ɕ��C�ŋq��҂����^�s��C�ӂɌ��炵�āC���������u��ʕs����v�I�^�p���Ă����悤�ł��B
���݂Ƀg���^���Y�����ł́C�^���̉��P�Ƃ́C1�Ԃ͋����˂��ĉ^���������Ƃł���C2�Ԃ͍ő�����p�x�ʼn^�Ԏ��������Ă��܂��B���̓n���M�Ō����C�D�������āC�������x�����Ă���̂ł���C���̑D������ɖڈ�t�����Ă��������C�q����l�ł������Ȃ炻�̋q���������݂ɉ^�ץ��
�܂�C�q�̑҂����Ԃ��ŏ��ɂ��鎖���l����Ƌ����Ă��܂��B
���ۂ́u�M�h�v�Ƃ������t���c���Ă���悤�ɁC�n����ɂ͏h���⒃��������C���l�͂����x�e���������ŏM�ɏ����n��������Ƃ���Ă��܂��B
���̎��Ԃ͏������ɁC�q���M�h�ɓ����Ĉ��H�𒍕���������I������������v����Ģ�M���o�邼�`��Ƃ����Ăѐ����o�����C���H���o�����ɋq���M�ɑ���C�ׂ��Ă��鈫���M�h�̘b������܂����C�ڋq��1�ɍl��Lead-Time�Z�k���ɓw�͂����Ƃ͌������������ゾ�����̂ł��傤�B
�M�h��q�ɁC�n���M���g���b�N�ƊE�ɒu��������Ό���ł��v�������邱�Ƃ�����悤�ȋC�����܂��B
�m3�n���Y�v��ɐV�����������̂����祥��
���N�C�~�E���E5���A�x�ɂ͐V�����̍�����j���[�X�ɂȂ�܂��B�����\�ׂ�Ƃ���ȊO�̋G�߂ł����܂߂ɗՎ���Ԃ𑖂点�Ă���̂�������܂��B�����O�N�x�܂ł̎��т����Ƃɉ^�s�_�C���i���Y�v��ɑ����H�j�����߁C��ؕ��ƌ������i�v��o���ċ��āC�e���ɂ��鎩���̔��@�ōw���ł���悤�ȒZ��Order-to-Delivery-Lead-Time�Ŕ����Ă��鎖�������o���܂��B
��ʊ�ƂŁC���̐V�����̐ؕ��Ɠ��������Ő��Y������ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�Ⴆ�C�P�����Ƃ������v�\���Ɋ�Â��Č��Ԃ̐��Y�v��𗧂āC���Y�̍\���i��Ԃ̃_�C���ɑ����j���s���܂��B�ڋq����̃I�[�_�[�́C�����̉����̗�Ԃ̎w��ȂƂ�������ɐ��Y�v������߁C����������玟�̗�Ԃ����E�߂��Č��߂Ă����܂��B
����ɂ���Čڋq�ɉ���I�ɒZ��Order-to-Delivery-Lead-Time��ł��C�X�ɂ���ɂ���Čڋq�ɓ���������������悤�ɁC�������������m�点�ł��܂��B
��ʂɗ\�Z�����@���̗p���Ă����Ђł́C��Ȃ�����Ƃ��̕����Ԏ��ɂȂ�ݒ�����܂�����C�ڋq��Lead-Time�v���������Ђ̌������̗��v��Nj����C��ɖ��ȂɂȂ�悤�Ƀ_�C����g�����Ƃ��܂��B���ꂪ���ɂ���������J��ɋꂵ�ތo�c�𔗂��Ă��錳���ł��B
�V�����̐Ȃ̂悤�ɁC�H��̃R���x�A��ɗႦ��Ȃ������Ă��C���Lead-Time�ŒZ��ڎw���ڋq�̖����Ďs���͂ݍ����v�Ő��������Ƃ�ڎw���ׂ��������C���M�����[�ȑ�����k�ɂ́C����Ȃ�̎��O���������C�C�w���s�̂悤�ɓ��ʗ�Ԃ��d���Ă�Ƃ��C��q�̐�Ηʂ��ႤJR���C��JR�����{�Ƃ̊Ԃł͏�q�̗����iLead-Time�j�m�ۂ���ׂɁC���p���n�_�ł͕p�x�͊m�ۂ�����ŁC16���A����8���A����4���A���Ȃǎԗ��������炵���v�����m�ۂ��Ă��铙�X�C�w�Ԃׂ��_�������B
���ꂩ��u���̂Â���o�c�v�͌ڋq�ւ̗����̌��オ�K�{�Ǝv���邪�C�V�������F�X������^���Ă����B�����Ƃ�����������悤�ƎԒ��ōl���Ȃ���A�r�ɏA���܂����B
